2025.4.5
武田信玄の野望を叶えた信州味噌
当記事は公開終了しました。
2025.4.5
当記事は公開終了しました。
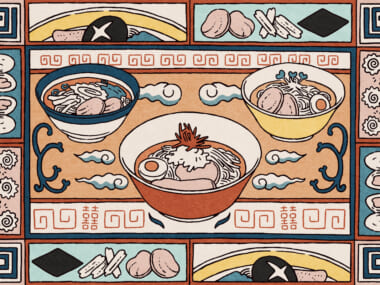
西の味、東の味。

西の味、東の味。

西の味、東の味。
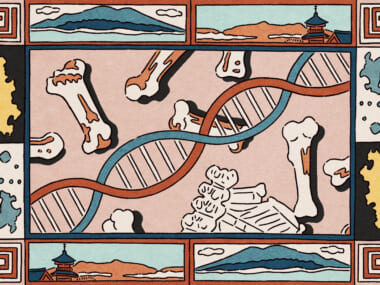
西の味、東の味。
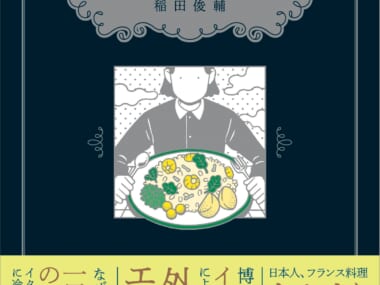
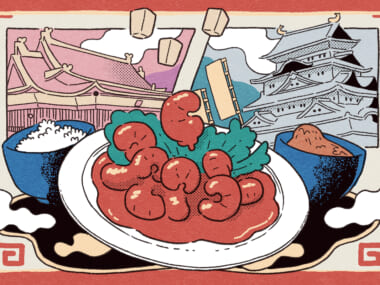
異国の味

2026/2/26
NEW

2026/1/26
NEW

2025/11/26

2025/10/24

ヘルシンキ労働者学校——なぜわたしたちは「ボーダー」を越えたのか


実録・メンズノンノモデル 創刊40年の歴史を彩る男たち

実録・メンズノンノモデル 創刊40年の歴史を彩る男たち