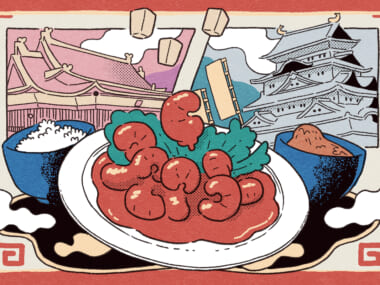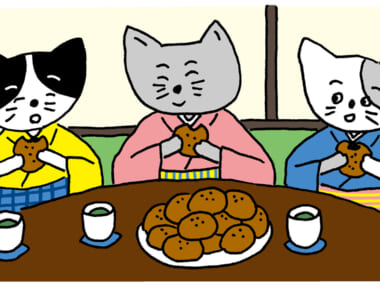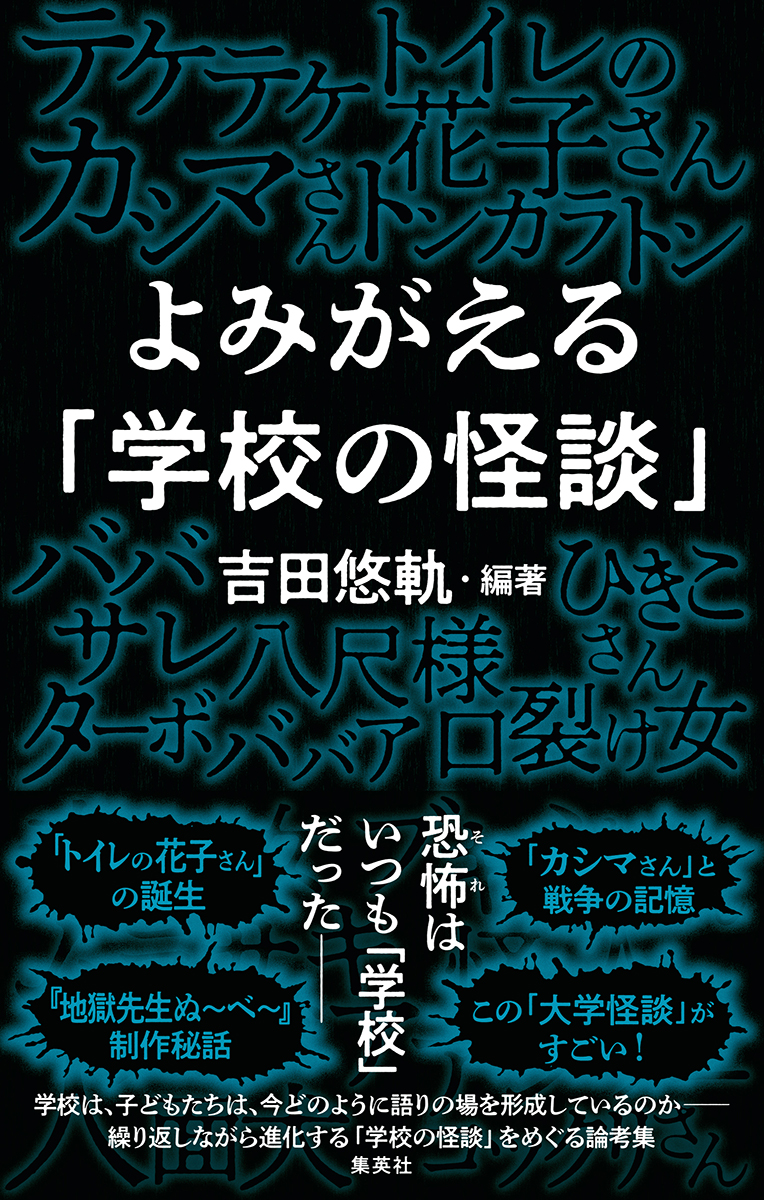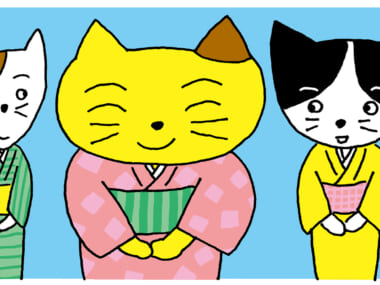2024.3.16
いつから、日本のうどんは「讃岐うどん一強」になったのか
日本の「おいしさ」の地域差に迫る短期集中連載。
今回から、全5回にわたり「うどん編」です。
初回テーマは、今や日本のうどんと言えば…の「讃岐うどん」の普及について。
うどん編① 讃岐うどん、まさかの天下統一
小学生の頃、家族で家でうどんを食べていたら、父親が突然、
「みんなでうどん屋をやろう」
と言い始めたことがあります。曰く、お母さんのうどんつゆは絶品だから俺がうどん打ちさえ習得すれば絶対に店ははやる、と。もちろんそれは冗談であり、母親もそれをハイハイとあしらっていたのですが、そこには微妙なリアリティもありました。なぜなら銀行員であった父親は常日頃から「俺は仕事が嫌いだ。本当はすぐにでも辞めたい」と子供の前でも公言していたからです。朝は母親に起こされながらも布団を引っ被って、
「会社に行きたくないよう」
と、ゴネていました。もちろんそれもまた冗談であり、まあ言うなれば父親の定番ギャグでもあったのですが、その自虐ネタの根底に魂の叫びのような真実が見え隠れしていたことにも僕は気付いていました。仕事が嫌い、ということ自体は、決してまるっきり冗談というわけでもなかったはずです……。
人の親としてはいかがなものかと思いますが、この魂の叫びのおかげで、僕はその20年後、一度就職した立派な会社を辞めて料理人という浮草稼業に身を投じる決心を、案外あっさり固めることができたのです。あの男の轍を踏んではならぬ、後悔のある人生にしてはならぬ、という思いは、その決心を確実に後押ししていたということです。
閑話休題。
父親が(現実逃避のよすがとは言え)絶賛していた母親のうどんつゆは、いりこと昆布が主体のダシに塩、醤油、みりんなどで味付けされていました。当時住んでいた鹿児島ではおおよそ標準的なものだったのではないかと思います。うどんの麺自体はパックに入って売られている「ゆでうどん」でした。当時はその麺に対して特に不満もなかったのですが、今になって思えば、それがおいしい手打ちうどんであったら、(店を出して成功するかどうかはともかく)確かになかなかのものになったことでしょう。
記事が続きます
僕がすっかり大人になった頃、讃岐うどんブームというものが訪れました。その時初めて出会った讃岐風の「生醤油うどん」や「釜玉うどん」は、それまで知らなかった衝撃的な味わいでしたが、「かけうどん」を食べた時は、明確にある種の懐かしさを感じました。讃岐うどんのつゆは基本的にいりこだしであり、その透明感のある見た目やあっさりとした味付けも含めて、それは僕が子供のころ鹿児島で食べていたうどんのつゆにとてもよく似ていたからです。
讃岐うどんがはやったのは、一にも二にもそのうどん自体のしなやかかつ強靭なコシゆえだったのでしょうが、「手打ちうどんを我が家のつゆに入れたらはやる」という父親のかつての読みは、あながち素っ頓狂なものでもなかったのかもしれません。
記事が続きます
日本で最初の讃岐うどんブームが起こったのは1960年代後半とも言われているようですが、実際にそれを実感したのは90年代以降、という人が多いのではないでしょうか。香川県には独特のうどん文化があり、地域に密着した知られざる名店がいたるところにある、という情報が世の中に広まり始めました。そういったお店を県内くまなくルポした『恐るべきさぬきうどん』の出版が1993年です。
畑の真ん中に民家のような製麺所があり、打ちたてのうどんをその場で茹でて食べさせてくれる、そんな牧歌的な光景が、テレビなどでも頻繁に紹介されるようになりました。極めて簡素な店内や半セルフサービスの素朴なシステムは、世の中のグルメ化が進む中でかえって新鮮に見え、どこかホッとするような安らぎを感じさせてくれました。中には「ネギが欲しければ自分で裏の畑からネギを引っこ抜いてきて、それを包丁で刻んでうどんに載せる」という、牧歌的と言うにもほどがあるお店もありました。
そして何より値段が安い。しかも地元の人たちが1日に3回食べることもあるくらい、それはすこぶるおいしいらしい……。
記事が続きます
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)