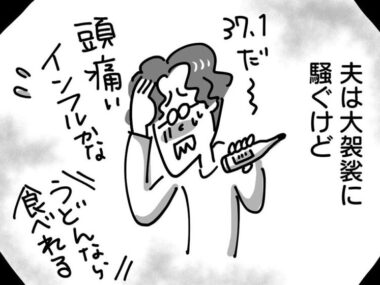2025.10.5
【中村憲剛×村井満対談 後編】「スポーツビジネス」ではなく、「ビジネスがスポーツ」な時代。「指導力」より「始動力」こそが求められている
(取材・構成/二宮寿朗 撮影/熊谷貫)

記事が続きます
「サッカーは習うもの」な時代。想像力が欠如してきているかも
中村
物ごとに主体的に関わっていく“オーナーシップ”が(日本は)足りないという村井さんの見解を、もう少し踏み込んでお伺いしたいと思います。
村井
クラブの育成システムを指標化したというベルギーのベンチャー会社の話を聞いたことがあるんですよ。2014年のブラジルワールドカップ後でしたかね。そこでは400項目5000点満点でクラブの育成組織を採点していくわけ。日本だと多くの場合は、優勝したチームに対して賞金を出す形ですけど、例えばドイツでは将来強くなる先行指標ともいうべき育成組織のレベルが高いチームにリーグがお金を出すそうなんです。その指標をそのまま日本(の育成組織)に対して評価してもらったら、そのなかの1つである、「オーナーシップ」という項目が最も点数が低くてゼロに近かったんです。
中村
どのようにしてオーナーシップを評価していくんですか?
村井
トレーニングのなかで選手から発案した練習メニューが全体の何%だったかを見ていくのです。たとえば次の試合はこういう特徴のある相手だから、「こんな練習もやっていこう」みたいな提案が選手側からあり実践していたか、というものです。でも日本は(指導者の)言うとおりに黙々とメニューをこなしているクラブがほとんどという結果でした。ドイツの子供たちは、「こういうことをやろうよ」と指導者側にアクションを起こしていくことも多いそうで、練習そのものにもオーナーシップを持っているから、試合でもそれが発揮されるのだということでした。
中村
正直、日本人はどうしても受け身になってしまうマインドがあるとは思います。
村井
指導者にも私は原因があると考えています。「期待」という漢字は「期限を区切って待つ」と書くでしょ。でも(日本の指導者は)なかなか待てない。「期待しているよ」って言いながら、すぐに「どうして俺の言ってるとおりにやらないんだ」ってなっちゃう。そうなるとオーナーシップは持たせにくい。
中村
そこは根が深いとは思います。今、サッカーはいろいろな場所で自由にできるわけじゃないので、サッカーを本格的にやろうとする子は、お金を払って練習場所が確保され、コーチもいて用具もそろっている環境でスタートする子が多いと思うんです。だからどこか「サッカーは習うもの」というマインドに子供たちがなっているのかなと。受け身ですね。そういう環境下で練習しているので、言われたとおりにやろうとする意識は高いんですけど、言われたことをやろうとしようとするあまり、想像力は欠如してきているんじゃないかというのが僕の率直な感想です。
村井
本当にそうだと思う。
中村
僕が子どもの頃は校庭を自由に使えて、公園でもボールを蹴って。仕切る大人もいないので、子どもたち同士で勝手にルールを決めて、自由にやっていました。僕も(育成年代の)現場にいますが、小学生に対してなら「みんな好きにやっていいから」と場所だけ提供して、あとは安全安心にできるように見守りながら、うまくいっていないなと感じたらサポートに手を差し伸べる、そのような日があっても良いのかなと思っている自分もいます。今はどちらかと言うと教え込む傾向にあるとは思うんです。ライセンスを取得した身として言えば、いろいろと深いところまで教わるので、どうしても伝えたくなってしまうのは確かなんですよね。そのバランスの難しさはあると思います。

記事が続きます
「憲剛はJリーグの宝」という言葉の裏にあった5つの特性
村井
憲剛が歩んできたプロセスというのはサッカーをやっている子どもたちにとってすごく参考になると思うんですよ。小さいころは体も小さくて、中学時代には一度サッカーから離れているよね。それでも日本代表になって、JリーグMVPも受賞して、日本サッカーを代表する選手になったんだから。そこには成功する人の多くが持っている大切な5つのハードルを越える特性があったと思うんです。
中村
僕が引退した直後に、仰ってくれたことですよね。
村井
1番目は「好奇心」。子どものころから好きな選手の映像を見たり、自由にサッカーを楽しんだり、とにかくサッカーへの興味をどんどん膨らませていく。そして2番目が「持続力」です。一過性の好奇心ではなく、うまくなりたい気持ち、うまくやっていくにはどうしていくかを考える習慣をずっと保っていく。憲剛の場合は引退しても、ずっとサッカーのことを考えているんだから。
中村
まさに。おっしゃるとおりです(笑)。
村井
そして3つ目が「楽観的」。今、このリフティングができなくてもいつかできるようになる、この試合ではダメだったけど次はきっとうまくいく、みたいに楽観的に考えていかないと持続ができない。そこがないとすぐに「もういい!やめた!」ってなっちゃうから。それに近い概念が4つ目の「柔軟性」です。この監督のもとじゃないとダメとか、このやり方じゃダメとか考えを固定してしまうと、(自分に)幅を持たせるのは難しい。憲剛は川崎フロンターレでずっとプレーしてきたわけだけど、どの監督でも重用されました。監督が何を求めているかを感じて、そこに合わせつつ自分の技術をマッチさせていくことが、結局、自分の引き出しを増やすことにつながる。憲剛を見ていて、それは強く思いましたね。
中村
サッカーの場合、試合に出られるか出られないかがはっきりしているじゃないですか。出られないのであれば自分が変わるしかない。結局、監督が変わるか、自分が変わるか、どちらかしかないので。新しい監督が来たとしても、その人と合うかどうかも分からないですしね。だから僕の場合、その監督のOKプレーとNGプレーを練習中から頭のなかでまとめていました。たとえば日本代表時代なら(イビチャ・)オシム監督が「ブラボー!」と言ってくれたら、このプレイはOKなんだと理解しました。「ブラボー!」という言葉が多ければ多いほど、自分が出られる可能性が高まってくる。そうやってアンテナの感度を高くしてやっていました。プロのサッカー選手になると、そこは意固地になって変えない人もいる。柔軟に頭の切り替えをすればいいのになって感じたこともあります。
村井
そして最後の5つ目が「冒険心」。ここは最大のハードルと言えるのかもしれない。(前編で)「シャレン!」のきっかけになった憲剛の「僕らは本気でやっているのに、Jリーグは何をやろうとしているんですか?」という発言を紹介させてもらったでしょ。ああやって勇気を持って、私に言ってくれたのは、社会貢献、地域密着をしっかり広めたいという冒険心があるから。実は今まで言った5つのハードルは、ジョン・D・クランボルツさん(スタンフォード大教授、心理学者)の「計画的偶発性理論」にある行動特性なんです。偶然性をきちんとチャンスにできるその5つを兼ね備えている人だなという目でずっと憲剛のことを見ていました。
中村
振り返ると、今、現場でもその5つの要素を通して選手と接している自分がいます。3つ目の「楽観的」はまさにそうで、選手に対しては「別に今はできてないだけで、この後できるようにすれば良いよ」とよく伝えています。「今できないとダメだ!」と伝える指導者はいるかもしれないですけど、できるようになるために自分で考えてやれるようにする作業こそが大事だと思うので。
村井
楽観的と柔軟性はつながっていますからね。
中村
はい。(育成年代の)選手たちに思うことは、「やるのは君たちだから、こちらの提示ももちろんあるんだけど、それを聞いた上で自分で選択して欲しい」。もちろん僕がジャッジするときもあるんですけど、基本的にはトレーニングのなかで何が良くて何が良くないかを選手たち同士でジャッジし、要求し合える雰囲気を作る集団になって欲しいですし、こちらはその空気感を一緒に作れるようにサポートするのが理想です。だから僕はできるだけベンチに座っていたい派(笑)。村井さんの話を聞いて感じたのは、大切なのは指導者の「冒険心」でもあるんだな、と。
村井
憲剛は自分に照らし合わせることもそうだけど、ちゃんと選手目線に合わせているのが伝わってきます。どう「好奇心」と「持続性」を持たせ、どう「楽観的」、「柔軟性」に考えさせ、そしてどう「冒険心」をくすぐっていくか、を。私は人事の立場で5つの要素を見ていたけど、サッカーに来て中村憲剛と出会って、(大事なのは)サッカーでも同じなんだという発見があった。それは日本サッカー界にとって財産だと思ったから、「憲剛はJリーグの宝だ」とまで言ったんですよ。
中村
ありがとうございます。選手たちには、自分は君たちの目の前でいま指導者としているけど、君たちからすれば長い選手生活のなかで通り過ぎていく存在に過ぎないので、こちらの言ったことは全部聞いてもらわなくていいし、何か心に残ったものだけ持って次のステップに進んでもらいたいと思って接しています。僕から見ても、この5つの要素は村井さんも大事にされていますよね?
村井
一番強いのは「好奇心」かな。
中村
それは当時から感じていました。Jリーグのチェアマン就任もそうですし、就任されてからの言動もそう。そして、いまは日本バドミントン協会の会長職をやってくださいと頼まれたら引き受けちゃうわけですから。
記事が続きます
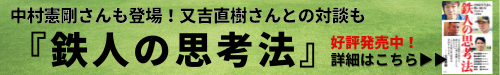
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)