2025.4.29
【中村憲剛×一力遼対談 後編】27歳の囲碁世界王者が目指す未来。「まだ韓国、中国とは差があるので、そこを詰めていきたい」
(取材・構成/二宮寿朗 撮影/熊谷貫)

記事が続きます
生活リズムを一定にしておけば大舞台でも普段と同じメンタルで臨める
中村
一力さんはなにかルーティンを取り入れていますか?
一力
はい。朝食前に囲碁の勉強を30分くらいやることや、就寝前にはストレッチをやることなど、ここ2年くらい結構いろいろと、やっています。
中村
毎日ストレッチをやっているんですね。意外!
一力
試合になると2日間で16時間以上も座っているわけなので、体にかなりの負担が掛かりますから。YouTubeで5、6分のストレッチ動画があるのでそれを観ながら。一時期はピラティスもやっていましたよ。
中村
ピラティスいいですよね。僕も以前、本格的ではないですけど、(体の)コア部分を意識できると思ってやっていました。
一力
朝食後にはラジオ体操もやっています。結構、体は柔らかいほうかな、と。(肩甲骨に両手を回してつなげるストレッチを実演)
中村
めちゃ柔らかい!
一力
メンタルトレーナーの方から体操やテニスの選手はこんなことをやっているとか教わるので、そのルーティンを1週間ほどは、とりあえずやってみています。自分に合わないと思ったらやめる感じですけど。
中村
僕は若いときにルーティンをつくりすぎて、ちょっと痛い目に遭ったことがあるんです。環境や状況が変わると、できないときってあるじゃないですか。それで、調子を崩してしまった経験があって。だから、最低限これだけはというものだけ残したパターンですね。
一力
残していったものにはどんなものが?
中村
食事だと、試合の日に何を食べるかを決めていました。でもほかの選手はその日の気分で食べていたりしているし、本当に人それぞれ。だから、いろいろ経験しながら自分なりの形をつくっていくのがベストなんだなって最終的には思いました。
一力
私も以前はタイトル戦の昼休憩などは食べたいものを口にしていたのですが、最近はいつもそばとか消化のいいものを食べるようにしています。
中村
僕の場合、いつもどおりのものを食べているっていう感覚が、安定したパフォーマンスにつながると思って気持ちが落ち着いたんですよね。
一力
ルーティンもそうなのですが、メンタルトレーニングを始めてから周りに流されなくなりました。というよりも周りがあまり気にならなくなりました。普段から生活リズムを一定にしておくことで、大きな舞台であっても普段と同じメンタルで臨めるというのが目指す姿ではあるので。
中村
その「同じメンタルで臨んだ大きな舞台」が昨年、優勝された国際戦、第10回「応氏杯」だったと思うんです。日本を拠点にする棋士の優勝は19年ぶりだったそうですね。
一力
1990年ごろまでは日本が一番強い国でした。1989年から始まった「応氏杯」をはじめ、そのあたりからいろんな世界大会ができて、中国や韓国が国を挙げて力を入れてくるようになったんです。1990年代後半からは中国と韓国が覇権を争い、台湾も力をつけてきていて、いま日本は三番手を争うところまで相対的に落ちてしまいました。
中村
一力さんは1997年生まれですから、囲碁を始めたころはだいぶ引き離されていたんですね。
一力
11歳のときに「応氏杯」のユース大会があって決勝で敗れたのが中国の柯潔(か・けつ)さん。今回は準決勝で同じ年の柯潔さんに勝って16年前の借りをやっと返すことができました。一昨年のアジア大会でも個人戦で負けていましたし。
彼は10代後半で世界チャンピオンになってから中国のランキング1位を長らくキープして、(国際戦を)何度も優勝している、ずっと意識する存在でした。自分の同じくらいの世代が韓国、中国とも非常に層が厚いんです。そういった環境のなかお互いに切磋琢磨できているので、時代にも恵まれているのかなって。
中村
僕は今、指導者をやっていますが、選手が成長するうえで競争は一番大きな養分だなという確信があります。自分のポジションが安泰な選手ほど、もう一つ伸びていかない。ただそこに強力なライバルがいると、勝手に引き上げ合っていくような関係性になっていくんですよね。一力さんも柯潔さんを意識することで、自然と目線が上がっていったんじゃないかなって思います。ずっと意識してきた人に勝ったときってどんな心情でした?
一力
たまらなくうれしかったです。3番勝負のうち1局目を落として、2局目を逆転勝ちして3局目も勝ってという形でした。自分自身が変われたと思う瞬間、新たに視界が開けたと思う瞬間でもありました。
中村
僕は世界を獲った経験がないから、一力さんが見た景色はわからない。ただ長年勝ちたかった相手に勝つことで、成功体験と自信が手に入るという経験はわかります。
一力
応氏杯では優勝できましたが、ほかの世界大会では目立った成績を残せていません。今、世界で最も強いのは韓国の25歳の申眞諝(シン・ジンソ)棋士で、頭一つ抜けています。少しでも彼に近づいていけたらと思っています。
中村
優勝して一段と目線が上がっているように感じます。

記事が続きます
トップが基準と目線を上げることで次世代の意識が変わる
一力
それこそ憲剛さんに伺いたいのは、川崎フロンターレが勝ちまくって優勝した時期、ほかのクラブだって“打倒フロンターレ”でやってきたと思うんです。そういった中で王者の立ち居振る舞い、戦略みたいなところで大変だったことってあるんですか?
中村
2017年に初めてJリーグのタイトルを獲ったときに、これまでうまくいかなかった歴史やその1年間の努力もひっくるめて、すべてが良かったんだなと思えたことが本当に大きかったです。だから次の年、「この努力よりも上に行けば自ずと連覇できるだろう」という基準が初めてクラブのなかにできました。一人もひとりとしても、チームとしても、その基準を超えることができればほかのチームは届かない、と。
基準から下がった選手は試合に出られないし、基準を超えようとしない選手は浮いてくる。チームがそういう空気になればトレーニングの質も、その基準も上がっていくんですよね。つまり、僕らを倒そうとする相手に対してではなく、自分たちがどう振る舞うかのほうにフォーカスしました。
一力
うまくいかなかった歴史も含めて、と言いますと?
中村
優勝したときに分かるんです。「勝てないときは隙があったな」とか、「ここが水漏れしていたな」とか、ちょっと足りなかったところが。だから今、若い選手や子供たちに言うんですけど、普段のトレーニングでどれだけ突き詰められるかが一番大事だ、と。トレーニングで100%出せない選手が試合で100%は出ませんから。練習をなあなあにしてしまうと、絶対に試合には勝てない。フロンターレが常に勝っていた時期は、隙のない厳しさみたいな雰囲気がありました。
一力
サッカー日本代表も、1998年のフランスワールドカップに初めて出場してから世界を意識して、ベスト16に何回も進んでと成功体験を積み重ねていくことで今の姿があるのかなという印象はあります。
中村
僕が少年のころは、まだ「ワールドカップは観るもの」という感覚でした。まさかその後、自分が南アフリカ大会で出場できるとは思ってもみなかったですけど、僕らの下の世代は、
「ワールドカップは出るものだ」という感覚です。カタールワールドカップではベスト16で負けましたが、森保一監督はじめ、いまはみんなが「ワールドカップで優勝」という目標を口にしています。だから、今の子供たちは、多分もっと上の目線になっているんじゃないでしょうか。
一力
囲碁もそうなっていきたいです。
中村
一力さんが基準と目線を上げることで、これからの若い棋士や子供たちが、日本は韓国や中国に勝てるんだという意識になればいいですよね。先を歩いていくのは本当に大変だと思うんです。日本を背負う、それも個人競技ですから一人で背負う。そのプレッシャーというのは想像もつかないです。でも一人のファンとして、一力さんには期待してしまうし、どんな時代でも、どんな分野でも、こうやって切り拓いていこうとする人がいるんだなと改めて思います。
一力
憲剛さんに言っていただいたことは自分の理想でもあるんです。日本では囲碁の競技人口が減っていますし、まずは関心を持ってもらいたい。自分が活躍して引っ張ることでどんどん若い棋士にも出てきてもらいたい。女流では上野姉妹が世界一になりましたし、空気は少しずつ変わりつつあります。ただ現状はまだ韓国、中国とは差があるので、そこをどう詰めていけるか。この先数年が大切になってきます。
中村
優勝することで自分もそうですが、取り巻く環境面でも変わることがあると思うのですが。
一力
中国で開催された応氏杯では、中国語を話せる棋士にサポートしてもらってとても助かりました。サッカーなど他の競技では当たり前に行なわれていることが囲碁ではそうじゃなかったりするので、ナショナルチームの活動において、良いと思ったことはいろいろと提言していくつもりです。
中村
サッカー、囲碁にかかわらず良いパフォーマンスを発揮するには、周囲のサポートが必要。結果を残せば、それが良かったとなりますからね。上の世代で当たり前になれば、育成世代でもそのようになってくるのではないでしょうか。
一力
2年前、中国・杭州でのアジア大会で、韓国チームのサポートが手厚くて、それを参考にしたいなって。そういうサポートもあって応氏杯を勝ったことで、次の世代ではそれが常識になってくれればうれしいですね。
記事が続きます
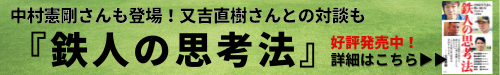
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)















