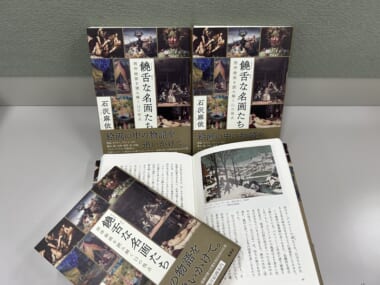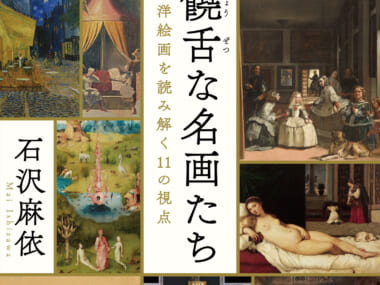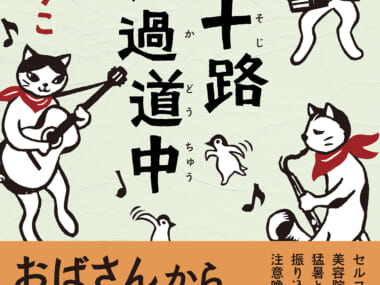2025.8.25
出世なんてしたくなかった!?【第4回 女性管理職を待ち受ける修羅】
役員になってから、孤独感は深まるばかり
やがてジェンダー平等の考え方が世界的に広まると、管理職や役員に女性を登用する動きが強まってきました。日本はその点においてもだいぶ後れをとっていますが、それでも政府は、二〇三〇年までに企業の女性役員を三十パーセントに、という目標を掲げています。経団連等の経済団体も、女性役員を増やすように働きかけることとなりました。
実際、役員が男性ばかりの企業は、旧態依然とした体質だと見られるようになっています。とはいえ役員候補として女性をきちんと育ててきた企業など、日本にはそうありません。女性役員比率を上げるべく、社外取締役などに女性を採用しよう、ということで女性人材の取り合いに……といった事態にもなっている模様。
そんな状態における、
「男性役員は全員、女のことが嫌い」
という発言は、私の中で重く響いたことでした。彼女の会社において、プロパーの女性役員は彼女のみ。役員会などにおいても、
「スーツ姿のおじさん達の中に女はごく僅かで、居心地が悪いといったらない。男女比が逆だったらどう思うのか、考えてみてほしい」
と言います。
様々な委員会等でも、かつてはメンバーが男性だけのことがよくありましたが、今は女性メンバーを入れるのが当たり前。それも、少し前までは「女を一人、入れておけばいいか」という感じだったのが、次第に一人だけではお茶を濁せないようになってきました。
しかし、いずれにしても女性メンバーは「少々」であり、「少々」の側のことに思いが及ばない男性も多いのでした。
件の女性役員は、
「女だから私を役員にしただけで、私だからというわけではない、という感じも伝わってくるのよね」
と言います。本当は男だけで役員を固めたいが、時節柄そうもいかないので仕方なく女も入れたのだろう、と。
企業の女性役員の多くは、その企業の中枢をなす部門の担当でなく、傍流部門の担当があてがわれがちです。重要な部署を任せられる人材が育っていないから、と男性達は言いますが、業種や会社によっては育てる気持ちがあるのかと疑問に思うケースも。
「うわべでは同じように扱われていても、本当は男性達から軽んじられているし、敬遠されているのがよくわかる。役員になってから、孤独感は深まるばかり」
と、彼女は言うのでした。
記事が続きます
男性社会が醸成した空気を無視する力が必要な時もある
別の企業で役員を務める女性と話した時も、職場において孤立感を覚えている様子が伝わってきました。それというのも彼女は、非常に真面目な性格。企業経営の場においても、間違っていることについてはきちんと異議を唱え、なあなあでは終わらせません。
それが男性達にとっては、非常に面倒くさいようです。
「空気読めよな」
ということになり、彼女はいつも孤立しがちなのだそう。
男性の身になったら、彼女のような存在は確かにウザいことでしょう。今まで、男性という仲間同士でずっとやってきた彼等。それがダイバーシティだなんだという世の変化によって「女を入れなくては」となり、無理矢理のように入れた女性が、男の感覚では絶対に言わないようなことを急に言い出すのですから。が、そのような〝空気読まない力″も、実は大切ではないかと私は思う。
場を支配する〝空気″に流された結果、企業が不祥事やスキャンダルに巻き込まれた事例は多々あります。男性社会が醸成した空気を無視する力が必要な時もあるわけですが、しかしそんな力を発揮し続ける彼女が男性役員達との戦いに疲弊してしまわないかは、心配でもある。
出世をした女性達は、このように孤独な戦いを続けているのでしすが、しかし孤独感を抱いているのは、組織のトップ層にいる女性ばかりではないようです。出世した女性達は、道を拓く人として、一種の覚悟と共に孤独な歩みを続けているのですが、その後に続いているはずの女性達もまた、孤独を感じている模様。
役員までではなくとも、今は出世する女性も増えています。かつての日本企業では、女性はどれほど勤続年数が長くても、ずっと末端の仕事しか担うことができず、年下の男性上司に仕えるしかありませんでした。しかし今は、女性の昇進も珍しいことではなくなってきたのです。
しかしそのような状況が、彼女達に悩みをもたらしてもいるようです。会社勤めの知り合いの中にも部下を持つ立場となった女性が多くなってきましたが、彼女達と話していると、上に立つ身であるが故のため息が、しばしば漏れてくる。
そもそもは男性ばかりだった「上司」の地位に女性が就くと、そこにはねじれが生じます。日本はかつて、男が上で女が下という男尊女卑システムで延々と回っていましたから、戦争に負けたからといってすぐに男女が平等になるはずもない。戦後八十年が経ってもなお、男が上で女が下という感覚は、少しずつ修正されつつも継承され、今に至るのです。
女の上司に男の部下という状況は…
だからこそ女の上司に男の部下という状況は、両者に緊張をもたらすのでした。
本来であれば「下」のはずの女に「上」に立たれたけれど、自分は現代的な人間なので女上司だからといって舐めたりはしない、と心に誓う男部下。「女の上司だから感情的」とか「論理立てて話ができない」なんてことも、たとえ思ったとしても口には出さない、と殊勝な心構えです。
女上司の側は、皆が昇進して喜んでいるわけではありません。面倒臭いところは男性に任せておきたかったのにな、という感覚の〝男尊女子″が管理職になると、部下をどう管理していいものやらと、しばし惑うことに。
もちろん管理にアグレッシブな女上司もいます。部下の仕事の出来が今ひとつだと、「男のクセにこんなこともできないのか」とか「……ったく今時の若者は文句が多くて扱いづらい」などと一瞬思うのだけれど、それを表に出してしまってはセクハラにしてパワハラそしてエイジズムになってしまうで、ぐっと呑み込む。
そして初めて管理職に就いた女上司は、上司という立場になったが故の孤独を感じるのでした。部下という自由な立場にいた時代は、同僚と上司の悪口を言い合うことがストレス発散になったけれど、自分が上司になると、部下の悪口を言う場は無い。部下は自分が育てるべき人材なのであり、部下の落ち度は自分の落ち度でもあるのですから。
仕事の愚痴も、軽々に口にすることはできません。それは部下にも上司にも言うことができない話だし、かといって仕事内容をよく知らない人に語っても、隔靴掻痒の感あり……。
その辺りは性別に関係なく、管理職初心者に共通する悩みなのでしょう。が、女性ならではの孤独感もあるようで、それは自身の大変さを誰にもわかってもらえないというところ。
女性管理職が増えてきたとはいえ、それはまだまだ少数派です。業種や立場、既婚か独身か、子供の有無などによってそれぞれが抱える大変さは全く異なるわけで、女性の管理職同士で話したからといって、必ずしもスッキリするわけではありません。
女性は「共感」の生き物だ、という話があります。確かに我々は女性同士で、
「そうだよねー」
「わかるー」
などと言い合うことによって仲間を作ったり安心したりすることができるのですが、女性管理職の場合は、なかなかそのような共感の場を見つけることができないのです。
かつての男上司であれば、
「おぅ、ちょっと飲みに行くか」
と同僚や部下と会社帰りに居酒屋へ行き、お酒の力を借りて本音を言ったり聞いたりしていたのでしょう。しかし女性管理職の現場では、その手の行為は激減しました。
「私に飲みに誘われても、部下は嬉しくないだろうし、こちらも家庭があるので早く帰りたい」
と、女上司。そして、
「上司との飲み? ありえない」
と、上司が女だろうと男だろうと飲みには行かない若い部下。両者はまさに、ビジネスライクな関係に終始するのでした。
しかしこれからはそのような関係が、組織におけるスタンダードな形になっていくのでしょう。かつては組織にも家父長制が浸透し、管理職は父親のような存在感を醸し出していましたが、女性管理職はお母さんではないし、バーのママ的にもならない。飲酒による本音吐露に頼らない組織運営が、当たり前のものになっていくのです。
女性が組織の「上」になることには、まだまだ慣れていないこの国。だからこそ管理職や役員に就いた女性達は強い孤独を感じているのですが、しかしそもそも、どんなに小さな組織であっても、その頂点は孤独な立場。女性管理職が孤独に慣れ、その解消法を編み出すようになる頃、この国の組織の形は、少し変わってくるのかもしれません。
^^^^^^^^^^^^^^^^
*次回は9月22日(月)公開予定です。

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)