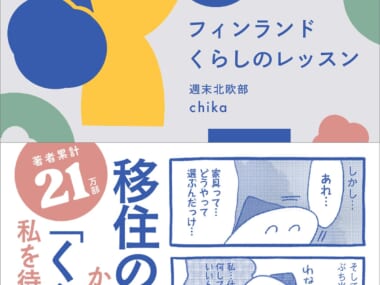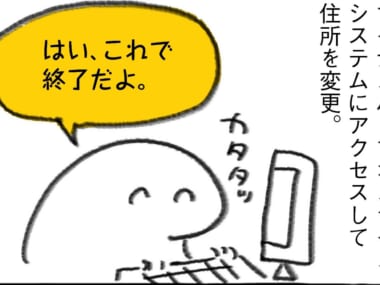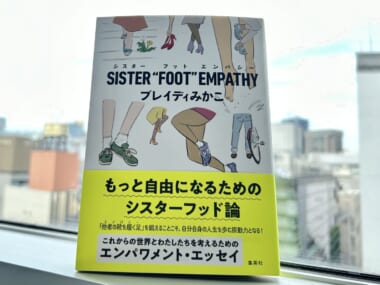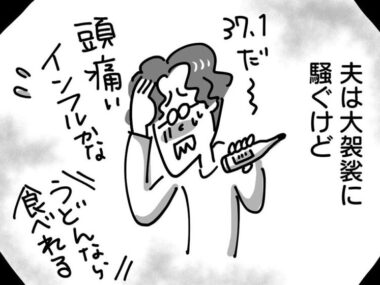2025.11.11
学びたいと思えば、誰でも学べるということが「フィンランドの精神」(第1回 後編)
それは、大人より子どもについてより感じることでもある。私が会社の休職制度を使って、渋る2人の子どもと初めてフィンランドに来たとき、「モイ」(こんにちは)と「キートス」(ありがとう)しか知らなかった。当時小学校4年生だった上の子は、近くの公立小学校に入れてもらえたが、それは他の外国人の子どもたちと一緒に、学科の授業ではなくフィンランド語だけを学ぶクラスだった。
最初は「フィンランドにいるのは1年間だけだし、人口560万人(兵庫県か福岡県、または北海道一つぐらいの人口)のフィンランド語を習って、将来何の役に立つんだろう……どうせなら英語を先に勉強した方がいいのでは」という思いがかすめたが、約20人のクラスに対して教員が2人、補助の先生が1人という手厚さで、外国から来た子どもたちにフィンランド語を一から教えてくれていることを知り、ありがたさが爆発した。すべての小学校にフィンランド語の集中クラスがあるわけではなく、少し離れた学区から通ってきている子どもたちもいた。そんな子たちには、バスチケットがもらえる。
おかげで、子どもはソマリアやシリア、イラン、ネパールなど、難民や移民の家族など多様な背景を持つ子どもたちと机を並べ、私はその家族たちにさまざまに助けられた。フィンランドに来て学校に入る時期は1年を通してバラバラなので、毎月のように新しい子どもたちが入り、1年経った子どもたちはそれぞれの家に近いフィンランドの小学校の普通クラスに巣立っていくのだった。
どの国出身の子どもたちも、つたないのかもしれないが、フィンランド語で楽しそうに話せている姿を見ると、尊くてありがたい気持ちになり、そしてそのたびにいつも、日本で日本語を学ぶことができていない海外ルーツの子どもたちのことを思って申し訳なくて胸が痛んだ。
というのは、日本にいる日本語指導が必要な児童生徒のうち、1万人以上の子どもたちが指導が受けられず、日本語が分からないまま教室にいるだけという話を聞いていたからだ。「日本人でなければ義務ではありませんから、学校に通いたければ日本語ができるようになってから来てください、お子さんが大変でしょうから」と、受け入れをやんわりと事実上拒否されることもあるとも聞いた。私も取材して、「コロナで休校になったことが分からずに登校してしまった」外国人の子どものことを記事に書いたこともある。
そのときは、あんなにニュースでもコロナのことをやっていたのに、休校が分からなくて登校させてしまうことなんて本当にあるんだと驚いた。それから約1年後、私もヘルシンキで子どもの保育園が翌日からコロナ休園になるというお知らせや会話が分からなかった。下の子を連れて登園してしまい、ガランとした保育園の付近をうろうろと歩き回った。言葉が分からなければ簡単に孤立する。みじめな気持ちになった。
もし自分が日本語も日本のことも分からず、でも学齢期の子どもを学校で学ばせたい、友だちも作って少しでも楽しく過ごしてほしいと思って相談した先で、「日本語ができてから通わせてください」「学校だけでは全部見きれないので、家でも勉強を手伝ってあげてください」と言われたら絶望しかない。自分が言葉の分からない外国で子どもを学校に通わせて、はっきり分かった。
ヘルシンキの小学校の初日、担任の先生とあいさつしたときに、
「すみません、私はフィンランド語がまったく分からなくて教えられないし、ほかに家族も友だちもいなくて、宿題なども家で手伝えないのですが、大丈夫でしょうか」
と言うと、
「ええ? いえいえお母さん!(今考えると「お母さん!」とは言っていなかったと思うが、脳内訳はそんな感じ)フィンランド語は学校で、わたしたち教師が教えますから、何にも心配しないでください。ご自宅では、母語がなくならないように日本語で話してくださいね!」
と笑顔で言われたほどなのだ。
私は、日本でコロナ休校の間、孤立して日本語が抜けてしまったという外国ルーツの子どもたちの話も聞いていた。おそるおそる、
「次にコロナでまた一斉休校などがあったら、クラスはどうなりますか」
と尋ねると、先生は、
「コロナなどで学校全体が休校することになっても、外国の子どもたちがフィンランド語を学ぶクラスは最後まで開けています。フィンランド語を学んでいる彼らにとっては、毎日学ぶこと、それもオンラインでなく教室に来ることが大切ですから」
とも言ってくれ、私はそこまでしてくれるのかと、安心して力が抜けた。
子どもが言葉を学ばせてもらったパワーを感じるたびに、日本のどこかでいまも孤立している子どもたちがいるのに、自分は彼らの学びを守るために何かできなかっただろうかという苦みがよぎる(もちろん、何かするのにまだ遅くないと思っています)。
記事が続きます
私は50歳のとき、26年働いた新聞社を辞めた。51歳で2度目のヘルシンキに来て、客員研究員として滞在する機会を得た。そのとき、私も今度はフィンランド語を学びたいと思った。たいていのフィンランド人は英語の使い手だ。けれどもフィンランド語は、子どもたちの友だちや、フィンランドに住んだり働いたりしている外国出身者と出会って話すときの唯一の共通語になることがある。フィンランド語ができれば彼らとコミュニケーションをとり、もっと社会を知ることができる(また、人手不足が叫ばれていた数年前と違い、今は簡単な仕事を探すにも、フィンランド語能力が求められることが増えていると、あとで知ることになる)。
だからいま、私もこのヘルシンキ労働者学校のフィンランド語クラスで学んでいる。それがまさか、年齢も背景も多様なクラスメイトたちと机を並べ、励まし合い、彼らの人生に惹きつけられることになるとは、思ってもいなかった。私にとってヘルシンキの街の魅力は、サウナも森もカフェもいいが、さまざまな理由でここにやってきた移民や外国人たちとそれを受け止める社会にある。
100年間の歴史が息づくこの学校で私が出会ったたくさんの彼ら・彼女らは、移民としてフィンランドに住み続ける人もいれば、母国に戻ったり、また別の国に移って行った人もいる。けれども誰にも共通しているのは、自分が住み慣れた環境から出ると決め、自分で変化を起こして動いてきたということだ。私は知りたかった。みんなはどうやって自分の人生のハンドルを握り、その変化を受け入れようと決断したのかを。怖くなかったのだろうか。
私は彼らの話をひたすら聞いた。そして、自らを奮い立たせ、明るいほうを見て生きていこうとする姿勢に勇気をもらった。それは、私がまだ日本にいたとき、新聞記者として取材してきた人たちの顔と重なる。当時と同じように、彼らは私の背中をそっと押してくれた。身寄りのないヘルシンキで、どれだけ救われたかしれない。これからこの連載では、同じ時代に、ヘルシンキで生きている人たちの物語を紹介していきたい。そのどれかに、あなたの力を思い出させ、変化を恐れないよう勇気づけてくれる言葉との出会いがあることを願う。
(連載の文中の肩書や組織、値段や為替レートなどはそれぞれ2025年の取材時点のものです)
第2回前編は11/25(火)公開予定です。
記事が続きます
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)