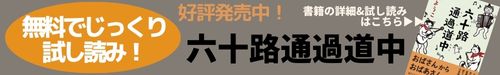
2024.12.11
ほのぼのとしたお店に出会いたい
当記事は公開終了しました。
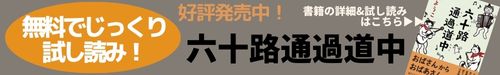
2024.12.11
当記事は公開終了しました。

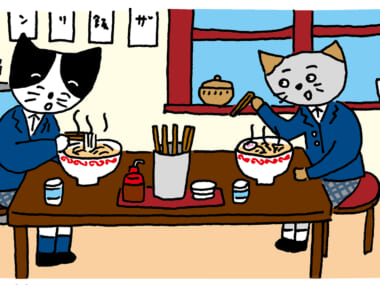
ちゃぶ台ぐるぐる


ちゃぶ台ぐるぐる
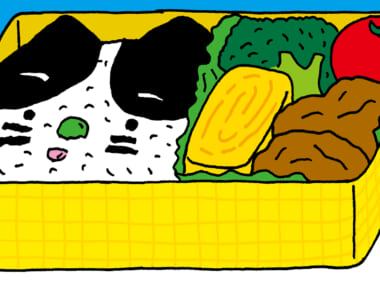
ちゃぶ台ぐるぐる


2026/2/26
NEW

2026/1/26

2025/11/26

2025/10/24

~40代、そろそろ誰かと暮らしたい~ 超実践! アラフォー婚活のかなえ方

植木和実「ゆっくり学ぶ子のための、小学校6年間の勉強を1年で習得する方法 」

目指すは山頂よりも、おもしろい寄り道 山岳ライター高橋庄太郎の山の名&珍プレイス

鈴木大介 「推し無き者」の憂鬱