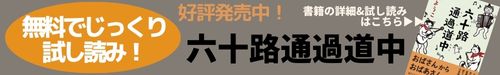
2025.8.13
母の無水鍋
当記事は公開終了しました。
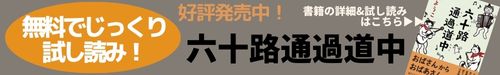
2025.8.13
当記事は公開終了しました。
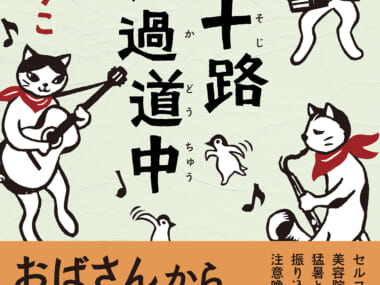
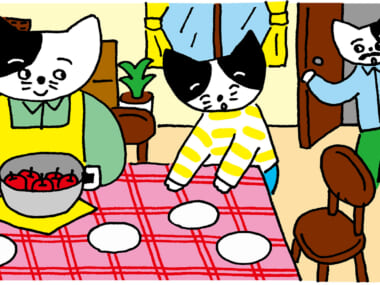
ちゃぶ台ぐるぐる

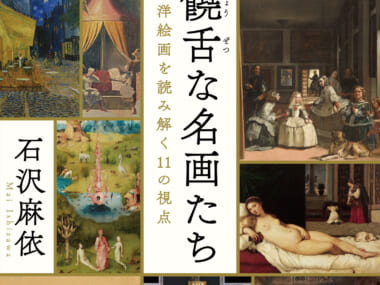

ちゃぶ台ぐるぐる

体重減・筋肉増のおばあさんになる!「あすけん」式 人生最後のダイエット

2026/2/26
NEW

2026/1/26
NEW

2025/11/26

2025/10/24


ケアとアートのダンス ~アクセシビリティのためのプロジェクト・レポート~

平成しくじり男

サーフィン犬 コーダが教えてくれたこと