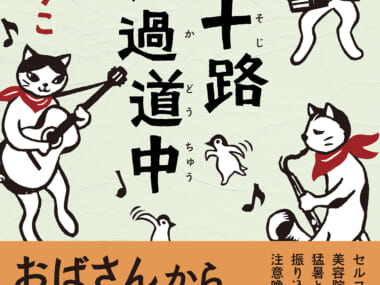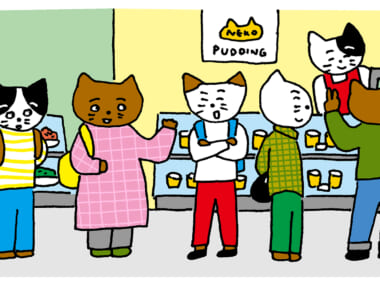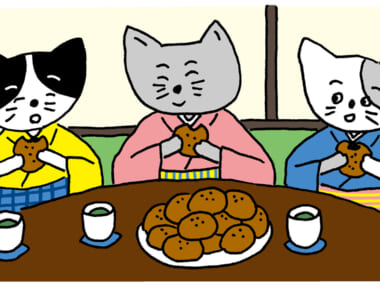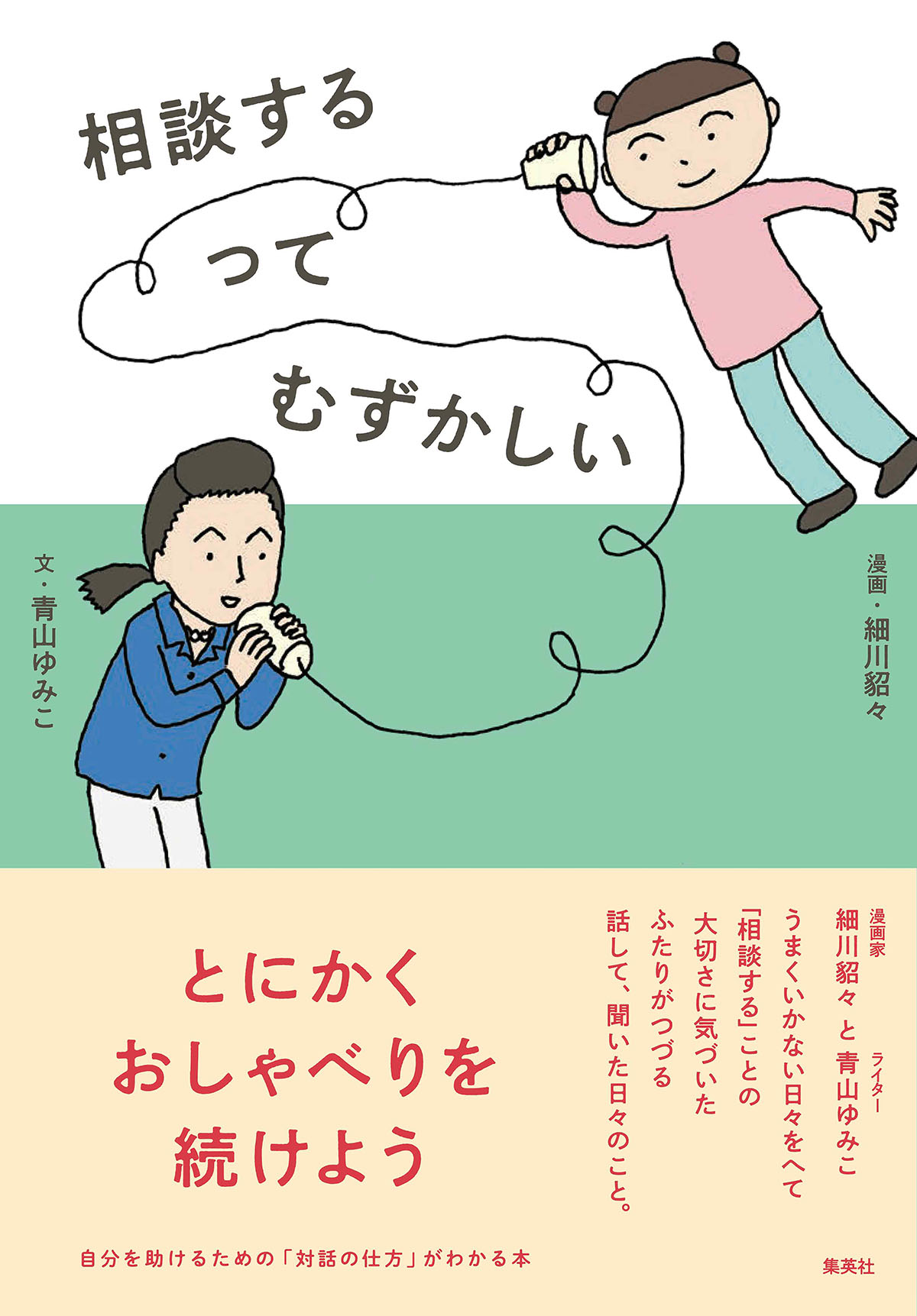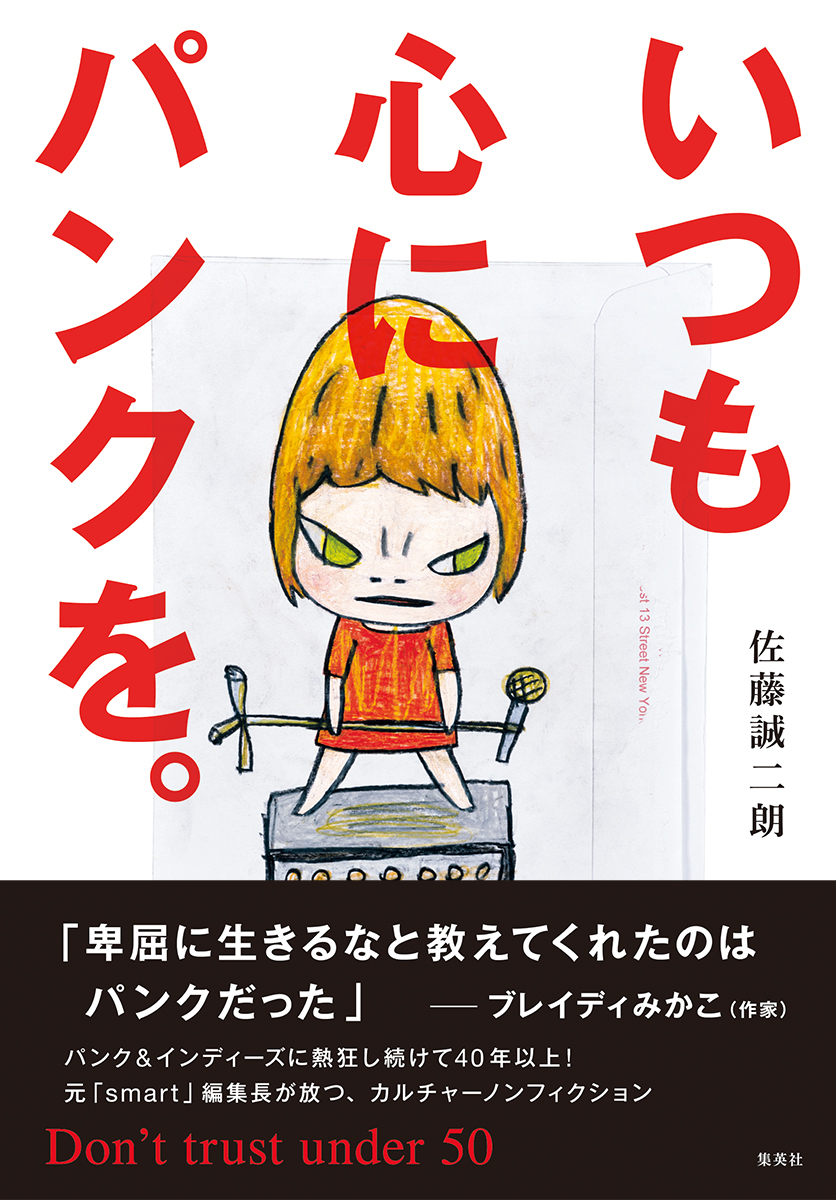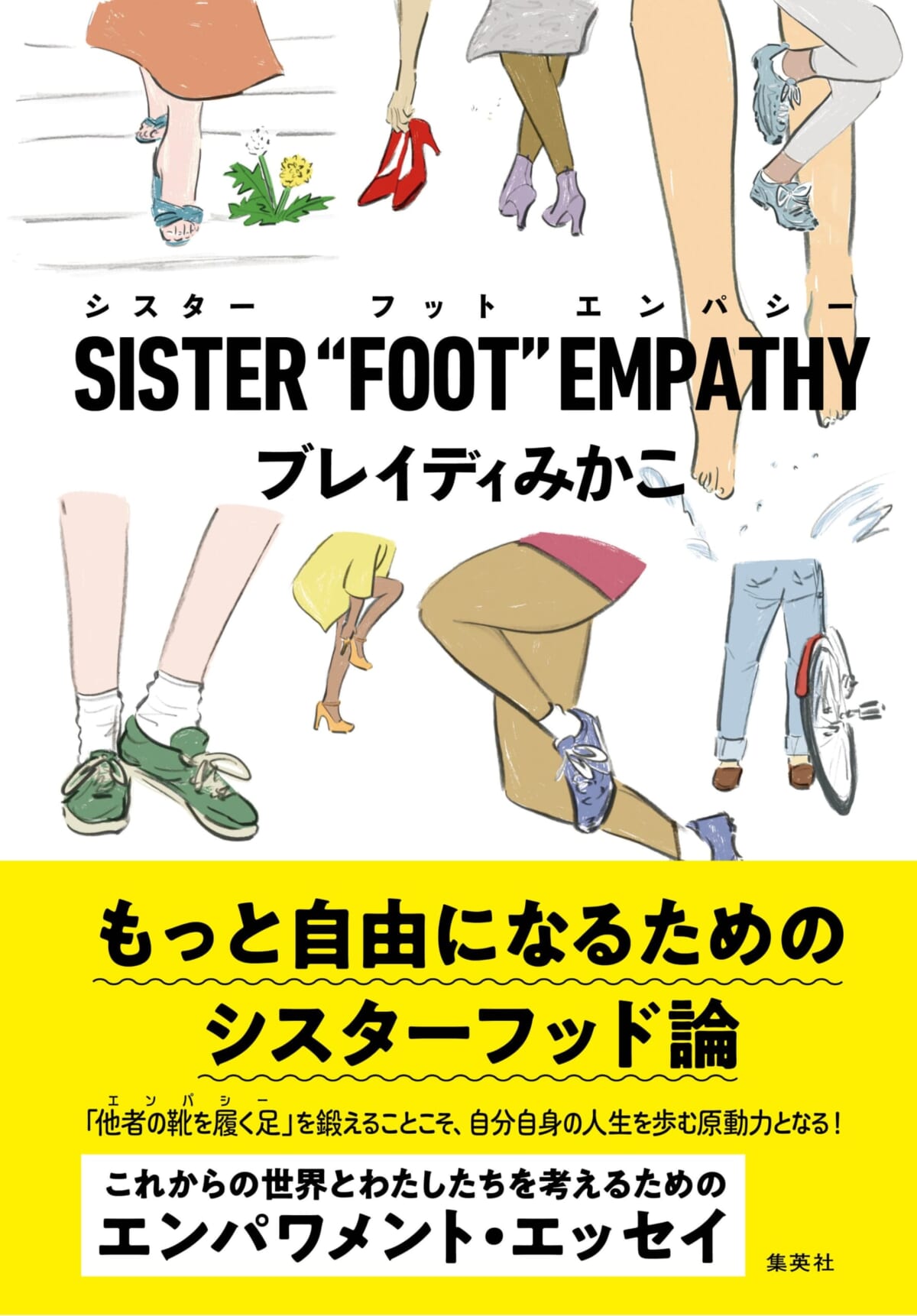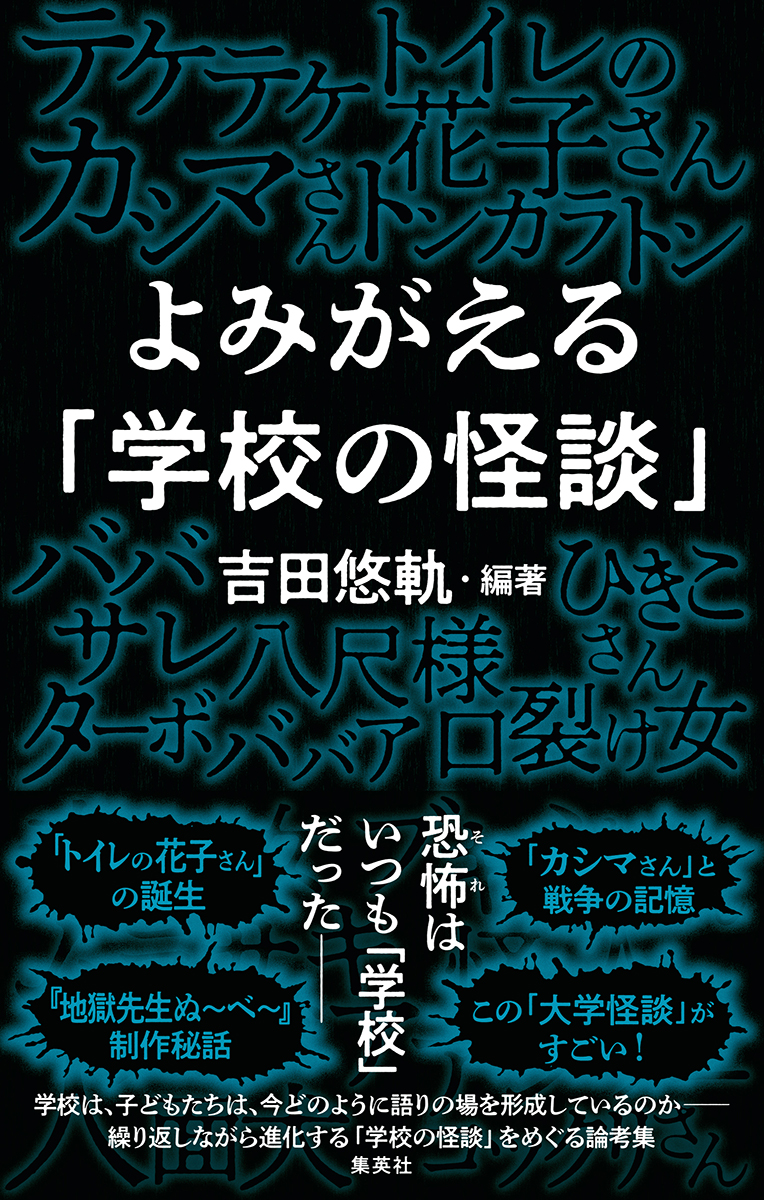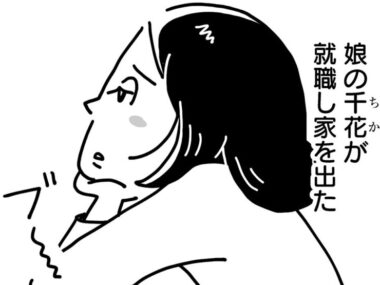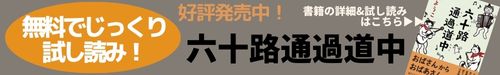
2024.6.12
お弁当箱の蓋を開ける瞬間
記事が続きます
何年か前にキャラ弁がはやりだした頃、さまざまなお弁当の画像を見た。それがまたどれもすばらしいテクニックで、
「食べ物でこんなことができるの?」
といいたくなるくらいのすごさだった。色の変化をつけるのにも、食材を薄切りにしたり染めたりと、考えぬかれていた。海苔や芽ネギの先を鋏で切って使うなど、本当に細かい作業だった。
そんな職人技が紹介されているテレビ番組を、驚きつつ眺めていたのだが、その後、新型コロナウイルスの感染拡大もあって、作る人が手袋をするようになった。世の中の事情も理解するけれど、調理をする人が手袋をしているのを見るのは、私自身はまだ慣れない。
手袋をはめたとしても、キャラ弁のクオリティは変わらないので、蓋を開けたときの驚きを想像すると、食べるのがもったいなくなる。しかしそんなものすごいクオリティの友だちのキャラ弁を見た子どもが、
「自分にも作って欲しい」
とねだって、親が困り果てているという話も聞いた。キャラ弁に比べると、普通のお弁当は見劣りするので、自分も同じようなものを持っていきたいというわけである。
あれは特殊な才能がある人が作れるもので、誰でも作れるわけではない。展覧会に入選した上手な絵を見て、
「あれと同じものを描いて」
といわれても、ほとんどの人が描けないのと同じである。作れなかったとしても、何の問題もない。キャラ弁でなくても、自分のために作ってくれることがありがたいではないか。とキャラ弁をねだる子にはいいたくなったが、弁当箱の蓋を開けたら、みんなに、
「わあ、すごい」
といわれたくなったのだろう。作ってあげたくても作れない親は辛いはずと同情したくなった。
先日、待ち合わせの時間まで少し余裕があったので、出先で目についた雑貨店に入ってみた。カットソー、エプロン、文房具、化粧品、台所用品などが置いてあり、店内を巡っていたら、隅の壁のところに、フックにかけられた黒いものがたくさんぶら下がっていた。いったい何かと近づいてみたら、それは海苔を様々な形に型抜きしてある商品だった。それをお弁当に使えば、精巧なキャラ弁まではいかないまでも、お弁当に変化はつけられる。
「へええ、こんなものまであるのか」
と驚きながら見ていくと、ウルトラマン、恐竜、乗り物、パンダ、にゃんこ、動物園、合格、必勝、開運という文字。六角形がつながり、丸いおにぎりに巻くと、サッカーボールができあがるというものまであった。
「はああ」
至れり尽くせりである。しかし、テレビで観たキャラ弁のほうが、親の職人技がすごかった。型抜きと職人技を比べたら、同じものを作ってもその差は歴然だ。それでもこういったものがお弁当に使われていると、子どもはうれしいのかもしれない。
前日の夫婦喧嘩の復讐なのか、夫が会社で弁当箱の蓋を開けたら、白御飯の上一面に大きく、「バカやろう‼」と海苔で描いてあったという話も聞いた。白御飯を敷き詰めた上に、「KILL YOU」とケチャップで書いてあったといった人もいた。両方ともおかずはなかった。バカやろう弁当でも、KILL YOU弁当でも、作ってくれる人がいるのは幸せだ。お弁当は幸せを与えてくれる、料理のプレゼントなのである。
記事が続きます
次回は7月10日(水)公開予定です。
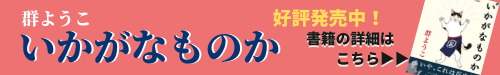
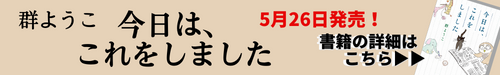
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)