2025.9.19
「モヤモヤ」するだけじゃなくて、日本の女性はもっと怒っていいし適当になってもいい。【ブレイディみかこさん×宇垣美里さん『SISTER“FOOT”EMPATHY』刊行記念対談/後編】
50年後の世代のために、私たちはもっと適当になっていい
ブレイディ メディアの世界にいる女性がそういう修羅場をくぐらなくていい社会にしたいですよね。
宇垣 本当に。表に出る仕事ということもあるかもしれませんが、私はやっぱりこの仕事をする中で繊細さとかビビッドに反応する感覚は確実に失われたと思います。それはたぶん、棘だらけの場所を走り回ったせいで、足の裏がすごく硬くなったんですよね。だって、強くならざるを得なかったから。それがいいかどうかわからないけれど、自分が繊細じゃなくなったことは絶対に忘れないようにしなきゃと思っています。そうしないと、「なんでそのぐらいで痛いの?」と誰かに言ってしまうから。
ブレイディ そうなると人の痛みがわからなくなっちゃうからね。でも、そういうトリッキーな業界でも目覚めている方は結構増えていますよね。
宇垣 多いと思います。一緒にお仕事をする俳優さんやモデルさん、グラビアのお仕事をしてる人でも、お話していることがとってもフェミニズムな方は結構いらっしゃるし、実際「私はフェミニストだから」とおっしゃる人も多くて。少なくとも同世代で同じように仕事をしている人から「そういうものだから」「笑って流しておけばいいんだよ」なんて言われたことはないです。「それ最悪だね。じゃあ次からこうしようか」「この人に言おうか」と言ってくれる人が多いので、全体として成長というより進化している部分はあるのかなと思っています。
ブレイディ それは素晴らしいですね。私は『MORE』という雑誌で連載をやっていたとき、20代後半から30代前半の女性たちと定期的に「今、モヤっていることを聞かせてください」というテーマでオンライン座談会をしていたんです。仕事の話だったり家庭の話だったり、いろいろ聞いてきたけれど特に仕事の話が壮絶で。「それはモヤモヤじゃない。あなたは激怒しているんだよ」と言っても、みんな「モヤモヤしてる」という言葉で流してしまう感じがありましたね。
宇垣 生きていくために仕方なく流す、っていうこともあるでしょうね。
ブレイディ でも、そうやって流し続けていると理不尽な抑圧が続いてしまう。日本の女性は、求められたら完璧にやろうとする人が多いように感じます。自由にやるシスターフッドというより、きちっとするシスターフッドみたいな。
統計によると、日本の女性は世界でいちばん睡眠時間が短いそうです。家事も育児も仕事もしっかりこなすから、寝る時間がないんですよね。それこそ本には自発的にベッドの中に引きこもる「ベッド・ロッティング」の話も出てきますが、50年後の世代のために今の私たちができるのは、家事を適当にやって早く寝るとか、ものぐさになるとか、そういうことかもしれない。
宇垣 ベッド・ロッティングの話は「私がよくやっていることだ!」って思いながら読みました。
ブレイディ セルフケアって、しゃかりきにスキンケアします! 体つくります! みたいに一生懸命やるものではなくて、ベッドの中で1日過ごして好きなことだけやるとか、そういうことが自分をもっと楽にしてあげて、本当にケアしたり大事にしたりすることにつながるはず。
しゃかりきにセルフケアするにはお金も必要だし、それって自ら資本主義に参加してデザイアブルな(選ばれるに値する)存在になろうとしているわけですよね。もうそういう競争やマウンティングよりも今はエンパシーが必要な時代じゃないかなと思います。
仕事も生活も、判断基準は「あの頃の私が恥ずかしがらない自分」
――(会場からの質問) 「他者の靴を履く」ためのマインドセットとは? 「人に頼るのはダメなこと」という自分の中にあるブレーキを外したいです。
ブレイディ これまで、「他者の靴を履くこと(エンパシー)はスキルや能力として磨けるものだから、想像するための知識のベースをつくってください」と言ってきましたが、それに加えて経験が大事だと思っています。エンパシーというのは、先ほどお話しした息子の友達のように経験のベースがないと的確には働かない。もし頭の中だけで想像した誰かの靴を履いているとしたら、それは本当に他者の靴を履いていることにはなりませんよね。他者の靴を履く上で大事な心積もりは、一歩踏み出していろんな経験をしてみること。でも、それって面倒くさいじゃないですか。だから、「面倒くさいことをしてみる」というのが第一歩かなと思います。
それから、自分だけが他者の靴を履こうとするのではなく、自分の靴も履いてもらうことがすごく大事。自分がきつい目に遭っているときは自分の靴を誰かに履いてもらって理解してもらう。そうやっていくと、お互いに他者のことを少しずつわかり合うようになっていくから。「苦しい」と声を上げるのは自分の恥を晒すことではなく、「誰かに自分の靴を履かせて勉強させてあげるんだ」と思えばいい。そのほうが世の中は変わると思います。
宇垣 私は人に頼ることが苦手なんですよね……頼るって難しい。
エンパシーを磨く方法としては、何かわからないことがあったらすぐ本を読むようにしています。例えばウクライナが戦場になったら、ウクライナ作家の小説を読んでみる。たとえ本の上でも、できるだけ「その場所で生きる人がいる」とわかるように、自分が知っている人が生まれる形にしようと思って。
一方で肝に銘じて自分に言い聞かせているのが、「あなたは誰かを理解し得ない」ということ。どんなに本を読んでも、どれだけ数字や情報を頭に入れても、自分には絶対にわかりきれないっていうことだけは忘れないでおこうと思っています。だから「わかるよ」とは言わないけれど、「そうじゃないかな」と想像を働かせることはすごく大事。ただ、それは「誰も私のことをわかりきれない」という意味でもあるので、そこは私の課題だなと思っています。
――(会場からの質問2)ブレイディさんと宇垣さんが、人生に負けないように心がけていることがあれば教えてください。
宇垣 「高校生の頃の私に対して恥ずかしいことだけは絶対しない」っていうのをすごく心がけています。私は、未来がまだ決まっていなくて、何もわかっていないけれど万能感だけがあった女子高生の自分がいちばん強かったと思っていて。例えば、すごくつらかったり、周りがみんな敵だらけに思うようなことがあったりしても、「こういう振る舞いをしたら、あの頃の自分は『素敵』って思ってくれるだろうな」と思える言動をするだけで心が負けないというか、人から何を言われても気にならなくなる。「ダサくない自分である」ということは心がけています。

ブレイディ 私もそう。「あの頃の私が恥ずかしがらない自分」っていうのはすごくよくわかる。10代の私はすごく反抗的なパンク娘だったんですよ、今はもうすっかり丸くなってますけど(笑)。斜に構えていてラディカルだったあの頃の自分に、「だせぇババア」って言われないような生き方をしたいと思っています。仕事でも生活でも、「こっちのほうがきっと楽だけど、これをやったらあの頃の私は『だっせぇ』って言うだろうな」とか、「これは時間がかかるし難しいし、どこへ辿り着くかわからないけど、あの頃の自分は喜ぶだろうな」みたいな視点で決めているところはありますね。
宇垣 そうすると自分のこと嫌いにならずに済むじゃないですか。
ブレイディ そうなんですよ、それがいちばん大きいですよね。自分のことを嫌いになったら心がペシャッと潰れそうじゃないですか。だから、「Cool」か「Uncool」かっていうのが結構基準になっていて、やっぱりUncoolなことはしたくない。美意識というか、もはやそれが自分の倫理観になっている部分があると思います。

完
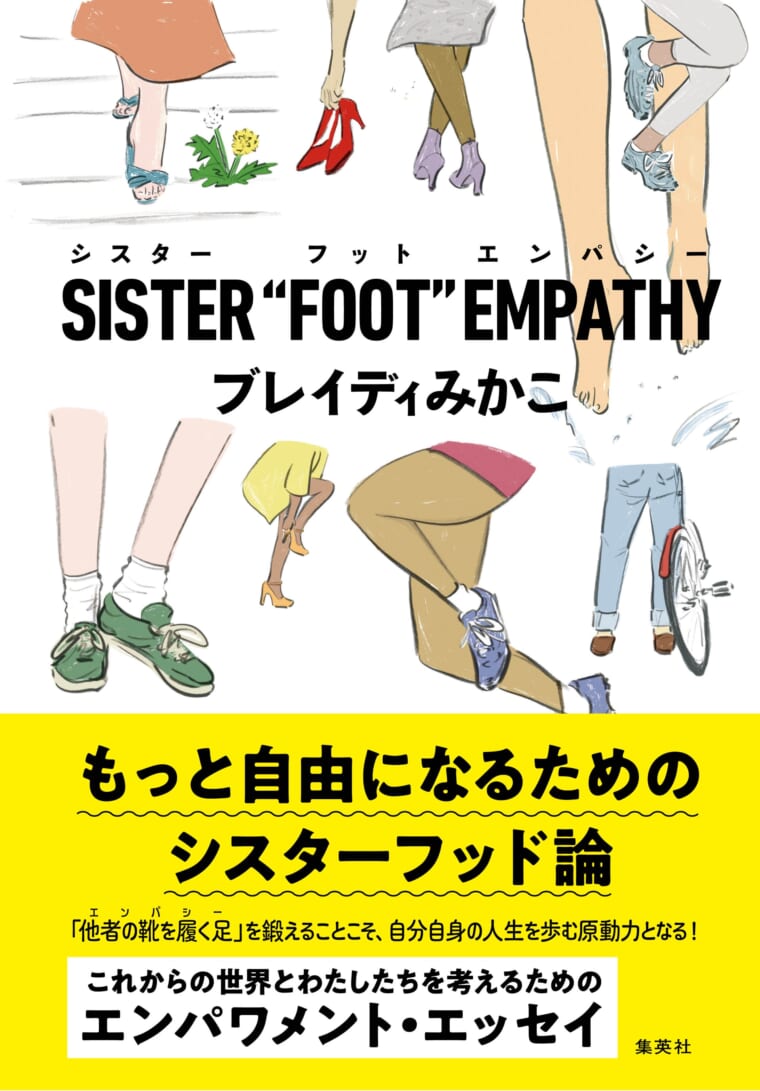
1,760円(税込)/集英社
アマゾンリンクはこちらから
●アイスランド発「ウィメンズ・ストライキ」の“共謀”に学ぼう
●シスターフッドのドレスコードはむしろ「差異万歳!」
●完璧じゃないわたしたちでいい
●シスター「フット」な女子サッカーの歴史
●オンライン・ミソジニーをボイコットするときが来た
●歴史から女性たちを消させない
●バービー、シンディ、そしてリカ
●焼き芋とドーナツ。食べ物から考える女性の労働環境
●街の書店から女性の歴史と未来を変える
●古い定説を覆すママアスリートの存在
……etc
雑誌『SPUR』での連載3年分に、新たに加筆修正を加えたエッセイ39編を収録。
わたしたちがもっと自由になるための、新時代シスターフッド論!
新刊紹介
-

独りで死ぬのはイヤだ 年収200万円、48歳独身漫画家の婚活記
2026/2/26
NEW
-

東西の味
2026/1/26
NEW
-

真夜中のパリから夜明けの東京へ
2025/11/26
-

歩いて旅する、ひとり京都
2025/10/24
よみタイ新着記事
-
- 連載
- 2/23

孤独の功罪
今日も明日も、動画のネタ探しは終わらない 【第10回 息切れしがちのユーチューバー】
-
- 連載
- 2/22
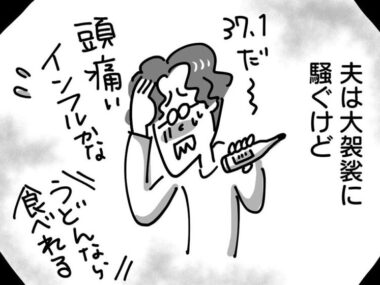
50歳、その先の人生がわからない
自分だと大げさに騒ぐのに、妻が熱を出しても「外食してくるから大丈夫」と言う夫…【50歳、その先の人生がわからない 第6話】
-
- 特集
- 2/21

大人の恋愛はフィジカルから始まる? 年収200万円、48歳独身漫画家が自問自答の末、本気の恋に落ちた
-
- 連載
- 2/20

ケアとアートのダンス ~アクセシビリティのためのプロジェクト・レポート~
ケア現場での意見の違いや違和感をどう受け止める? 違いを楽しむ@≪微分帖≫ワークショップ【前編】
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)



