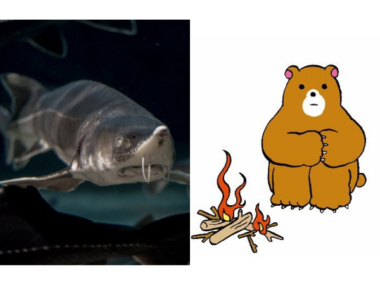2021.10.6
私が女主人に語った、新人ドライバーのありえない失敗談
日経新聞などの書評欄でも紹介された、昭和・平成・令和を貫くタクシードライバーたちの物語を、期間限定で全文無料公開します!(不定期連載)
初回の舞台は「2019年の東京」。主人公である「私」の話から物語は始まります。
いつも鏡を見てる 第1話
プロローグ 【東京 2019年】

私が語るタクシー運転手の小さな物語
女主人がひとりで切り盛りするその店は、開け放った入口の扉に代えて、丈が長くて生地の薄い暖簾を下げている。誰が触れるわけでもないのに、通り過ぎるクルマの勢いが地階まで風を運ぶのか、浴衣の裾がひらひらなびくように暖簾が風に舞っていた。歩けば駅から5分の距離にある一画は商店街と住宅街をつなぐ緩衝地帯で、飲食業を営むのに適した立地かどうかの判断は難しかったかもしれない。20分で100円という格安のコインパーキングと整骨院の向いにある白い三階建ての横幅は6メートルほどでしかなく、一階はラーメン屋で、入り口横のまわり階段を降りた先に、女主人が一年半前に開いた店はある。彼女の名を逆さまにして名付けた『おりか家』である。
先入観が決めてかかっていたのは狭い店内だったが、暖簾をくぐると、思いのほかの広さに、まず驚いた。厨房まで勘定に含めれば、たとえるならバドミントンのコートくらいはあるだろうか。そこに用意された木目のテーブルは四卓しかなくて、あとは横一列に6人が座るカウンター。店内にありあまるこの空間でなら、奥の壁に張り付けるようにして設置されたひかりTVの映像を流す60インチのモニターの前で、酔客が踊りだしたとしても誰の邪魔にもなりはしないだろう。食事どころと聞いていたが、横長の三段の棚に、二階堂や閻魔、いいちこ、といったいくつもの銘柄の焼酎と日本酒が一銘柄、それに混じって何本かのサントリーの角瓶が、どれも常連客の名入りの札を下げてキープされている。近所にはタクシー会社があって、明け番の運転手たちが、早朝から営業しているこの店にやってくることもある。キープされたボトルの何本かは、その運転手たちのものだった。ひかりTVは北の演歌大全集を流していて、スピーカーからは『石狩挽歌』が聞こえていた。
ランチメニューから私が選んだ一品を運んできた女主人が、バッグから取りだした黒革の財布をカウンターの上に無造作に置いた。使い込んだ年月が、そうと気づかせずに薄皮をまだらに剝いでいつの間にか元の色を失わせるのが常だとすれば、三つ折りのそれが重ねた年季は3年や5年ではきくまい。新宿の小田急百貨店のセール品の籠から選びだしたもので、革の上から花柄の小さな刺繡を施してある。内側の布にも同じ図柄が描かれていて、そこが気に入って衝動買いしたという1万5000円の財布である。「それで?」とでも言いたげな顔を私に向けた女主人が、私が語りだした新人タクシー運転手の小さな物語に耳を傾けたのは、「1万5000円は、当時の私には大金でした」と付け加えてからだった。
新人ドライバーのありえない失敗談
右折すれば「犬吠埼」と記された道路標識を何キロか手前で通りすぎ、住宅街を抜けた県道の左右は真っ暗闇で、おそらく田畑が広がっているのだろうとは想像がついた。道案内のカーナビが右折を指示したのは、その暗闇の先である。
曲がったとたん道はいきなり狭くなり、クルマ一台がやっと通れる程度の路地に変わった。画面に50メートルほど先の踏み切りが映り、真横にあるのが目的のキミガハマエキだと表示していた。遮断機こそあるものの、踏み切りといっても狭い路地を幅1メートルほどの単線の軌道敷が横切っているだけで、そこを通過すると道はすぐに左に折れ、ガイドが終わった。タクシー運転手に転職して日の浅い彼が、カーナビの案内を頼りに銚子電鉄の君ヶ浜駅前に辿り着いたのは、すでに日付が三月四日に変わった午前三時ちょうどのことである。
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)