2025.4.26
動物パートナーを喪って「親が死ぬよりも哀しかった」【猫沢エミ×小林孝延・往復書簡9】
当記事は公開終了しました。
2025.4.26
当記事は公開終了しました。
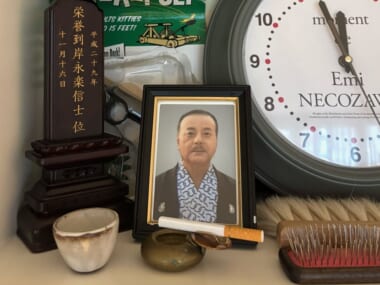
真夜中のパリから、夜明けの東京へ

真夜中のパリから、夜明けの東京へ

真夜中のパリから、夜明けの東京へ

真夜中のパリから、夜明けの東京へ
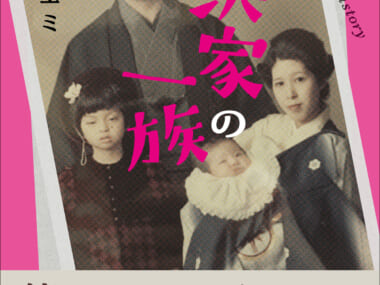

猫沢家の一族

2026/2/26
NEW

2026/1/26
NEW

2025/11/26

2025/10/24

ヘルシンキ労働者学校——なぜわたしたちは「ボーダー」を越えたのか


実録・メンズノンノモデル 創刊40年の歴史を彩る男たち

実録・メンズノンノモデル 創刊40年の歴史を彩る男たち