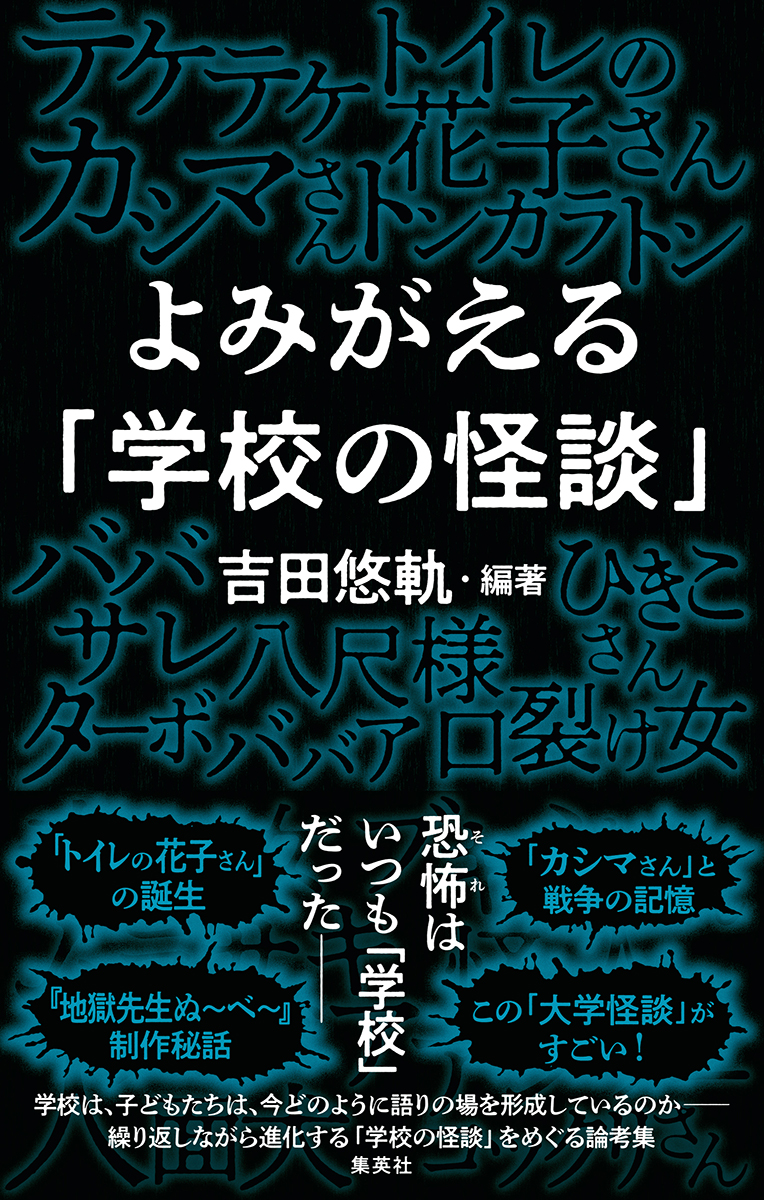2018.10.24
帯留め(三)
どのくらいの間、見入っていたのか。気配にふと顔を上げると、店の奥からお年を召した女性が出てきた。
七十歳は過ぎていようが、垢抜けた美しい人だ。目が合う。と同時に、私は興奮をぶつけていた。
「随分、古いものですね。四分一ですよね」
女性はおや、という顔をして、頷きながら私を誘った。
「よかったら、中でゆっくり見てらしてください」
言葉を受けて、私は店に入った。
売りつけられる不安はなかった。むしろ、手の届く値段なら、ひとつは持って帰りたい。既に、私は考えていたのだ。
やや薄暗い店内は、古びていたが、女性同様、こざっぱりと清潔だった。
奥に据えてある机の前に、店主が腰を下ろしている。
先の女性と夫婦であるのは、多分、間違いなかろうが、主人は妻より随分と老け、顔色もあまりすぐれなかった。
聞けば、長年の持病があり、年齢的にも店を続けることが難しくなってきたという。
「今年いっぱいかな。だから、この際、親父のコレクションを少し手放そうと思ってね」
(ああ、この店もなくなるのか)
こういう話は切ないばかりだ。
感傷的になったものの、机の上に女性の手で帯留が並べられていくにつれ、意識は素直にそちらに移った。
蜆、鬼灯、栗、龍、鯰、鼠、牛、鮎、花鳥……。
僅かな巧拙こそあれ、いずれも見事な金工細工だ。目を丸くして唸っていると、店主が鑑定用の単眼鏡を貸してくれた。
改めて拡大して見れば、一センチに満たない鼠の歯までが、きちんと刻まれている。
「すごい。素晴らしい」
芸のない言葉しか出てこない。
「今の人から見ると、汚い色でしょうに」
店主がやや掠れた声で言う。
「いえ! この美しさがわからないなんて、野暮の極みです」
謙遜だとはわかっていたが、つい、声が大きくなった。
店主は笑った。
「そう言ってくれると、親父もきっと喜びますよ。なにせ、あの空襲から守り抜いた品ですからね」
聞いて、私は目を上げた。
店主は皺だらけの顔に、なお皺を作って微笑んでいる。
(そうだ)
この一帯は、東京大空襲でほぼ壊滅した地域ではないか。
「戦前から、ここでお店を?」
「ええ。大正時代に始めましてね。当時の店は燃えちゃったけど」
「商品は疎開させたんですね」
訳知り顔で頷くと、店主は小さくかぶりを振った。
「店は全焼しましたが、金庫だけが残っていたんです」
店主は当時小学生、その父は明治時代を知る人だった。
ふたりとも丁度、徴兵を免れる年代で、家族は東京に残っていた。
地方から来た人は疎開できるが、東京生まれで東京人同士で結婚した人は、親類縁者も皆、東京。縁故を頼って疎開するのは、なかなかできないことだったのだ。
空襲はそんな人達を無差別に殺し、焼夷弾で町を焼き払った。
幸いにして、時計屋父子は生き延びることが叶ったものの、町は一面の焼け野原となり、かつて店のあった場所には金庫だけが立っていたという。
「昔の金庫ですからね。冷蔵庫ほどの大きさがあるんです。それだけが、広場に置かれたみたいに残ってたんですよ。けど、凄まじい熱でしたから、一夜明けても金庫は真っ赤に焼けて燻っていましてね。とても、手では触れない。けど、水を掛けてはいけない。すぐに開けてもだめだと、親父は言いまして。なんでも、熱いうちに扉を開けると、金庫の中に熱が入って、すべてが燃えて溶けてしまうそうなんです。なので、親父と私は交代しながら、徹夜で金庫の番をしました。きれいに冷めて、もう大丈夫だろうと思えるまで、一週間掛かりましたね。それでドキドキしながら扉を開けたら、思惑どおり、中には火の気配もなく、すべてきれいに残ってたんです」
「よかったですねえ」
「ええ。これらの品は、その金庫にしまっておいた物なんです。父は金工細工が好きでしてね。さして商売にもならないのに、古手の物や良い物を見つけると買って、集めていたんです」
「そんな思い出の品を、お売りになっていいんですか?」
「いいんですよ。うちは跡継ぎもいないんで、好きな人に持ってもらえたほうがいい」
寂しい言葉だ。
色々事情はあるのだろうが、手放すのは辛いだろう。
だが、そのお陰で、私が良質の四分一を目にしているのは間違いない。
(やはり、どれかひとつは欲しいな)
店主の語る物語は、私の所有欲を一層、駆り立てた。
思ったより、値段も高くない。
相場はわからないけれど、これなら小遣いで買える範囲だ。
私は改めて、ひとつひとつを手にとって、つぶさに眺め、迷いに迷った。その間、拙い言葉で延々と細工を褒め続けていたところ、
「本当にお好きなんですね」
少し呆れた口調で言って、店主は妻に頷いた。
「せっかくだから、奥の手箱にある、あの鮎をご覧に入れてあげて」
やはり、人手に渡したくない品はあるのだ。
全部を売り払わないことに人情を見て、私はむしろホッとした。老夫婦の生活が、逼迫してないことも嬉しかった。
(お父さんの形見でもあるはずだもの)
鮎の帯留なら、目の前にもひとつある。
これも充分、素敵だが、店主秘蔵の品ならば、きっと見事に違いない。
眼福に与る礼を述べつつ、私は女性が戻るのを待った。(つづく)

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)