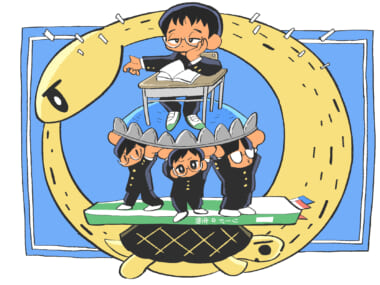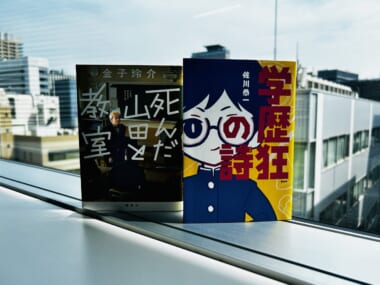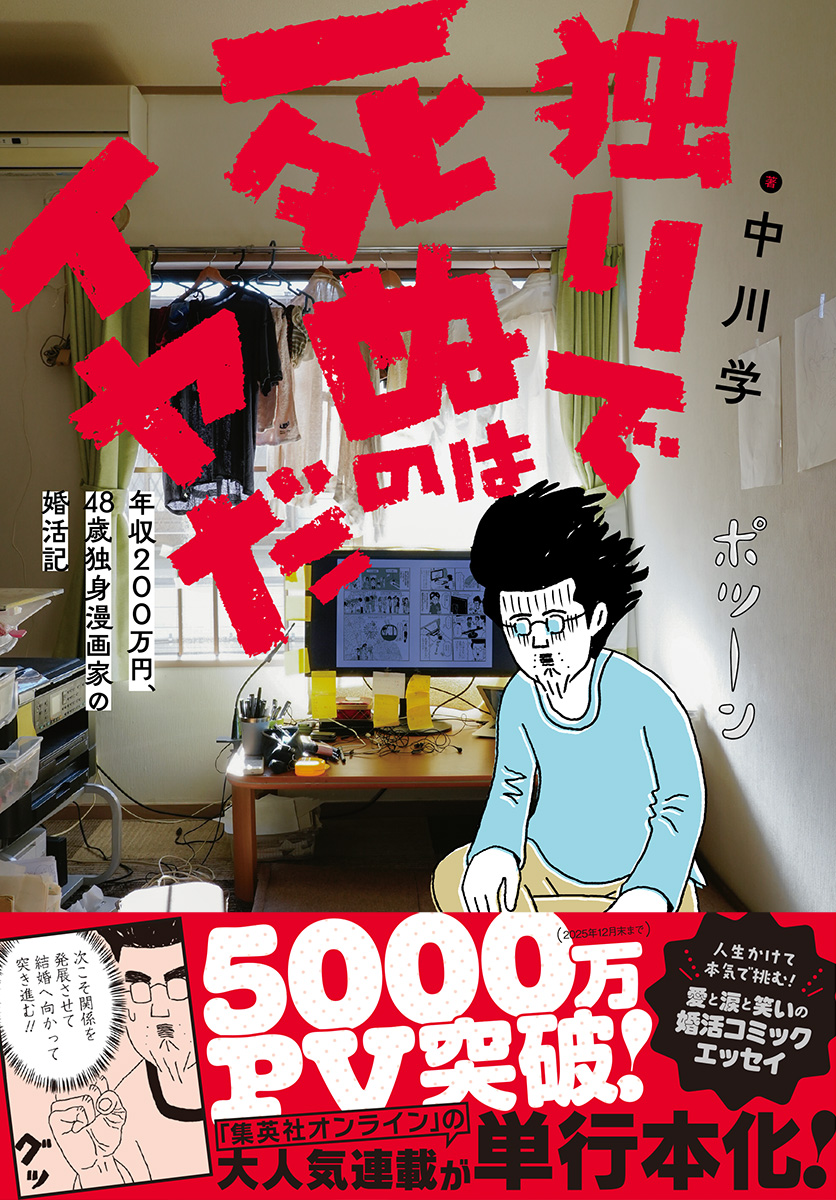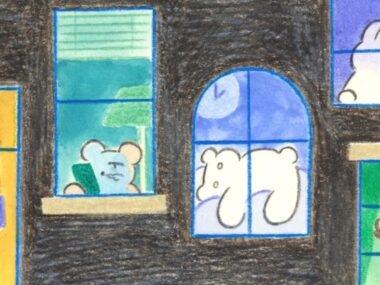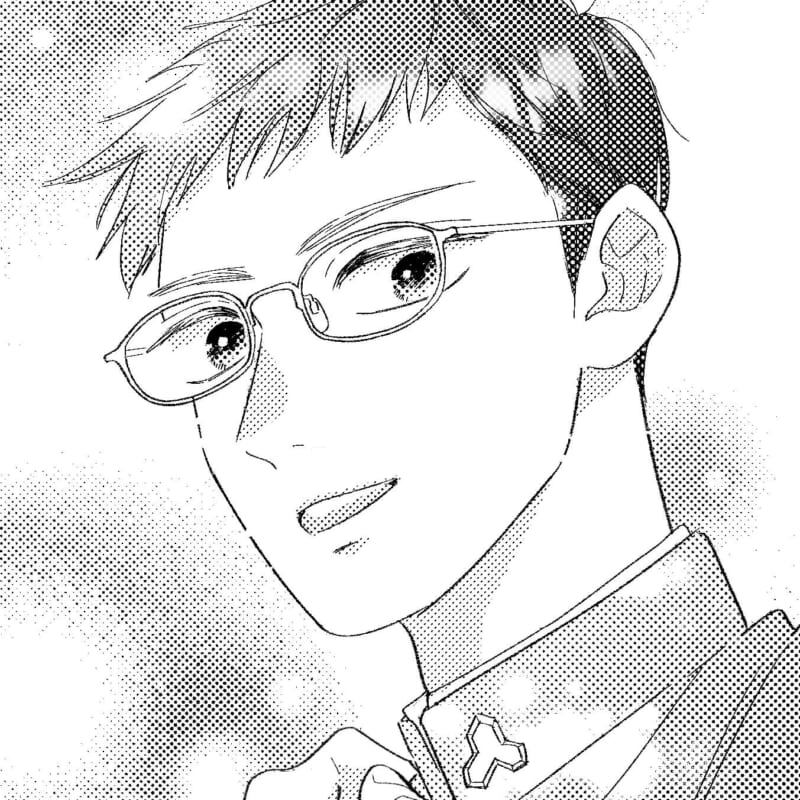2025.10.11
寺山修司にすばらしい詩を書かしめた魅力とロマンあふれるハイセイコー【人生競馬場 第3回】
朝倉未来との共通点
記事が続きます
話が少し逸れるが、これは現在の日本格闘技界における朝倉未来選手の在り方にも近いと言えるだろう。この原稿を書いている時点では、朝倉未来選手はRIZINという日本最大級の格闘技団体で敗北を重ねていた時期を乗り越え、元チャンピオンの鈴木千裕選手とクレベル・コイケ選手を判定で下して復調気味といったところなのだが、彼はもともと街で喧嘩を繰り返すばかりの手の付けられない「豊橋の不良」だった。そこから前田日明主催のTHE OUTSIDER(私の感覚で言えば「地方競馬」的なものである。ちなみにOUTSIDERに出ていた時代の狂犬・瓜田純士とBREAKING DOWN以後の瓜田純士は同一人物とは思えないほど成熟しているので、ご興味ある方はぜひご覧いただきたい)で頭角を現し「路上の伝説」と呼ばれ、そのままRIZINというプロの舞台に上がってしばらく快進撃を続け、その後負けが込んできても粘り強く人気を保ち続けたのである。ヴガール・ケラモフに負け、YA-MANに負け、平本蓮に負け、もうダメだもうダメだと言いながら、多くの人々は朝倉未来の応援をやめられない。人々は何度彼の無残な負けを見せられても、破竹の快進撃を続けていた「あの頃」の朝倉未来が帰ってくるのではないか、と毎回期待を寄せずにいられないのである。そして実際、今の彼はその期待に再び応えつつある。
何があっても朝倉未来を応援する人間は、格闘技ファンの間では朝倉信者、「アサシン」などと呼ばれ揶揄されるが、結局のところそうした呼称が生まれること自体に彼の凄みがあるのであり、彼は現代格闘技界のハイセイコーだと言ってもいいだろう。ハイセイコーと朝倉未来を見れば、そこには大衆の支持を得るための大きなヒントが確実にある。そう、足が速いだけでも格闘技が強いだけでも、歌がうまいだけでもダンスがうまいだけでも、顔が良いだけでも話が面白いだけでもダメなのだ。何かインフルエンサー的なものを目指す人はぜひ過去のスターたちを参考にしてほしい。あなたはあなたのファンを増やすための、時代に応じた物語を構築しなければならないのだ。
マジで話が逸れすぎた。ここで一点言い添えておきたいのだが、朝倉未来がガチの不良で少年院上がりであるのに対し、ハイセイコーの出自の実情は大衆イメージとは少し異なる。まずハイセイコーの父チャイナロックは産駒が次々にGⅠレースを制した一流種牡馬で、母ハイユウも地方で相当な実績を残した活躍馬であり、中央入りは当初からの計画通り、地方デビューは形だけのものだった。つまりハイセイコーの中央における活躍はいわゆる「下克上」とは言いがたいもので、中央での活躍前からブームが大きくなったのは話題作りのため、マスメディアが煽り立てた結果だったのである。今だとおそらくハイセイコーの隠されたエリート性などは簡単に暴かれ、メディアのイメージ戦略など機能しないだろうが、当時はまだメディアのそんな大雑把な計算に人々がホイホイ乗ってくれる時代だった。「大衆扇動」と言ってしまえば危険な香りがするが、こうした誰もが見て知っている共通の対象があった時代、その規模がケタ外れに大きかった時代の熱狂に、なんとなく羨ましさを感じてしまうのは私だけだろうか。
ハイセイコーが出走したレースのいくつかは視聴率が20パーセントを超え、日本ダービー当日には朝日新聞紙上で「サザエさん」の題材になり、引退直後に主戦騎手の増沢末夫がリリースしたレコード『さらばハイセイコー』は45万枚を売り上げ、『週刊少年マガジン』や『週刊少年サンデー』の表紙も飾り、『襟裳岬』や『トラック野郎・望郷一番星』といった映画にも出演した。そしてハイセイコーといえば、寺山修司の『さらばハイセイコー』という詩(増沢のレコードと同じ題だが別物)が有名であろう。演劇をはじめとしてマルチに活躍した寺山修司は、何の分野の人なのか一意に定義することが難しいが、とにかく競馬を文学の域に押し上げた功労者であることは間違いなく、競馬ファンとして過去の歴史を振り返れば百パーセント行き当たる名前である。
寺山の『さらばハイセイコー』はおそらく彼の「競馬仕事」の中での代表作であり、まずは「ふりむくと」「一人の〇〇が立っている」で始まる節が畳みかけられる。「〇〇」には少年工、失業者、車椅子の少女、ピアニスト、四回戦ボーイ、受験生などが入り、次々にその人生のワンシーンがハイセイコーと絡めて切り取られていく。これもどんな世代のどんな人間もハイセイコーを見ていたのだ、という共通了解があってこそ書けるものである。そして終盤になると「ふりむくな」と言葉が変わり、「ハイセイコーはもういないのだ」という寂しさが歌われ、最後は次のような節で締められる。
だが忘れようとしても
眼を閉じると
あの日のレースが見えてくる
耳をふさぐと
あの日の喝采の音が
聞こえてくるのだ
この詩のように多種多様な人間を次々にピックアップしていくやり方は、演劇人としての手法に似ているためか、寺山の文章ではよく使われる方式である。ただ、他の競馬に関するエッセイなどでもかなりステレオタイプ的な──基本的には社会から脱落した──人物が頻繁に描かれるため、何かその裏に際限なく文章を生成するためのフォーマットめいたものを感じてしまうことも(個人的には)多い。正直、こんな奴おらんやろとしか思えない不遇な人物が、彼のエッセイの中では無限に作られている。
しかしこのハイセイコーの詩でははじめから個々の人物はフィクションだとわかっており、そこに「ハイセイコー」という実在の中心が据えられることでその文章の強度が高められている。そして、競馬を観戦する群衆の一部として切り取られる個々の人物の部分には──おそらくハイセイコーの「自己投影」の射程の広さを計算した上で──読者が自分を代入できるようになっているのである(多分)。これは演劇において避けがたい「俳優」と「観客」の分離に苛立ち、その限界を破壊しようともがいていた寺山にとっての、一つの解答例であったようにも思える。
寺山はハイセイコーが出走したスプリングステークスの予想の中で、「ハイセイコーが強いことはわかっている。しかし、英雄が出てきたときには、それを倒す馬に賭けてみるのが男というものではなかろうか」「そんなわけで、これから二、三年、私はハイセイコーのために身上をあやうくするかも知れない。しかし、それでも私は、ハイセイコーを負かす馬を買い続けてみたい」と言っている。つまり、寺山はどちらかといえば、大衆の圧倒的支持によって権威化してきたハイセイコーの「アンチ」だったのである。そんな寺山をしてこのすばらしい詩を書かしめたハイセイコーの、大衆を嵐のように巻き込む魅力と秘めたる文学性に、やはり何かすべてにまとまりのついてしまった現代に蘇らせることの難しい、大きなロマンを感じずにはいられない。寺山修司やハイセイコーがいた時代を心から羨む私の物欲しげな視線に対しても、寺山は「ふりむくな」と言うだろうか。
次回連載第4回は11/8(土)公開予定です。
佐川恭一の傑作エッセイ集、大好評発売中!
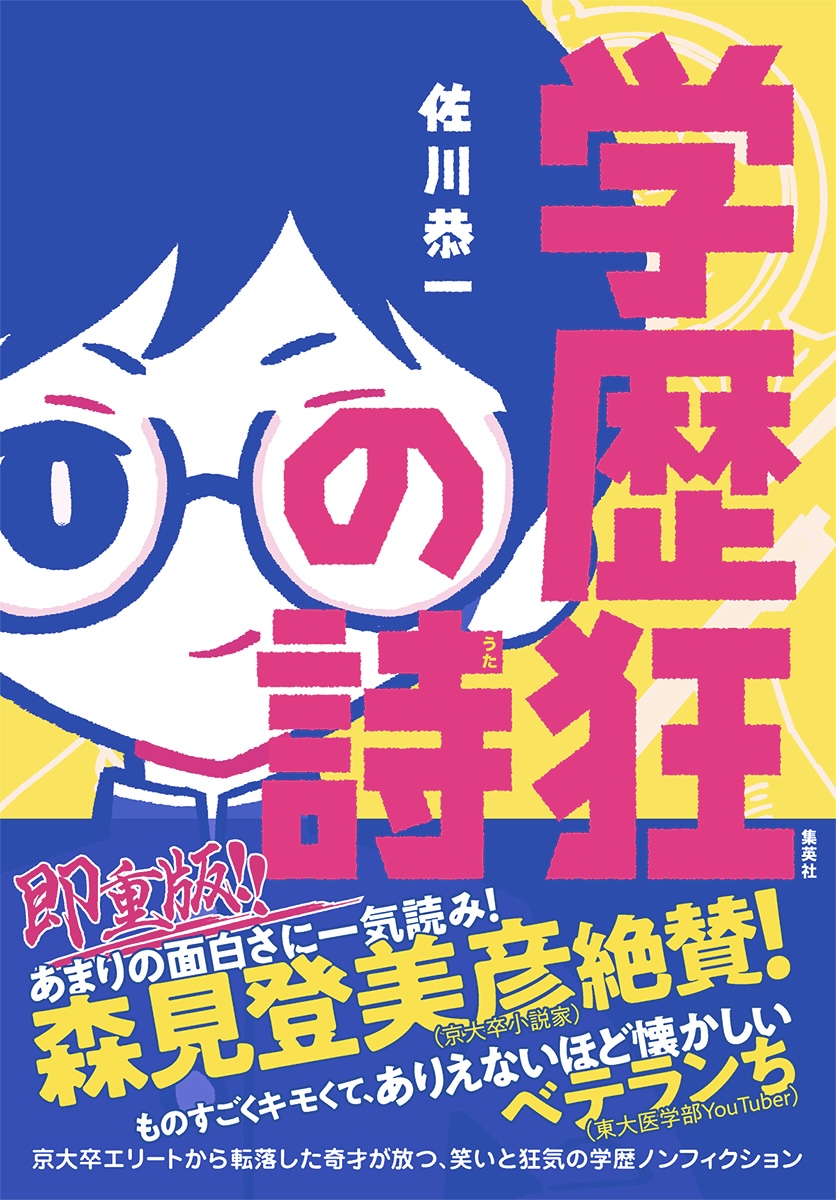
あまりの面白さに一気読み!
受験生も、かつて受験生だった人も、
みんな読むべき異形の青春記。
——森見登美彦(京大卒小説家)
最高でした。
第15章で〈非リア王〉遠藤が現役で京大を落ちた時、
思わず「ヨッシャ!」ってなりました。
——小川哲(小説家・東大卒)
ものすごくキモくて、ありえないほど懐かしい。
——ベテランち(東大医学部YouTuber)
なぜ我々は〈学歴〉に囚われるのか?
京大卒エリートから転落した奇才が放つ、笑いと狂気の学歴ノンフィクション!
書籍の詳細はこちらから。
記事が続きます
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)