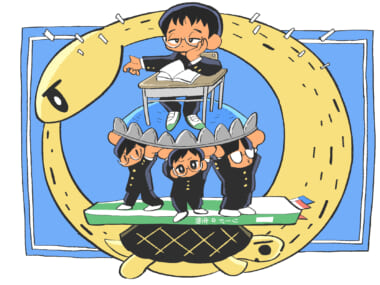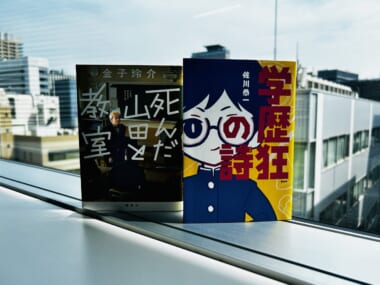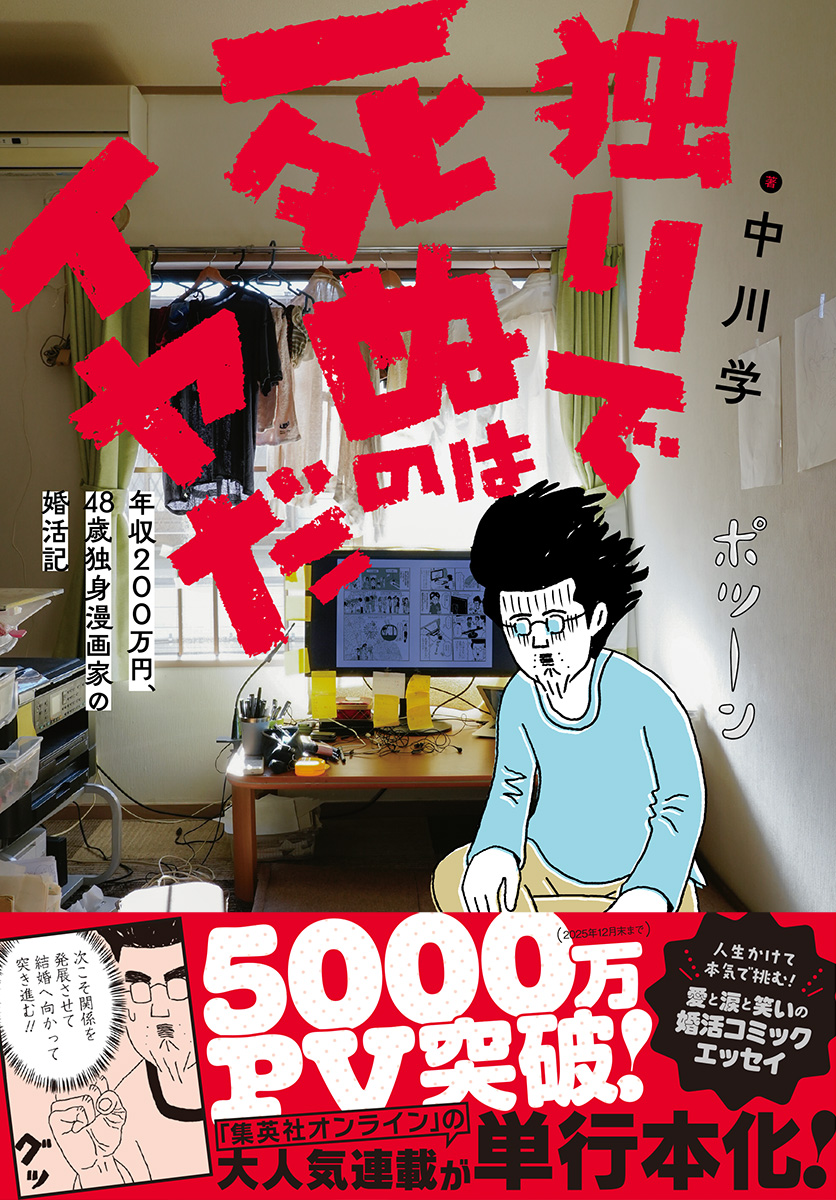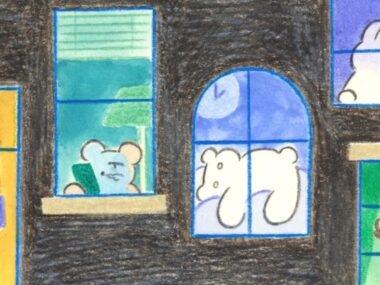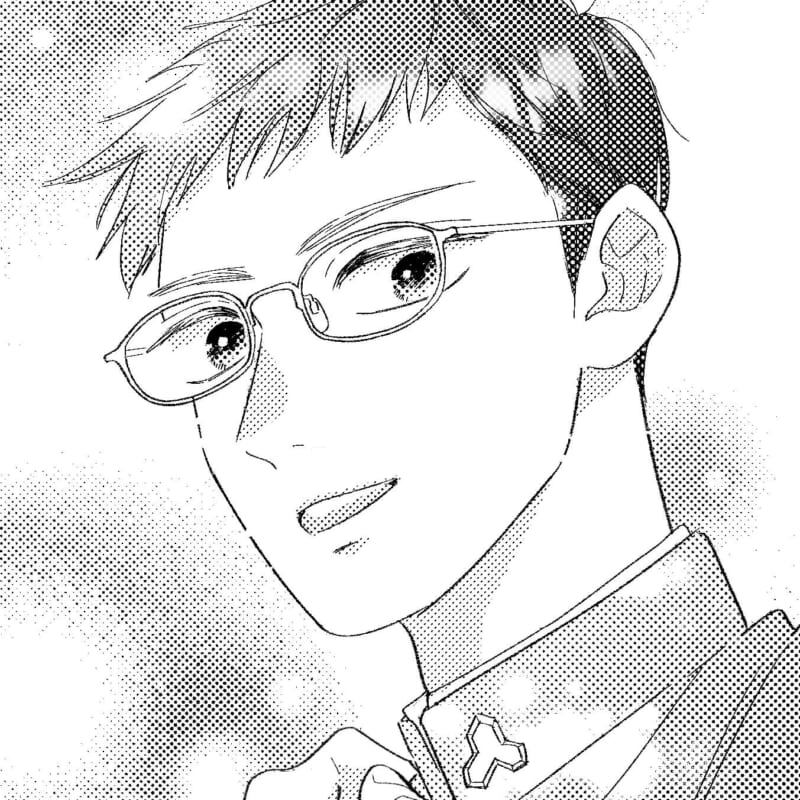2025.10.11
寺山修司にすばらしい詩を書かしめた魅力とロマンあふれるハイセイコー【人生競馬場 第3回】
前回は、牡馬クラシックレース三冠を達成した名馬・ナリタブライアンの思い出を綴りました。
今回は、競馬界初の〈国民的アイドル〉と言えるハイセイコーについて存分に語っています。

記事が続きます
中央競馬と地方競馬の違いは…?
1985年生まれの私は、残念ながらリアルタイムでハイセイコーを知ることができなかった。しかし、この馬なしに現在の競馬はなかったと言っていいほどの、競馬界初の巨大な社会現象を引き起こしたスーパーホースがハイセイコーであり、競馬について書くならこの馬に触れないわけにはいかない。おそらく若い競馬ファンでも名前ぐらいは聞いたことがあるだろう、と思うのは私がオッサンだからだろうか。
このハイセイコー現象を語るにあたって、まず日本の競馬の歴史について簡単に振り返ってみたい。競馬ファンでなくとも競馬が「中央競馬」「地方競馬」に分かれていることはなんとなく知っている方が多いかもしれないが、これらはサッカーのJ1・J2のような同組織の上下関係にあるわけではなく、それぞれ異なるルーツから成長してきた別組織である。ハイセイコーのみならず、今後触れることになる馬たちについても理解しやすくなるよう、一応ここでそれぞれの成立過程を見ておこう(流し読みで大丈夫です)。
〈中央競馬〉
中央競馬は競馬発祥の地・イギリスで完成した近代競馬を元にして始まった。日本で洋式競馬が行われたのは1861年、在留外国人によって開催された横浜でのレースが最初といわれている。これは治外法権に基づいて開催されたため、江戸時代における賭博禁止法の縛りを受けず馬券が発売され、江戸幕府も西欧人と友好関係を築くため洋式競馬開催を援助した。
後に日本人も洋式競馬を模倣して上流階級のための催しとして独自の競馬を開催するようになったが、こちらは馬券発売ができなかったため、経済的な理由で早々に廃れてしまう。日本政府公認の賭博競馬が初めて行われたのは1905年。政府は日清・日露戦争で日本産軍馬がパワー・スピードの両面において外国馬に劣っているという事実を痛感し、競馬は軍馬改良という国策にかなうとして賭博禁止の例外とされた。その後も再び賭博が禁止される時期を経て、1923年に馬券合法化を目指す安田伊左衛門(「安田記念」の安田さんです!)らが中心となって(旧)競馬法を制定し、競馬を「軍馬の改良と増殖のための有効な手段」と明確に位置づけて復活させる。その結果「日本競馬会」が発足し競馬の開催を取り仕切るようになったが、第二次世界大戦で中断。戦後1948年のGHQによる日本競馬会解散と現行の(新)競馬法制定、国営化を経たのち、農林水産省の外郭団体、特殊法人・日本中央競馬会を主催者とすることが決定された。こうして現在まで繋がる「中央競馬」が始まったのである。
〈地方競馬〉
地方競馬は洋式競馬をルーツとする中央競馬とは異なり、日本の馬術の流れを汲んでいる。日本の馬術は神事に由来するものであり、地方競馬は神社の祭典において奉納されてきた神事競馬をルーツとしている。1910年には競馬規定の改正により、地方の畜産組合が地方長官の許可の下で競馬を実施することが正式に認められたものの、やはり馬券発売は禁止されていた。制限付きの馬券販売が認められるようになったのは、1927年制定の地方競馬規則によってである。
1939年には軍馬資源保護法が制定され、軍用保護馬の鍛錬を行うための鍛錬馬競走として馬券発売を正式に許可されるものの、1943年には第二次世界大戦の激化でやはり地方競馬も停止。戦争が終わると軍馬資源保護法が撤廃され、地方競馬はその存在意義を失った。しかし国の財政難を救う目的でギャンブルが解禁され、地方自治体の管理下での公営ギャンブルが認められ、1948年には前述の(新)競馬法が成立。1962年になると地方競馬の主催者は民営の馬事関係団体から地方自治体に移り、特殊法人地方競馬全国協会が設立され、現在まで至っている。
長々となんのこっちゃという感じかもしれないが、とにかく農林水産省の監督の下でやっている、賞金とかもめっちゃ出るので強い馬も集まってくるデカい団体が中央競馬で、地方自治体等が主催するちょっとレース規模や賞金などもかわいい感じの小さな団体が地方競馬だと思ってもらえれば良い。お笑いコンビ「さらば青春の光」のYouTubeでは地方競馬の馬券を買う企画がよく行われているが、森田氏は地方競馬を「かけっこ」と表現しており、うまい騎手がいると「中央の乗り方してる!」とよく言っている。エンタメなのでやや言い過ぎの感はあるが、実際に中央と地方のレースを見比べてみると頷けるところもないではない。いや、めっちゃある。だが、「さらば」が何度も地方競馬企画をやっていることからもわかるように、地方競馬には何とも言えない野生の魅力があるのだ。最近と言っていいかわからないが、五月末あたりに令和ロマンの高比良くるま氏が参加した回などもかなりアツい展開になっているので、ご興味ある方はぜひ見てもらいたい。
とにかくこうして異なるルーツから成長してきた中央競馬と地方競馬だが、中央競馬がエリートで地方競馬は雑草、というイメージは今に至るまで根強く続いている。実際所属馬の力の差や団体の規模からしてそれも仕方のないことなのだが、この「中央」と「地方」の区分けが、「判官びいき」とも言われる日本人を熱狂させる下剋上ドラマを何度も生み出すことになる。その輝かしい歴史の最初の一頭が、当時知らない者はないほどに流行したハイセイコーだったのである。
ハイセイコーは競馬界に初めて誕生した「国民的アイドル」だったと言ってもいい。1923年以降、上流階級の人間でなく社会からやや逸脱した「博徒」的な人間の文化となっていた競馬を、一般市民に好意的に受け入れられるきっかけを作ったのは間違いなくハイセイコーであり、その競馬界における功績はあまりにも大きい。
1970年生まれのハイセイコーは、1972年~1974年にかけてGⅠ級レース2勝の活躍を見せた(細かい話だがハイセイコーの時代にはグレード制が導入されていなかったため重賞にGⅠ、GⅡといった呼称がなく、クラシックレースに天皇賞(春)(秋)、有馬記念を加えたレースが「八大競争」と呼ばれ別格の扱いを受けていた)。数字だけ見れば「大レースはたった2勝?」と思われるかもしれない。
そう、ハイセイコーは決して無敵の強さを誇ったわけではなかった。確かに地方競馬時代、大井競馬場でのレースは圧巻の一言で、トレードマークの白いメンコを揺らしながら大差勝ちを繰り返していたが、中央競馬に参戦して初戦の皐月賞トライアル・弥生賞(重賞)は1と3/4馬身差、その後皐月賞(「八大競争」の一つ)は二馬身半の差で制するものの、次のNHK杯(重賞)はアタマ差の辛勝だった(これは日本ダービーに備えて東京の左回りの馬場に慣れさせるため、過酷なローテーションを組まれたせいだとも言われている。ちなみに馬にも右回りと左回りで得手不得手があり、馬券を買う側としては簡単に無視すべきファクターではない)。
記事が続きます
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)