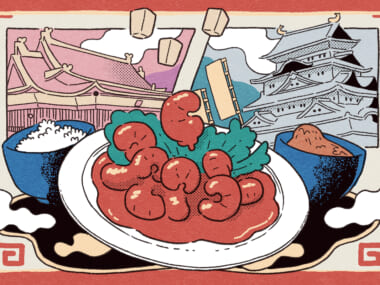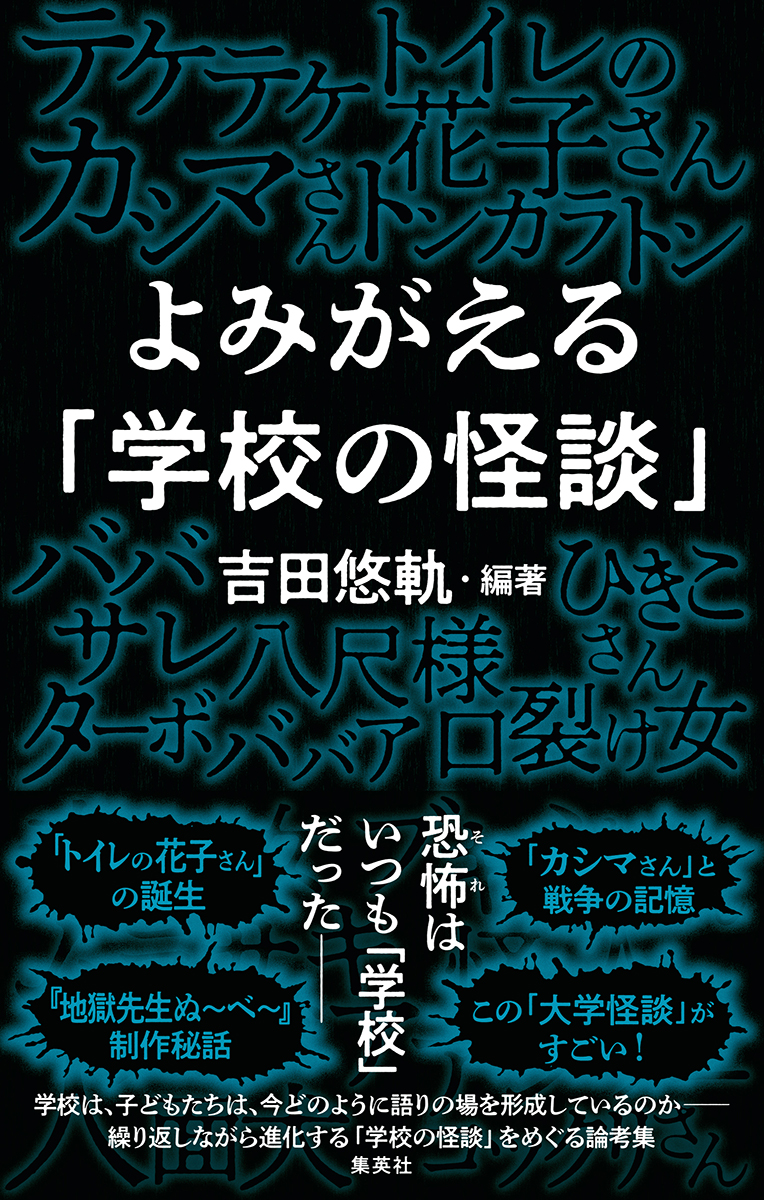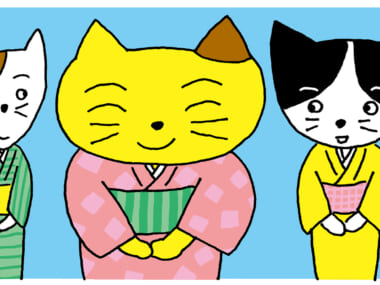稲田俊輔
イナダシュンスケ
料理人・飲食店プロデューサー。鹿児島県生まれ。京都大学卒業後、飲料メーカー勤務を経て円相フードサービスの設立に参加。
和食、ビストロ、インド料理など、幅広いジャンルの飲食店25店舗(海外はベトナムにも出店)の展開に尽力する。
2011年には、東京駅八重洲地下街にカウンター席主体の南インド料理店「エリックサウス」を開店。
Twitter @inadashunsukeなどで情報を発信し、「サイゼリヤ100%☆活用術」なども話題に。
著書に『おいしいもので できている』(リトルモア)、『人気飲食チェーンの本当のスゴさがわかる本』『飲食店の本当にスゴい人々』(扶桑社新書)、『南インド料理店総料理長が教える だいたい15分!本格インドカレー』『だいたい1ステップか2ステップ!なのに本格インドカレー』(柴田書店)、『チキンカレーultimate21+の攻略法』(講談社)、『カレー、スープ、煮込み。うまさ格上げ おうちごはん革命 スパイス&ハーブだけで、プロの味に大変身!』(アスコム)、『キッチンが呼んでる!』(小学館)、『ミニマル料理』(柴田書店)、『個性を極めて使いこなす スパイス完全ガイド』(西東社)、『インドカレーのきほん、完全レシピ』(世界文化社)、『食いしん坊のお悩み相談』(リトルモア)、『異国の味』(集英社)、『料理人という仕事』(筑摩書房)、『現代調理道具論』(講談社)、『ミニマル料理「和」』(柴田書店)など。
最新刊は『食の本 ある料理人の読書録』(集英社)、『ベジ道楽』(西東社)。