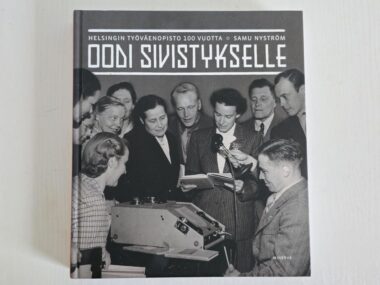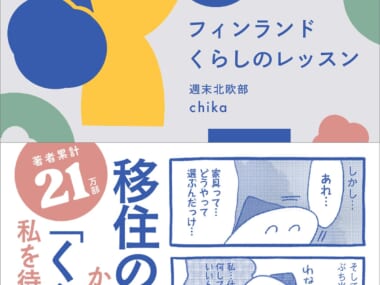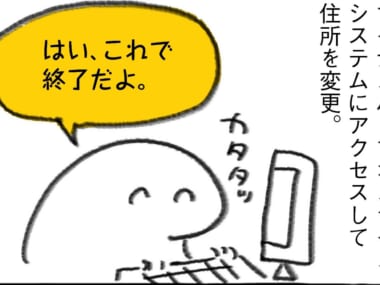2025.11.25
わが子の小学校の「愛国教育」をきっかけにロシアを出てフィンランドへ来たシングルマザー(第2回 前編)
さて、周囲の意見を聞いてロシアを出る決断ができなかったターニャは、ついに長年勤めた優良企業を辞めて、2021年に息子とロシアを出ることになった。きっかけは、息子がロシアの地方都市の小学校に入学したことだった。
「息子が入学したとき、ロシアで奇妙な、恐ろしいことが起きていると気がついたの。私はそれまで、安全なバブルの中に生きていたのかも」とターニャは振り返る。2015年6月、ターニャは、9月に始まる息子の小学校の就学説明会に出た。そこで、子どもたちの学校のトイレに、便座と個室のドアがついていないことを知った。
「トイレに便座をつけてほしい」と、大勢の保護者たちを前にターニャは学校に求めた。ほかに2人の保護者も賛同し、書面や電話で、学校に何度か申し入れた。そして「自分たちがお金を出してもかまわない。便座とドアをつけさせてほしい」と頼んだ。けれども校長は「すべて法に則っており完璧に基準を満たしている」と拒否した。そこでターニャは、ロシア連邦消費者権利保護・福祉監督庁(公衆衛生と消費者保護を担うところ)に申し立て書を送った。
1年生として子どもたちが入学して1週間後、学校全体の保護者会が開かれた。
教頭が、
「何か学校に不都合があれば、どこかに書面で訴える前に、まず私たちに相談してください」と言った。
ターニャは、「行政に申し立てする前に、6月に手紙、7月には別の保護者が電話で学校に相談したけど、何も対応しなかったからです」と言った。
担任は「私は血圧が高いんです。もし保護者が、引き続き要求するなら教員を辞めます。いま、教師人生で初めて授業でミスをするのではと不安に感じています。そもそも、私の孫もこの学校に通っていますけど、トイレの便座なしで問題なく過ごしています」と言い、最後に「人を裁くな。あなたがたが裁かれないようにするためである」という聖書の一節を引用した。
他の保護者たちは、
「もし便座なしのトイレで子どもが何かに感染しても、今はすべて治療できるという情報もあるし」
「校長に文句を言う保護者がいることで、ほかの子どもたちにまで不利益が出そうだ。もう言わないでほしい」
「もしこの学校がいやなら他の学校に転校すればいい」などと、口々に言った。
話を聞きながら私は、自分の家のトイレで何度か、便座が上がっていたことに気がつかずに座ってしまったときの不快な気持ちを思い出していた。便座がないトイレとは、トイレに行くたびにあの緊張感が常に続くということか。学校で、トイレの個室にドアがないのも苦痛だ。
そして学校のトイレ問題と言えば、私は「素手トイレ掃除運動」を連想してしまい、「ああ……ちょっと違うんだけど、日本では便器を素手で磨くと心が磨かれるとかいって、学校や公衆トイレでそんな運動をしている人たちもいるんだよね……」と話して、便座なしトイレの話をしているターニャに「ありえない」と気持ち悪がられた。
記事が続きます
ターニャは、自分の息子ではなく、学校全体の環境を良くしようと働きかけていたのだが、保護者たちの多くは、学校に何か要求することそのものを怖がっているようだったという。その理由の一つは、ターニャと、彼女より一回り若い親たちの受けた教育の違いではないかと彼女は考えていた。
「ロシアではもう、教育改革の影響を受けた世代の多くが親になっているの」。2000年代、プーチン政権下で徐々に進められてきたロシアの教育改革では、教育方針や教科書が統一され、ロシアの偉大さを伝える愛国教育が徹底された。反体制的な思想、リベラルな価値観への弾圧が強まり、教師・生徒への監視が強化されているという。
「彼らは被害者だと思う。(教育改革の影響で)物事の本質を見極めたり、情報を体系的に理解する力などが意図的に奪われていると感じる。だから自分でものを考える教育を受けた人たちは、外へ出ていくの。ロシアでは単純労働で働ける人だけが求められているみたい」
ターニャの息子の小学校では、その後、監督官庁が衛生基準と規則を遵守するように指示を出したので、校長はようやく学校の予算でドアと便座をつけた。「校長がバカだと証明するためだけに、自分がいったいどれだけの時間を使わなければいけなかったのかと思うと腹が立つ。でも結局、学校の至るところに愛国教育とプロパガンダがあふれていたの」
教科書や、子どもたちが学校の外で行事に参加するときに着せられたベストにまで、(プーチン政権の与党である)「統一ロシア」という政党の名前が書かれていた。ついにターニャは息子を転校させたのだが、それでも状況は似たようなものだった。それで、息子がロシアの学校で小学2年生の時、学校をやめて家で勉強することにした。勉強はターニャや、オンラインで先生について進めた。そして子どもを再び学校に通わせるために、外に出ようと考えたのだという。
「あなたの身の回りで、意見を言うのは難しかった? もしロシアであなたの味方がいたら、ロシアを出なかったかな」
「私の場合、自分の意見はいつも言ってきたよ。恐れたことはないの。でも、私はいつも1人だった。友だちは1対1ではいつも私の助言を求めていたけど、私のSNSに「いいね」を押すのも怖がっていた。話せる相手はいたけど、彼らは誰もいないところで、声をひそめて私と話すしかなかった。『あなたは鋼の球を持ってる』って、腫れ物を触るみたいにね。私は息子がそういう社会に順応してほしくなかったから、どっちみちロシアを出ていたと思う」
「なにか、ロシアから出ることで、あきらめたものはある? うまくいくかどうか不安はなかった?」と私は聞いた。
「そうだね、私はロシアでよい教育を受け、責任ある地位もいい給料もあった。モスクワで新しい仕事を見つけることは簡単だったと思う。でもむしろ、ゼロから始められることがうれしかったかな」
「移住することは怖くなかった。自分で考えた決断だったから。生活費は3か月分しかなかったし、住む場所や子どもの学校も心配だったけど、思っていたより簡単だった。フィンランド系の子孫として手当も受けられたし、外国人向けのフィンランド語を学んだり、職業訓練やインターンシップもできたし。もっと早くフィンランドに移住していればよかったと思うぐらい。まあでも、自分がいやな場所で過ごした時間が少なければ、フィンランドで自分がどれだけいい生活を送っているのか、実感できなかったとも思うから、これでよかったんだよ」
ターニャは私に、トイレについて小学校や監督官庁に提出した申し入れ書や、保護者たちと交わしたSNSのメッセージ、ターニャの息子の学校のトイレの写真や、ロシアの地方の町のトイレ事情を知らせるSNSなど、これまでの膨大なやりとりや資料を見せてくれた。私はため息をついた。仕事と家事と育児をしながら、1人でこれをやりきったなんてすごい。
「ね、これで、どれだけ私がここで幸せか分かるでしょ。もう誰ともやり合いたくないの。役所や職場や保護者同士とかで消耗したくなかった。はあー、今は、『あら小鳥がいい声で鳴いてるわ』なんて、エレガントに過ごせるのがうれしいよー」とターニャは笑った。
けれども、実際ターニャは、そんなふうにエレガントに過ごしているだけの人ではなかった。
(連載の文中の肩書や組織、値段や為替レートなどはそれぞれ2025年の取材時点のものです)
第2回後編は12/9(火)公開予定です。
記事が続きます
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)