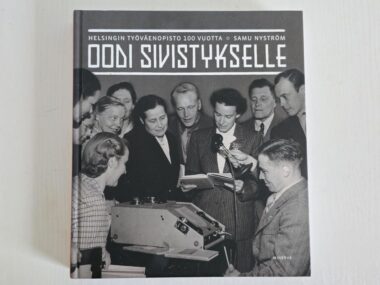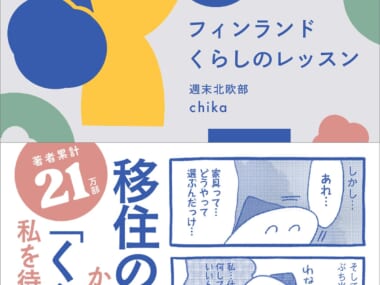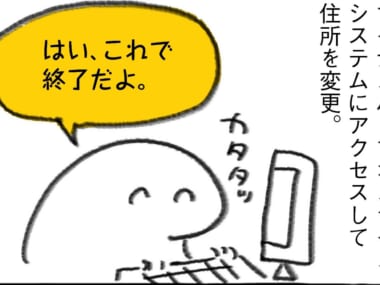2025.11.25
わが子の小学校の「愛国教育」をきっかけにロシアを出てフィンランドへ来たシングルマザー(第2回 前編)
100年の歴史をもつこの場所で、元新聞記者の堀内京子さんはフィンランド語の教室に通いはじめました。
そこで出会ったのは、いろいろな国からそれぞれの理由で、この街へ来ることになったクラスメイトたち。
生まれ育った国を出る決断の背景には、どのような物語があるのでしょうか。
「ほぼ全員が(フィンランドの)外国人」という教室で交差した、ひとりひとりのライフヒストリーを紹介するルポ連載です。
第1回前編はこちら。
第2回 生活費3ヶ月分だけを持ってフィンランドへ。今もSNSで声を上げて闘うロシア人のターニャ(前編)
フィンランドにどれだけ住むかも分からないのに、51歳でフィンランド語の勉強を始めた。頸椎を痛めて足がしびれ、目もかすむ。むかし読んだ新聞記事が頭をかすめる。
「……趣味の範囲内ならいいと思います。でも50代を過ぎてから新しい語学を身につけ、仕事で使えるレベルになるということは想定できませんね。大学で学んでいたり、20~30代で高度なレベルまでいったりしたものを再び伸ばすのなら別ですが、全く新たに何かを始めても、非常に低いレベルにしかいかないでしょう。ほとんど時間とお金の無駄になると思います」(2020年12月17日付 朝日新聞デジタル)
「ヘルシンキ労働者学校」のクラスに通いながら、いままさに自分は、大切な時間とお金を無駄にしているんじゃないかという思いが、毎日よぎった。

勉強を始めて半年たったころ、フィンランド語で即興劇をするという無料のクラスに出て、女優の原日出子似のロシア人生徒のターニャに出会った。
先生が「誰かが言葉に詰まったときは、他の人はすぐに「ブラボー!」って拍手喝采してね。言いよどんだり、分からなくなっちゃった人は、『おほほ、みんな、ありがとう~』って、胸をはってカーテンコールみたいに堂々と喝采を受けること」と説明した。真っ先に言い間違えて「ブラボー!」に囲まれたターニャは、人懐っこい笑顔を見せた。ブラボーはあちこちで起きて、そのうち誰も気にしなくなり、気がつけばみんなでアドリブの劇をやっていた。授業のあとは口も滑らかになり、すっかり打ち解けた気分になった。たまたま帰る方向が同じだったターニャと、一緒にソルナイネン駅まで歩いた。
「私、今日初めてフィンランド語を使えた気がするよ! 家では子どもとずっと日本語で話してるから……」
「キョーコは夫さんがフィンランド人なの?」「ううん、ひとり親。子どもは8歳と14歳」
「私も息子が16歳」
「そっか、大変だね。ターニャはフィンランドに来てどのぐらい?」
「3年前。だけどフィンランド語の勉強はしばらく休んでいたの。がんが見つかって、手術したから」
「それはショックだったでしょうね」
「ううん全然。『ああよかった!』って思った、ふふふ」
「え。どうして」
「だって、私はもうロシアを出てたから。今でよかったって思って」
「なんでそんなにロシアを出たかったの?」
「息子を、プロパガンダばかりの学校に行かせたくなかったからね。大学にも自由がなくなって優秀な教授たちはどんどん国を離れて、このままロシアで勉強しても未来がないんじゃないかと思って。あとね、」
と彼女は大きな笑顔になって「私もシングルマザーだよ!」と言った。そんな嬉しそうに打ち明ける人、初めて会った。
記事が続きます
ターニャはいま52歳。それまでの人生で2回、ロシアを出ようと考えたそうだ。最初は高校卒業したとき。ロシアからフィンランドに行こうと考えた。けれど父親が、「自分の生まれた国(ソ連)を捨てて行くなら、お前は祖国の裏切り者だ!」と言い、祖母も「そんな話は論外だ!」と反対した。「従順な娘だったので、父や祖母の言う通りに従った」。
2度目は、1人で2歳の子どもを育てながら働いていたときだ。そのときは、フィンランド国立公文書館に祖母の出生証明書を請求し、元フィンランド国民の子孫として滞在許可を申請しようとした。けれども結局、実行しきれなかった。
「フィンランドに20年住んでいる知り合いのロシア人に相談してみたら、『2歳の息子を連れて、頼る人もなく1人でフィンランドでやっていけるはずがない。薬局に行くこともできないだろうね。子どもを預けられる人もいなくて、働けなくなるよ』と言われて、ひるんじゃった。わたしはそのとき37歳で、自分の気持ちを聞くとか、自分を信じるっていうことができなかったんだね。他人の意見に左右されてた」
少し話は逸れるが、ヘルシンキに住んでみて驚いたことの一つが、ロシアの存在感だった。日本がロシアの東端に国境を持つが、フィンランドは反対側、ロシアの西端に1300キロもの陸の国境を持つ。そしてそれ以上に、歴史的な関係が深い。
1917年にフィンランドが独立するまで、ロシア領(その前はスウエーデン領)だったこと、ロシア領のときも、フィンランド語や固有の法律を持つことを認められていたこと、そして第二次世界大戦後に、ロシアに土地の一部を割譲したことで、もとはフィンランド人だった人とその子孫たちがロシアに住んでいること。ターニャの祖母は、その父が移住したロシアに呼び寄せられたが、仕事や勉強、結婚などで人の行き来があり、家族の誰かが関係する人が双方にいるということだ。
ウクライナ戦争前は、ヘルシンキと古都サンクトペテルブルグを結ぶ電車が一日4往復走り、わずか3時間半の近さだった。戦争が始まった後もかなり長い間、国境は開いたままで、人々は車でも行き来ができていた(のちに、ロシア側から”移民”が送り込まれる事態になり、国境は閉鎖された)。ロシア語を第一言語とする住民は戦争前から一定数が住んでいて、トラムの中でロシア語を聞くこともよくあった。
記事が続きます
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)