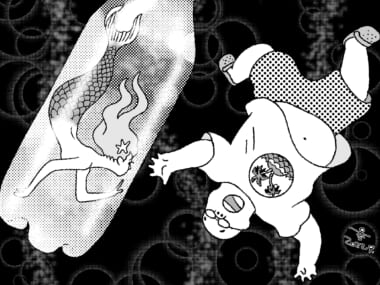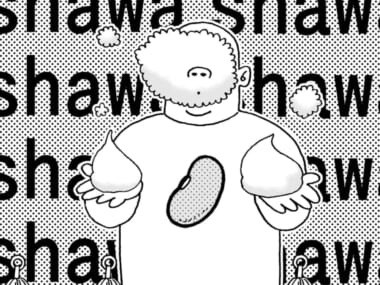2022.10.23
母親がいない寂しさも、極貧な家庭に生を受けた境遇も、お湯に溶けて消えてしまえばいい
ドラマ化もされた『死にたい夜にかぎって』で鮮烈デビュー。『クラスメイトの女子、全員好きでした』をふくむ3か月連続エッセイ刊行など、作家としての夢をかなえた著者が、いま思うのは「いい感じのおじさん」になりたいということ。これまでまったくその分野には興味がなかったのに、ひょんなことから健康と美容に目覚め……。
前回は、洗顔、化粧水、に続きフェイスパックに手を出してみたら、なぜか幼きころの父との思い出が頭に浮かんだ著者。
今回もまた幼少期の父との思い出から、美容と健康に大切な「お風呂」について改めて考えてみたようです。
(イラスト/山田参助)
第7回 お風呂とは「死」に一番近い場所と見つけたり
健康と美容に関する見聞を広めていくと、遅かれ早かれ〝お風呂の大切さ〟に行き着くわけである。
あたたかいお湯につかることで血液の循環が活性化され、心身共にリフレッシュ。ひいては美肌効果や日々の快眠にも繋がるらしい。
なるほど、確かに道理は通っている。しかし、いくら理屈ではわかっていても〝お風呂に入る〟という行為が、それほど素敵なことだとはどうしても思えない。入るのが億劫だとかそういう類の話ではない。だって、私にとってのお風呂とは、常に「死に一番近い場所」だったのだから。
幼少期、「一人前の男なら、風呂ぐらいひとりで入らなあかんぞ」という親父の鶴の一声で、三歳にして、ひとりでお風呂に入ることを義務付けられた。
シャンプーとリンスの違い、お湯と水の出し方、お風呂から上がるときの作法などを乱暴にレクチャーされ、「簡単やろ? ほれ、あとは自分でやってみい」と風呂場に放置された孤独な三歳児。
それは「修行」という名を借りた立派な「育児放棄」であったが、私の心の中では、悲しみの感情より、自分だけの秘密の場所を手に入れたという喜びのほうがはるかに勝っていた。
廊下をミシミシと軋ませて歩く親父の偉そうな足音が遠くなったのを確認し、私は風呂場の中で大はしゃぎ。DV親父の暴力もここには届かない。あたたかい湯船に肩までつかってしまえば、母親がいない寂しさも、極貧な家庭に生を受けた境遇も、その全てがお湯に溶けて消えていくような気がした。
それが束の間の気休めだと子供ながらに理解していても、風呂場は私にとっての天国に他ならなかった。
記事が続きます

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)