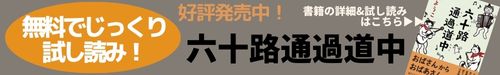
2024.6.12
お弁当箱の蓋を開ける瞬間
当記事は公開終了しました。
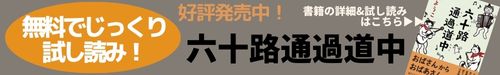
2024.6.12
当記事は公開終了しました。
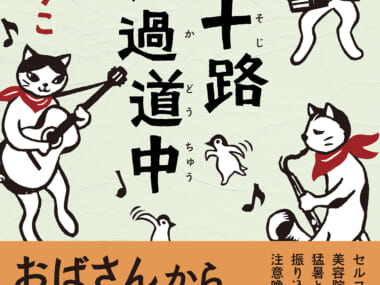
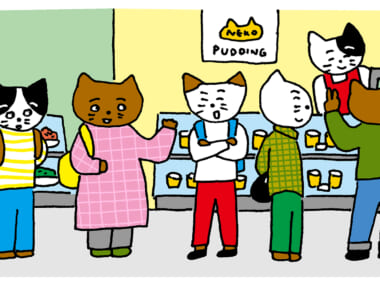
ちゃぶ台ぐるぐる

わたしとふたりで旅をする 京都・大阪・神戸 西の都のものがたり
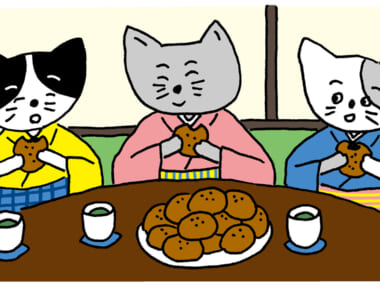
ちゃぶ台ぐるぐる

ちゃぶ台ぐるぐる

ちゃぶ台ぐるぐる

2025/11/26

2025/10/24

2025/11/26

2025/11/6

台所で詠う

平成しくじり男

ヘルシンキ労働者学校——なぜわたしたちは「ボーダー」を越えたのか
