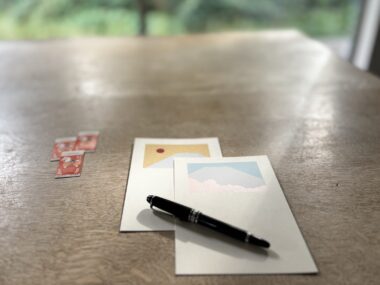2025.10.24
視覚障害者と晴眼者が一緒に美術鑑賞をして「聴く演劇」作品を作る。ユニークなワークショップの狙いとは@江戸東京たてもの園【後編】
記事が続きます
「まっすぐ」と「ブラブラ」の両方を一緒に体験したい
江戸東京たてもの園で3チームが散策する建物は、現代の私たちの生活感と離れすぎない場所を選んだ。聴く演劇をつくるワークショップは、「散策」「創作」「上演」という3つのパートに分かれている。そのうち「散策」は、林さんたちが長年行っている「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」のやり方と同様だ。ここまでなら、参加者それぞれがバラバラな感想を持つことを肯定されて解散することができる。
しかし「創作」が加わると、みんなから出された感想や意見を取捨選択する必要に迫られる。自分と他者の意見がつながる喜びもあるが、違和感を抑えて進行することもあるかもしれない。また、鑑賞で見つけた具体的な事実から、フィクションも交えた創作に向かう際には飛躍(ジャンプ)が必要である。創作にマニュアルはなく、林さんたちも試行錯誤している。
参考書籍から建物の解説や当時住んでいた人のインタビューなどを抜粋することもできるが、「それでは正しいテキストを僕らの声でなぞっているにすぎない」と林さん。たてもの園にはたくさんの建物があり、一人で見たら、1軒1軒サッと見て回ることに終始しそうでもあった。「このワークショップでは、鑑賞という行為が時間的にも幅があるものになるし、音声作品をどこで聞くのかによって空間的な幅も広がると思います」。

「そもそも迷いたいんですよ。作品の周りに広場をつくって、そこをみんなでうろうろするようなことなんです」と林さんは続ける。
「例えば、買うものが決まっていてまっすぐ買いに行くだけじゃなくて、ブラブラしながらその場にいるっていう、その両方をやりたいんです。スタート地点から目的地まで最短距離が良いとなると、途中のプロセスがほぼ生まれない。
でもものを見る行為には、実はたくさんのプロセスがあって、人によって全然違うものを見たり聞いたり、みんなうろうろしながら別々の経験を生み出している。多数派である目の見える人の鑑賞が正しいのではなく、いろいろなやり方でたどり着けるはずだと。
これを参加者の皆さんで体験しながら、参加してない人にも伝えていきたいです。演劇って、その場に集まった人にも、何百年後のお客さんにも伝わるものをつくれますよね。そんな演劇の力を借りて、社会における価値観を少しずつ変えていければいいなと思います」。
一方で、触察模型やガイドツアーなど、基本的なアクセシビリティも大切だという。当事者の声を聞きながら裾野を広げていくことが重要だろう。
小さなケアを積み重ねていけば、一緒に迷うこともまた楽しい
「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」のスタッフは現在、視覚障害者を含む11名で運営されている。美術に限らず、このような建築、あるいは映画・映像などにもジャンルを広げている。長らくケアとアートにまつわるプログラムに携わっている林さんに、ケアとアートのあり方について思うところを尋ねた。
「今回のワークショップでも小さなケアはたくさんありました。前半の散策のプロセスでは、みんなで移動したり、情報を共有するために目の見える人が見えない人に腕を貸して目的のところまで移動したり、建物の形状を言葉で描写したり、歴史的な背景を説明したりと。
でも鑑賞とか創作の現場では『自分たちは何を見ているんだろう?』とか『どんな作品を作ろうか?』とか答えのない状態でうろうろ迷うこと自体が大切なんですよね。
迷っている場では、見える人が説明しようとして発した言葉をもはや誰も必要としていなくて不発に終わったり、でもそういう意味を失った言葉こそが創作の種になったりもして。小さなケアを積み重ねて目的のない会話ができるようになってやっと創作の現場ができると思うんです。
Cチームの作品作りでは最終的に小出邸の和室で台本とアドリブ半々で会話することになりました。アドリブができるのは小さなケアを重ねて自由に振る舞える環境が整っていたからだと思います。
その頃には目の見える人も見えない人も、スタッフである私も含めてみんなちゃんと迷っていましたよね。必要なものが揃った結果、自由に迷うことができるようになっている。そんなふうにケアの意味が薄れていくのがアートの創作現場におけるケアのあり方なのかなと思います」。
つまり「鑑賞や創作の現場でのケアとは迷うためにあるのだ」と林さんは語る。「マイノリティとマジョリティが関わる鑑賞とか創作の現場では、迷うこと自体を奪われてしまうことが往々にしてあるので、そうではなくて小さなケアを丁寧に積み重ねて迷う場を作る、というのが理想だと思っています」。
確かに、上演ではひと言のセリフであっても、迷いも含めた創作プロセスを経て演じたことに手応えを感じた人もいただろうし、実感を得られたことで作品に近づいたという人もいただろう。ワークショップを行う側がうんちくを披露するのではなく、問いによって会話の推進力をつくるという技術も興味深い。

今、目の前にあるものと、過去に起きたことを行き来し、心を動かされる「鑑賞の眼」が、その人の人生を変えることもあるかもしれない。
美術館や劇場で作品を見るだけでなく、作品を見る行き帰りに光や風、すれ違う人などを感じることも「鑑賞をつくる」ことにつながりそうだ。アクセシビリティためのアイデアもいろいろ考えられるような気がしてきた。
次回連載15回は11月14日公開予定です
記事が続きます
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)