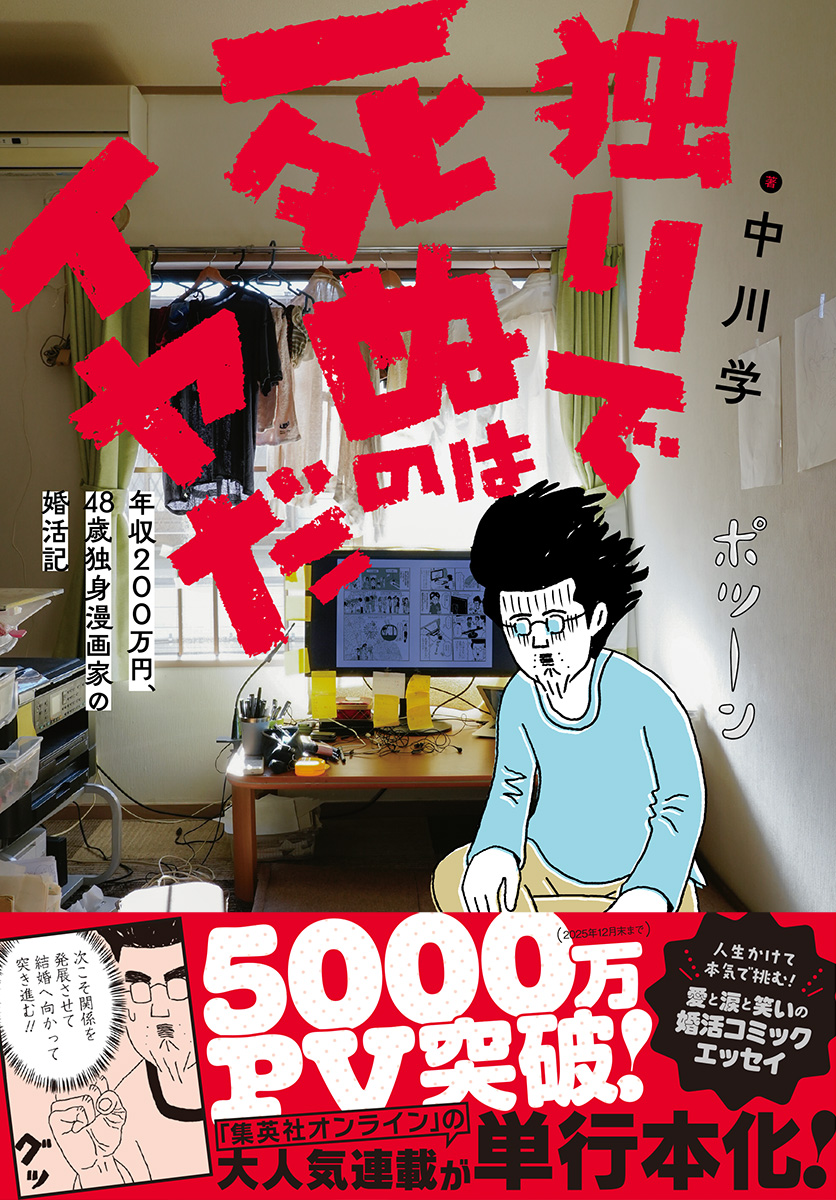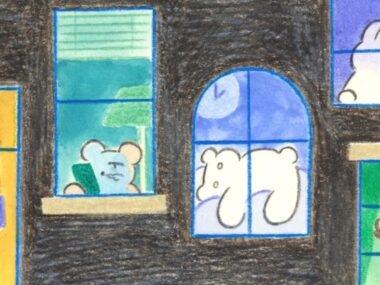2025.10.24
視覚障害者と晴眼者が一緒に美術鑑賞をして「聴く演劇」作品を作る。ユニークなワークショップの狙いとは@江戸東京たてもの園【後編】
これらには、視覚・聴覚障害のある人とない人がともに楽しむ鑑賞会や、認知症のある高齢者のための鑑賞プログラムなど、さまざまな形があります。
また、現在はアーティストがケアにまつわる社会課題にコミットするアートプロジェクトも増えつつあります。
アートとケアはどんな協働ができるか、アートは人々に何をもたらすのか。
あるいはケアの中で生まれるクリエイティビティについて――。
高齢の母を自宅で介護する筆者が、多様なプロジェクトの取材や関係者インタビューを通してケアとアートの可能性を考えます。
前編に続き、任意団体の「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」が江戸東京たてもの園で行った取り組みを紹介。主催者の林建太さんのインタビューを通して、美術鑑賞の在り方について考えます。
記事が続きます
見える人も見えない人も個々にバラバラな見方をつくっている
前編で紹介したワークショップの後日、代表の林建太さんに「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」を立ち上げた経緯をうかがった。
「20代の頃から介護福祉士として在宅ヘルパーの仕事をしたり障害者の方達と関わることが多くありました。ある日、視覚に障害のある友人と美術館に行ったんですね。僕は、絵画に描かれたモチーフや色や大きさ、構図など作品についての情報をできるだけ客観的に伝えたつもりだったのですが、何か面白くないんだよね、という反応が返ってきたんです。
もしかすると美術を見る楽しさって目の見える人にとっての客観性じゃないところにもあるのかもしれない。
それじゃあ、目の見える人、見えない人、双方にとっての美術鑑賞の面白さとはなんだろうかと。そのような問いについてさまざまな人と考えたいと思い、複数人で話し合いながら美術を見るワークショップを企画するようになりました」。

「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」では、作品の図像と視覚障害者がイメージする図像を一致させることを目的としていない。答え合わせではないのだ。
長年、さまざまな場所でワークショップを行う中で、見える人も見えない人も、ものの見方は個々に違っていて、それぞれのやり方で鑑賞していることに気づいたからだという。
では、目の見えない人には、どんな鑑賞の仕方があるのだろうか。
「参加者の言葉を聞きながら、頭の中で作者のように絵を描いていくという人もいますし、自分の言葉で作品について話せるようになると鑑賞したと思えるという人もいます」。
見える人でも、例えば「赤」といっても同じ「赤」には見えていない。だとすれば、美術鑑賞も「つくる」ものだと納得がいく。

「美術鑑賞の経験がひとりひとり違うのだとしたら、ミュージアムで、美術作品にアクセスできない人に用意されている音声に“ガイド”という機能しかないのは、入口から出口まで1種類しかないようで不自然だと思います。
使用者が『視覚障害者』という立場や枠にはめられていくように感じるという人もいます。情報の意味や重要性があらかじめ決められていて、あなたが説明されるべき情報なんですよ、と押し付けられているみたいだと。それは自由じゃないですよね」。
そのような当事者の声を聞き、作品についておしゃべりする場をつくってきた林さんだが、そこで生まれた会話がその場限りで消えてしまうことを残念に思っていた。
音声ガイドとは違う、作品の鑑賞方法を模索する
その場にいない人にも伝わる形として音声に記録したい。そんなとき俳優の大石将弘さんもまた、新たな演劇を模索する中で「場所」から発想して「音や声の演劇」をつくるワークショップを行っていることを知る。
「大石さんには、一つの空間で同じものを見ていてもみんな違う経験をしているという話がすんなり通じそうだと思い、声をかけました」。
こうして「きくたびプロジェクト」(前編参照)が始まった。横浜美術館のコレクション展で“音声ガイドじゃない音声”を目指して、作品を見ながら聞く音声作品を15本ほど制作。YouTubeにアップして、誰でもアクセスできるようにした。
そのときのアンケートには「今まで触察図や視覚障害者向けの説明を聞いても、自分は絵画を鑑賞できなかったが、今日は鑑賞できた感じがする。詩や物語という形の音声のおかげで、触れることができない作品の味わいや、奥行きも楽しむことができた」という嬉しい声があった。「解説されるのではなく、さらに謎が深まる感じ。新しい見方が次々出てくる感じ、たまらなかったです」という反応にも手応えを感じた。

「美術館におけるアクセシビリティって、作品に続く最短の一本道があって、みんながその道を歩けるようにするという考え方が多くあると思うんですけど、僕はちょっと違っていて。作品の周りにみんなが何をしてもよい広場があるみたいな、近づいても良いし、遠くから眺めても良いし、何をしても良い状態もアクセシビリティには必要だと思っているんです」と林さんは語る。
「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」では、視覚障害者と晴眼者がコンビでナビゲーターを務めている。鑑賞のサポートをしたり、話が一つの方向に固まりそうになってきたら新たな問いを投げかけたりする役割だ。あるときナビゲーターの一人、浦野盛光さんが、大石さんに「ものを演じるとき、どうやってものの気持ちになるんですか」と質問した。話しているうちに大石さんは、一般の参加者でも音声演劇をつくれるのではないかと思い始めたという。そのことが「聴く演劇」をつくるワークショップを開発するきっかけとなった。
記事が続きます
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)