2025.3.28
見えること、見えないこと。感覚の違いを超えて生まれる新たな表現とは?【後編】<感覚の点P>展@東京都渋谷公園通りギャラリー
記事が続きます
訪れた人が何かを持ち帰り、また誰かと交換する
〈感覚の点P〉展では、光島さんと今村さんの感覚の交換にとどまらず、多様な他者が参加することも特徴だ。もともとひとりで作品をつくることが好きだった今村さんも、他者に開く可能性を感じるようになった。
「見に来てくださった人が、何かを持ち帰ってくれて、ちょっとした変化があったりすれば嬉しいです。僕と光島さんとの直接のやり取りじゃなくてもいいと思うし、見に来た方が別の誰かとの関係性からちょっとした影響があったり、その人の周りの人との間でささやかな何かが起こったりすることがあれば理想的かな、と思っています」。

2月16日には作曲家の野村誠さんが《プリペアド・トイピアノ》を演奏するライブが2回行われた。鍵盤ハーモニカの名手でもある野村さんは、プロもアマチュアも一緒に音楽とアートのワークショップを行うなど、国内外で多彩な活動を行っている。

野村さんは演奏前にどの鍵盤がどの仕掛けにつながっているかを確認したうえで、感覚にしたがって即興で演奏した。バケツの内側を叩く音がリズムを刻んだり、天井の上の方のライトが星座のように光ったり、スタンドライトが座る女性を横から照らしたり。あちらこちらで存在を証明するように何かが生まれては消える。
音の聴こえ方の違いが感じられるので、演奏会の参加者は歩き回ってもいい。
また、マイクで拾った音を振動に変換するインターフェイス《タッチ・ザ・サウンド・ピクニック》を借りて鑑賞する人もいた。これは聴覚障害の有無にかかわらず音楽が楽しめる「共遊楽器」を研究・開発する金箱淳一さんによるものだ。

ふと、野村さんが光島さんの作品の前に移動し、指や鉛筆を使って音を奏で始めた。光島さんの作品はやはり音楽的でもある。

野村さんが奏でる音楽は、終わるかなと思うとまた波が生まれて続いていく。演奏家としてだけではなく、コンダクター(指揮者)にも振付家にもなって《プリペアド・トイピアノ》のある空間をいきいきと楽しんでいた。野村さんが参加したことで、関わる人によって展示空間が変わることにあらためて気づく。
余白や余韻が残る時空間。ここではないどこかを思う
ところで、このような参加型プロジェクトでは、感覚や言葉が集積されていくことが多いものだが、今村さんと光島さんがつくりだす場には余白や余韻が不思議と感じられる。なぜだろうか。
学芸員の門さんはこれを「引き算の表現」と称した。
「今村さんは、空間に対して影響を及ぼし、それを見た人の記憶や感覚を引き出す作品制作を行っています。そのため、ここではないどこかが必ずある。そのどこかで何かがコツンと音を立てるような、見えないけれども別の場所で起きているものごとを想起させます。強いメッセージではないけれども、小石の波紋のように多くの人に響く。それに対し、光島さんは直接的にふれる作品をつくっていますが、実はふれているもの以外の多くの情報をそこに落とし込んでいます」。
ここではないどこかを思う。確かに光島さんの作品にもそれはある。光島さんは今回、背伸びをしても届かない高い位置にも作品を設置した。美術館では、車椅子や子どもの目線に合わせて展示作品の位置を下げることがある。同様に、今回の展示でも低い位置にも作品があるが、光島さんはすべての作品に手が届くようにはしなかった。世界にはふれることができないものがたくさんあり、人間には想像する力があるからだ。

木は空へ、根は土の中へと伸びている。その誰にも見えない、ふれないところを想像してみよう。自分が生きてきた時間を振り返り、新たな意味をつくる。そうした思考や行為は、目が見えるか見えないかという二項対立を超えたものだ。

取材を終えて、やはりこれはアーティストとアーティストの対話、そこから派生する鑑賞者や参加者の広がりが主眼にあるプロジェクトだったのだなと思う。光島さんが、今村さんとの出会いを糧にして、立体作品から、空間芸術へと表現を拡張したことにも大きな意味がある。
こうしたことをケアの話に引き寄せると、「感覚の交換」という概念は、同じことを一緒にしていても感じ方がそれぞれ違うこと、相手にはどんなふうに世界が見えているのか想像し、尊重することの大切さを教えてくれている。
また、「ふれる」という言葉は、今ここにある物や人に直接的に手が届く状態を指すものだと思ってきたが、人間には、亡き人の写真や墓碑銘に思わずふれる、ということがある。それは、そこにはいない誰か、ここではないどこかに向けて間接的に祈る状態だといえる。ケアにもまた、物や人に対する直接的な行為ばかりではなく、遠くから心を寄せるという間接的な行為もありうる。
それはアートにおいても、物質的な作品そのものを直接的に鑑賞することと、作品を媒介として何かを思うこと、その双方の働きがある、ということに重ねて考えられるのではないか。私自身の〈感覚の点P〉は、今そんなところにある。
今村遼佑×光島貴之 感覚をめぐるリサーチ・プロジェクト〈感覚の点P〉展
会場:東京都渋谷公園通りギャラリー
(東京都渋谷区神南1-19-8 渋谷区立勤労福祉会館1F)
会期:2025年2月15日(土) ~ 5月11日(日)
開館時間:11時~19時
休館日:月曜日 (2月24日、5月5日は開館)、2月25日、5月7日
入場料:無料
公式ホームページはこちらから
次回連載第3回は4月11日(金)公開予定です。
記事が続きます
関連記事
-
- 連載
- 3/22

真夜中のパリから、夜明けの東京へ
自分はこの先、ずっと悲しい物語の主人公でいなければならないのだろうか【猫沢エミ×小林孝延・往復書簡8】
-
- 連載
- 3/17

台所で詠う
ずっとカーネーションがきらいだった【第1回 社会が要求する女というもの】
-
- 連載
- 3/18

もう一度、君の声が聞けたなら
妻が逝った。オレ、もう笑えないかもしれない 第1話 さよなら、タマちゃん
-
- 連載
- 3/11

海をわたる言葉~翻訳家ふたりの往復書簡
私は一体、なんのために介護なんてしているのだろう 第7便 先の見えない老親の介護
-
- 連載
- 3/12
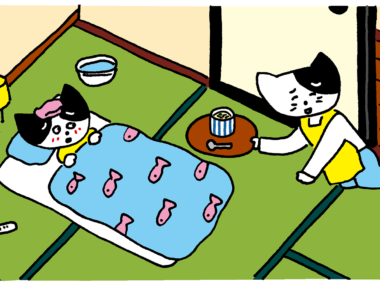
ちゃぶ台ぐるぐる
風邪をひいたら小田巻蒸し
-
- 連載
- 3/15

西の味、東の味。
家庭料理と違う……? 日本料理の世界における「普通の醤油」とは
新刊紹介
-

真夜中のパリから夜明けの東京へ
2025/11/26
-

歩いて旅する、ひとり京都
2025/10/24
-

粋 北の富士勝昭が遺した言葉と時代
2025/11/26
-

ちゃぶ台ぐるぐる
2025/11/6
よみタイ新着記事
-
- 連載
- 1/15

平成しくじり男
大ヒットアニメ『天気の子』は「池袋素人童貞モノ」の歴史を継承している?!【平成しくじり男 第6回】
-
- 連載
- 1/13

ヘルシンキ労働者学校——なぜわたしたちは「ボーダー」を越えたのか
40歳でも、小さな子どもが2人いても、フィンランドでは外国人にも機会がある(第3回 後編)
-
- 特集
- 1/11

語らないという選択――レディー・ガガが引き受けたもの【社会に言葉の一石を。もの言う女性アーティスト特集 第4回】
-
- 連載
- 1/10

人生競馬場
「成り上がり」と「アイドル的人気」で競馬界を塗り替えたオグリキャップ【人生競馬場 第6回】
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)


