2025.11.1
10年浪人も当たり前?! 京大卒の作家が語る「小説家デビュー」と「大学受験」の重要な共通点
「合格」にはどれくらいの筆力がいるの?
小説が大学受験と大きく違うのは、明確な「正解」がないことです。正解がないどころか選考する側が間違っている場合さえありえるので、「プロの小説家として十分通用する力はあるのに新人賞を受賞できない」というケースは実はめずらしくありません。この理不尽さは書き手も読み手も不完全であることから逃れられない表現の世界特有のものであり、同時におもしろさ・奥深さでもあります。
とはいえ「実力はあるのにデビューできない」なんて我慢ならない!という方も多いでしょう。乱暴に言えば結局はくじ引きで「あたり」を引いたひとがデビューできる世界ですが、逆を言えば「あたり」がでるまでくじを引き続けたひとがデビューしているわけです。
新人賞対策とは、「あたり」を引く確率を高める戦略を立てることです。試行回数を増やす、というのは「あたり」を引く戦略として最も単純で効果があるもので、本気で作家になりたいひとは絶対にやるべき行動です。では他に何ができるでしょうか? まず当然ですが、小説を上手く書けるようになりましょう。ここでの上手さですが、任意の新人賞の2次選考や3次選考を通過できるだけの筆力があれば、もうあとは運次第と思って大丈夫です。
新人賞攻略本にはよく「3次選考と最終候補の違い」とか「最終候補と受賞作との違い」とかを解説していますが、私に言わせればそんなもんありません。連中が言いたいだけの妄言です。たとえばあなたが「きのこの山」と「たけのこの里」がどっちが優れているかというディベートに参加することになったとします。あなたはどちらにもさして興味はないのですが、「きのこの山」を推さねばならなくなりました。「たけのこの里」勢があの手この手で自身の優位を主張してくるので、あなたも負けじと「きのこの山」の長所を捻出し、短所をうまく「個性」と言い換えて応戦します。このやりとりを繰り返していると、あなたはさっきまで興味がなかったはずの「きのこの山」の美徳を細部まで説明できるようになっています。新人賞攻略本が説く「受賞作と落選作の違い」はそういうプロセスで出てくる謎理論でしかありません。しっかりと書かれた作品は、かならずどこかの誰かに刺さります。作家が信じるべきはそれに尽きます。
だいたい個性やらなにやら、そんなもんはデビュー済みの作家の課題でもあるわけですし、切り口次第でどんな小説にも言えることです。それなりの水準でまとまっている作品は読み手が変われば評価が変わるので、指摘を真に受けるより、自作を肯定的に評価してくれる場所を探した方が有意義です。
ただ、自作を使い回すより新作を書いて応募するようにしてください。「まぐれで1回だけ予選を通過した」と「安定して予選を通過できる」は筆力に差があるので、自分の現在地を知るために、できるだけ新作で応募するようにしましょう。
応募数500作以下の賞を狙え!
では1次選考も通らない場合はどうでしょう? その場合は応募する賞やジャンルを変えてみてください。まず考えられるのはカテゴリエラーです。そして自作が予選を通過する賞やジャンルがどこなのかを色々応募しながら見つけましょう。
また純文学みたいに応募数が1000作を超える新人賞で予選通過できない場合、別ジャンルでもいいので応募数500作以下の賞に応募してみてください。冷静に考えて、1000作以上の小説を人間が選考し、一切のミスが起こらないなんて事の方があり得ません。応募数が多くなると取りこぼしは必ず起きます。なので取りこぼしが少しでも起こりにくいところに原稿を持っていくと自分の現状の筆力がわかります。とりあえず、まずは自分の筆力を客観的に確認できる成果を出せるか試してみてください。
また、一定の筆力があればあとは運であることを考えれば「応募数」は大事です。どんな賞でも箸にも棒にもかからない「記念受験」が9割あるとすれば、「あたり」を引く可能性があるのは残りの1割。応募数2000作の新人賞だとこのくじ引きを引くのは200人ですが、応募数500作の章では50人です。なんだか当たりそうな数です。電卓を叩いてみましょう。
新人賞の記念受験が9割、受賞者が毎年1人だと仮定して計算すれば、応募数2000作の賞に10年応募して受賞できる確率は約4.9%、応募数500作の賞を受賞できる確率は約18.3%になります。なるほど、1年に複数の賞に応募できることを考えれば、作家チャレンジを10年やるのはそこまで悪いギャンブルでもない気もしますし、10浪で合格も妥当なラインっぽいですね。
受賞者が誇れる賞であって欲しい
本稿では作家のよく訓練された受験ソルジャーとしての一面を紹介させていただきました。もっと言えば受験先選びは「偏差値」だけでなく「待遇」も大事なのですが、その話は次の機会があればしたいと思います。
でもやっぱり、作家になるのは大変です。そして「作家であり続ける」ことも大変で、めんどくさいことに両者の大変さは質が異なるものです。デビューに苦労したひともいれば、デビュー後に苦労したひともいるし、両方大変だったひともいます。ちなみに私は新人賞を取らずして「指定校推薦」みたいなデビューをしましたが、それでも自分なりには苦労しましたし、苦労はまだ続いています。
ただ、私は本稿で「高偏差値」と紹介したような新人賞ではない──この文脈では「Fラン」とでも言われるだろう出身であることを微塵も恥じたりはしていません。私を世に出してくれた『たべるのがおそい』(書肆侃侃房)の作品公募も、阿波しらさぎ文学賞も、真摯に作品に向き合ってくださった。私と作品に信頼を寄せ、背中を押してくれた。賞とともに成長するようにキャリアを歩んで来れたのは私にとっていちばんの誇りです。
そして私自身も文学賞の選考をする立場になったいま、受賞者が誇れる賞であってもらいたいと心から思っています。完全ではない私はきっと間違える。間違えるのが運命づけられているからこそ、自分の文学を全力でぶつけるようにして応募作を読んでいます。
最後に私が作家になるためにいちばん費やした研究を紹介します。
私には「個性的な作家は個性的な小説の読み方をする」という持論があります。理系出身ということもあり学生時代から「小説をいかに自然科学として解釈するか」という試みをしてきました。
その研究成果をまとめたのがエッセイ集『理系の読み方 ガチガチの理系出身作家が本気で小説のことを考えてみた』(誠文堂新光社)です。カフカやガルシア=マルケス、ヴァージニア・ウルフを理系的に分析し、円城塔のような「難解」と呼ばれる作品の読み方を提案し、「なぜ解けるか」に着目して現代ミステリの構造を解説しています。
古典文学から国内エンタメもカバーした超絶グレートな創作論でもあります。これを読んでぜひ最強小説パーソンになって新人賞を無双してください!
好評発売中!!
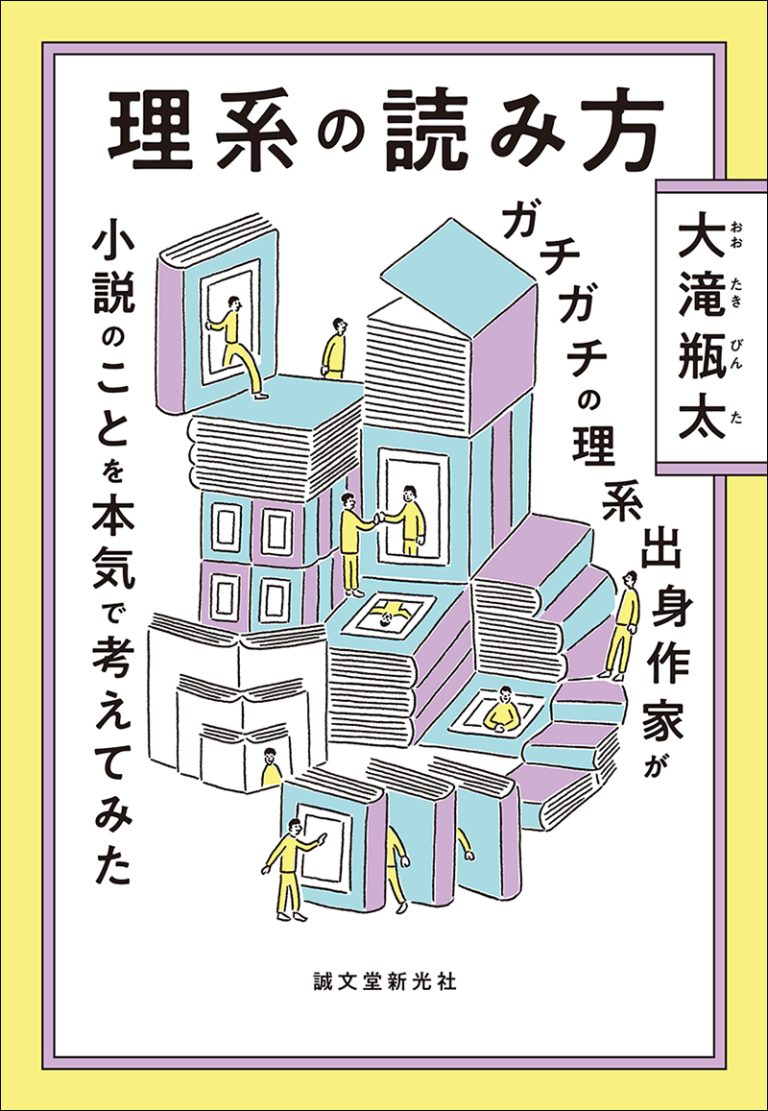
理系のバックグラウンドを持つ作家が誘う、理系的な名作の読み方。知的刺激に満ちた読書エッセイ。
書籍の詳細はこちらから。
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)










