2025.11.1
10年浪人も当たり前?! 京大卒の作家が語る「小説家デビュー」と「大学受験」の重要な共通点
小説家としてデビューするまで「8浪」かかったという大滝さんが、「受験としての新人賞」について綴ってくださいました!
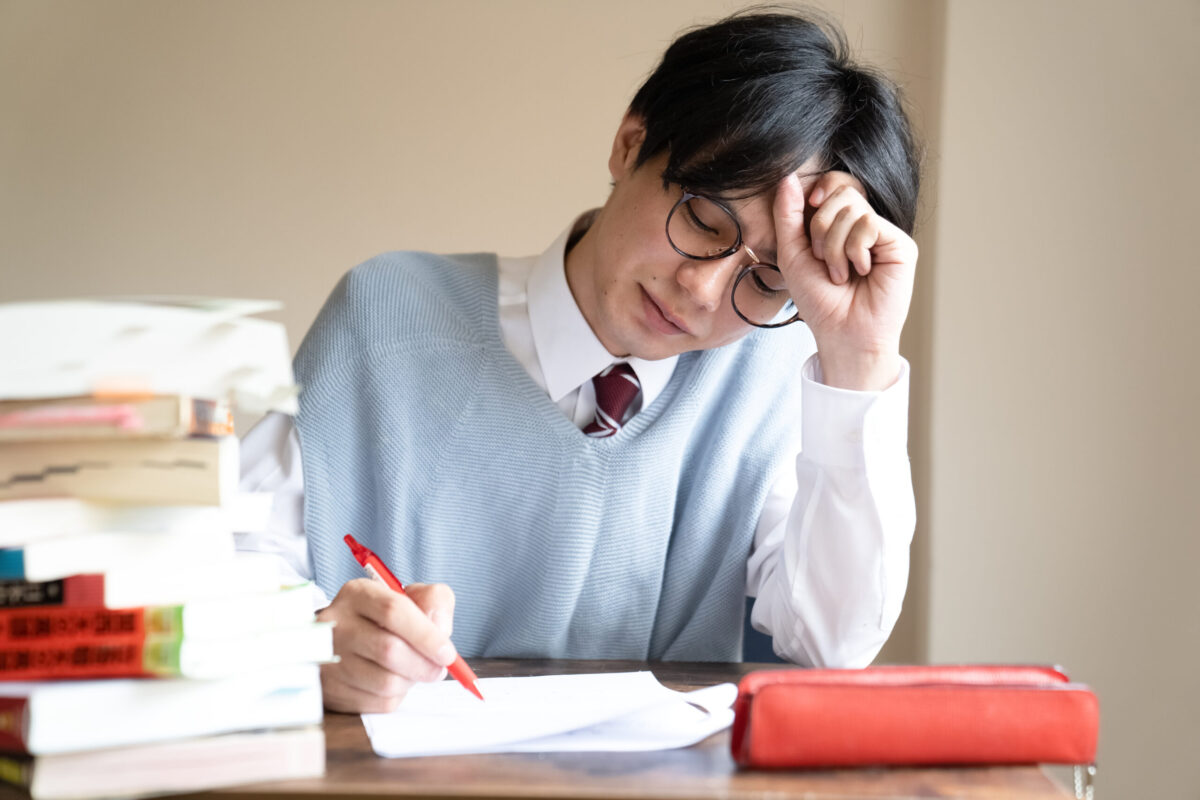
10浪で現役!? おいでよ 新人賞多浪の森
デビューしてもう何年も経つのにまだ新人賞の話をしている恥ずかしい作家がいる。私である。
これがどれくらい恥ずかしいかを作家を目指したことがない皆さんに説明すると、「もう就職したのに大学受験の話を一生くっちゃべってるおっさん」みたいな感じです。「すばる文学賞で最終候補の一歩前までいったことがある!」という話をするのは「東大に10点足らずに落ちた!」とほぼ同じとみていいでしょう。
ところで、皆さんは作家になる方法を知っているでしょうか? たぶんよっぽど興味がない限り知らないと思います。実際に私が作家になってから、知人友人に一番訊かれるのも「作家ってどうやってなるん?」です。
最近では小説投稿サイトやSNSで無双していたらスカウトされるケースや、同人活動の積み重ねでのデビューが増えてきましたが、今でも最もメジャーなルートは「新人賞の受賞」です。いわゆる「作家志望者」の多くはこれを目標に日々創作に励んでいるわけですが、これがけっこう大学受験に似ています。
私自身、新人賞にはじめて応募してから商業デビューするまで8年かかりました。この8年、大学院生をやり、会社員をやり、無職をやり……という感じだったのですが、大学受験多浪界隈のひとびとをインタビューするYouTubeチャンネル『トマホークTomahawk』を見ると、謎に共感してしまうところがあります。8年の浪人生活には何をやったかマジで覚えていない年とかあるし、基本ダラダラしていて、危機感もなく、新人賞に応募すらしない年もありました。それを見兼ねた友だちに尻を叩かれ一念発起した最後の1年でデビューが決まったのですが、それを思い出すと気がつけば頬に涙が伝っていました。
そこで今回は「作家」という仕事をより身近に感じてもらうために、「受験としての新人賞」を紹介します!
科目選択をしよう!
ある日、あなたは突然小説を書き始め、数ヶ月かけて渾身の一作を仕上げました。自作を読み返しながらあなたは自分が天才であることを確信します。これはもう作家にならなければヤバいだろうと脳内の天使と悪魔の意見が一致し、行動を起こすことにします。原稿を持ち込もう。
あなたはググります。あるいはChatGPT に訊いてみます。どうやら小説はマンガとは違って、出版社への持ち込みというのは基本的にないらしい(小説はすぐ読めないからね)。そのかわりとして機能しているのが「新人賞」だとあなたは知ります。いったいどこへ応募すればいいでしょう?
まず「新人賞」ですが、これは公募型文学賞(=プロアマ問わず誰でも応募可能)のなかでも出版社が主催するものとします。公募文学賞はいろんなかたちで開催されています。出版社だけでなく新聞社や地方自治体、非営利団体、文学好きの個人が主催することもあるのですが、当然ながら主催団体が違えば目的も変わってきます。そのなかで商業デビューに注視すると重要になってくるのが「商業誌掲載」と「書籍化」ですが、ここに直結するルートがあるのは出版社主催の賞だけです。地方文学賞などで研鑽を積み、実績を残すことはもちろん書き手にとってプラスにはなりますが、最速で作家になりたいなら出版社主催の「新人賞」を狙いましょう。
その「新人賞」は、毎年50-80程度が稼働しています。ここには純文学・総合エンタメ・SF・ミステリ・歴史・官能・ライトノベルなどさまざまなジャンルが含まれているので、まずは自作と相性の良さそうなフィールドを検討します。ジャンルの検討は受験で言うところの科目選択に似ています。たとえばミステリにはミステリ特有の技法があるように、ジャンル特有のお約束や問題点を押さえて創作するとそれだけでけっこう「読める」作品になったりします。
ここで困ることになるのは「自分の作品がどのジャンルに入るかわからん」というあなたです。ぼくもそういうタイプだったのですが、そういうタイプは純文学に集まる傾向があります。これらは他に比べて定義が曖昧というか、ジャンルの枠に囚われない発想を好意的にとってもらいやすいためじゃないかと、私は考えています。まぁ、小説全体からあらゆるジャンルを引き算していった結果、最後に残るのが純文学という説もありますが……。
文学賞に「偏差値」はあるのか?
ジャンルを絞ったなら、どこの賞に応募するかをもっと詳しく吟味しましょう。応募先はいわば「志望校」。絶対に東大・京大に行きたい、医学部に行きたい、大学生になれるならどこでもいい……大学受験では志望校の選択に「偏差値」が絡んできますが、このような発想は新人賞でもあるのでしょうか?
大沢在昌『売れる作家の全技術 デビューだけで満足してはいけない』(角川文庫)では、「できるだけ偏差値の高い新人賞からデビューすることを目指しましょう」と書いています。この「偏差値の高い新人賞」とは、直木賞作家やベストセラー作家を多く輩出している賞を指し、ミステリなら「江戸川乱歩賞」「横溝正史ミステリ&ホラー大賞」、時代小説なら「松本清張賞」が該当すると大沢氏は述べています。大手商社とか外コンに就職したいなら東大か早慶に行っとけ、みたいな理屈ですね。
本音を言えば「文学賞の偏差値」という概念の存在はわかるっちゃわかるのですが、あまり受け入れたくないものでもあります。
たとえば純文学だと五大文芸誌と呼ばれる「文學界」(文藝春秋)・「群像」(講談社)・「新潮」(新潮社)・「文藝」(河出書房新社)・「すばる」(集英社)が主催する賞が絶対的な「高偏差値」新人賞です。これらの賞を経由せずに純文学の主戦場である五大文芸誌への進出はかなり困難で、そして純文学で最大の影響力を持つ「芥川龍之介賞」の候補作は基本的に五大文芸誌に掲載された作品から選出されます。もちろん、他ジャンルからの転向や文化人の小説家デビューなど例外もありますが、数字で見る限り純文学作家で活躍したいなら「高偏差値の賞(=五大文芸誌の新人賞)」を取らないとかなりキツいと言わざるを得ません。外から見るとなかなか閉鎖的でマッチョな世界観です。
「文学賞の偏差値」という概念を受けいれるのは、こうした構造を肯定することでもあるので、ぼく自身としては気が進まないわけです。しかし最近はWEB文芸や同人活動の活発化がめざましく、これも変わっていくんじゃないかなと期待しています。
だいたい何年「浪人」するの?
上記の新人賞は「高偏差値」というほどですからやはり受賞難易度は高いです。特に紹介した純文学の新人賞の応募数は1500〜2000作程度……というのが私の投稿時代の肌感でしたが、コロナ禍以降は増加傾向にあるようで、いまはだいたい2000作前後で推移しています。
なかでも新潮社主催の「新潮新人賞」は近年応募数がガツンと伸びたという印象で、第56回(2024年開催)は2855作の応募があったとのこと。穴場と言えそうなのは集英社主催の「すばる文学賞」で、ここ数年は1100〜1300作を推移していて、それでも1000作以上きます。
これだけ集まったなかで1位か次点を取らなければデビューできないんですから、はっきり言って無理ゲーです。冷静に考えて、「ハイハイ! この1000人のなかで私が一番小説がうまいです!」と言えるってヤバいですよね。
難関新人賞のエグい倍率ゆえか、新人賞界隈には10年とか20年応募を続けているという猛者がゴロゴロいます。新人賞には「中間発表」というものがあり、選考でいいところまで進んだ作品と作家の名前(あと居住している都道府県)が雑誌で発表されるのですが、そこで「常連さん」を見つけることもあるでしょう。これはこれでハガキ職人的な楽しみがあります。
ちなみに知り合いの同業者に「はじめて新人賞に応募してから商業デビューするまで何年かかったか?」と訊いてみたら、10年前後が一番多かったです。また、「はじめて書いた小説でデビューした」と言っている某作家について「あのひとがやってたmixiの日記には投稿歴が長いことを示唆する内容が散見された」というタレコミも新人賞探偵たる私の耳に入っています。つまり、だいたいみんな10浪しています。新人賞10浪は実質「現役合格」です。
現在、新人賞で思うように結果が出ずに悩んでいる方は、応募予定の選考委員のカッコよくキマッてる写真を見ながら「このひとらも10浪やしな」と口に出してみることをオススメします。
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)










