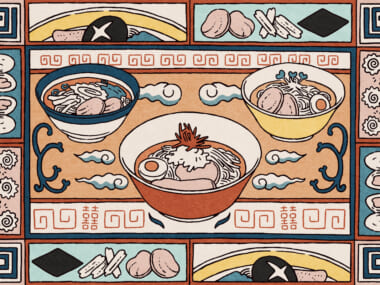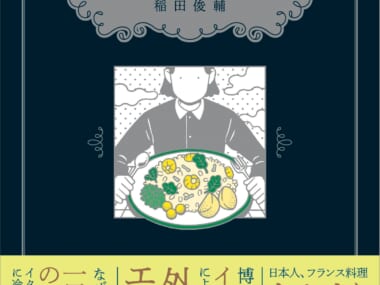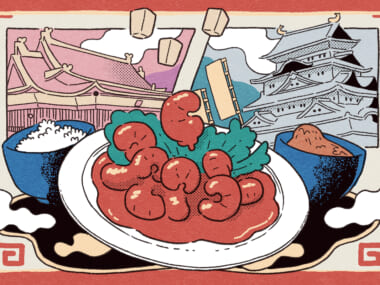2025.5.3
原材料表を見て眉を顰め……都会人に毛嫌いされる各地の「甘いお醤油」たち
日本の「おいしさ」の地域差に迫る連載。
前回は、名古屋の八丁味噌がいかにスペシャルな味噌か、ということが語られました。
今回は、おみやげ品などでもよく見かける、各地の「甘いお醤油」についてです。
醤油と味噌④ アミノ酸醤油、その数奇な物語
先日、旅行で福岡に行ってきました。いわゆる社員旅行です。岐阜に本社を置く弊社は、小さいながらも関東・東海・関西に拠点を持っていますので、この日は各エリアから総勢30名ほどが集まりました。
弊社の社員旅行は、到着日の夕方からとりあえず全員揃って宴会を行い、その後、小グループに分かれて夜中過ぎまで数軒をハシゴして食べまくります。その間に脱落や合流が繰り返され、最終生き残った精鋭たちが、深夜営業の店に再び集結して夜明けを迎える、というのが毎回のパターンです。ちなみに翌日は一応自由行動なのですが、過半数はロクに観光もせずに、昼間から飲めるところを探してゾンビのように徘徊し、帰りの便の出発時刻ギリギリまでまた数軒で食べ続けます。今書いていてその異常性に改めて気付きましたが、こういう社風が肌に合いそうな方は、ぜひ奮ってエントリーしてください。
その最初の大宴会での話です。我々は全員が飲食のプロであり、この時点ではまだ正気を保っていますから、やはり話題は、卓に並ぶその土地ならではの料理の数々についてです。まず盛り上がったのは、宴会開始と共に供された、半透明のイカの姿造りを主役とする「刺身盛り合わせ」、およびそれに添えられてきた醤油についてでした。
ご存知の方も多いでしょうが、九州の醤油は甘いです。甘さを数値的に換算すると、標準的な醤油との比較で約4倍程度になるようです。うま味の強さも特徴です。弊社のメンバーはサンプルとして少し特殊ですからあまり参考にならないかもしれませんが、この醤油に対する感想は、一定の地域性もあるように思われました。
関西民は、違和感を口にしつつも、おおむね好意的でした。そして東海民で魚市場で働いた経験もある弊社の魚番長は、「これはこれで悪くないけど、これじゃないほうが嬉しいのも確か」と冷静に評し、多くのメンバーの賛同を得ていました。
最もビビッドな(拒否)反応を示したのは関東勢です。ある江戸っ子女子(酒豪)に至っては「これは無理」と断言しました。そもそも刺し盛りの内容がおかしい、とも。ヤリイカ、ブリ、キビナゴ、タコ、タイという布陣で、そこには赤身がなかったからです。「トロとか別に要りませんけど真っ赤っかのマグロが欲しい。でもマグロにこの醤油がついてきたらブチ切れます」と、既に正気を失いかけていました。
九州民である僕としては、色々と思うところもあるのですが、いったんここでは私情は抑えて、客観的なデータを提示します。こちらが福岡でポピュラーな、ある甘口醤油の原材料表の内容です。
アミノ酸液(国内製造)、食塩、脱脂加工大豆、小麦、砂糖、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア、甘草)、保存料
わかります。言いたいことはわかる。しかし、いっとき黙りんしゃい。
これを見て、眉を顰める人の気持ちはわかります。なぜなら僕もかつて眉を顰めていたからです。あえて名は伏せますが、某グルメ漫画のオールバックの主人公なら、きっとこう言うでしょう。
「こんな醤油はまがいものだよ。来週またここに来てください。俺が本物の(以下略)」
しかし山岡さん、今はとりあえず黙りんしゃい。
記事が続きます
大豆ではなく「アミノ酸液」が主成分となるこのタイプの醤油は、「アミノ酸醤油」と総称されます。これがポピュラーなのは、何も九州だけではありません。他には、北陸、東北、中国、北海道と、一見何の脈絡もなく全国に散らばっています。容易に想像が付くと思いますが、その歴史は、そう古いものではありません。誕生したのは戦後間もないころです。その感動的なストーリーを今からダイジェストでお届けします。僕は常々、この話は、大河ドラマか朝ドラで取り上げるべきだと思っています。
時は戦後間もない1948年。ある大手醤油メーカーの二人の技術者は、頭を抱えていました。GHQの統制により、醤油の主原料である大豆がほとんど手に入らなくなることが決まったためです。しかしこのままでは、日本の醤油文化はここで途絶えてしまう。
二人は苦心し、戦中の物資不足の中で苦肉の策として開発された醸造期間を必要としない代用醤油の技術をベースに、半化学・半醸造する新しい試みで、効率と味を両立させた「新式2号製造法」を完成させました。そしてさらに、その技術を特許として独占することなく、製法を全国の醤油メーカーに教え歩きました。
各地で誕生した新式醤油は、伝統にとらわれない時代が求めるおいしさが様々に工夫されたこともあって、大人気を博しました。その大手メーカー自体は1970年にはこの製法を取りやめることになりましたが、その時に生まれた新式醤油の数々は、今もなお各地の食文化を支え続けています。

記事が続きます
各地のこの種の醤油は、最近「地醤油」とも呼ばれています。全国で流通する普通の醤油とは味わいが明らかに異なる、というニュアンスが込められているのでしょう。
しかし各地の地醤油は、味も香りも、そして原材料表の内容もよく似ています。もちろん、前述したような共通の出自を持つからです。その中で九州醤油が最も甘いのは確かですが、他の地醤油も基本的には甘めです。うま味の強さも共通しています。独特の香りもよく似ていて、不思議なことに、タイ・ベトナムなど東南アジア圏の醤油ともどこか通じるものがあります。
東京でこの種の香りに出会うことはまずありません。僕が気付いた唯一の例は、ある有名なラーメン店です。チャーシューの味付けと、おそらくカエシにも使われていたのでしょう。いろいろ調べていくと、どうも千葉のローカルメーカーで、今もひっそりと作られ続けているもののようでした。
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)