2018.10.22
熱海にかかってきた電話
介護のうしろから「がん」が来た! 第1回
「○×クリニックですが、検査の結果が出ているんですが、これから来れますか? ご家族と一緒にお願いします」
三月半ば、熱海名物の最中を買って従姉妹たち三人で、齧りながらそぞろ歩いていると、携帯にそんな電話が入った。
「今、旅行先なんで。来週の火曜日に通院予約してあるんですが」
「できるだけ早くお伝えした方がいいので、では明日の夕方五時でどうでしょう?」
土曜日の夕方五時。医院の受付終了後だ。急を要するらしい。それに「家族も一緒に」とくれば検査結果のシロクロはおのずと知れる。
「あー、はいはい。じゃ、明日うかがいます」
傍らで、夫を肺がんで亡くした従姉妹が青くなっているが、本人は至って呑気な返事をしていた。
着信音が鳴ったとき、実は老人保健施設にいる母に何かあったのではないか、と一瞬、身構えたのだ。肺炎か、イレウスか、それとも騒ぎ出して手に負えないので連れ帰ってくれ、ということか。そうではなく、自分のことだったのでほっとしていた。
自分の健康や生活、生命なんか、かまっていられない。
意識しているか否かは別にして、多くの介護者に共通する心理状態だろう。それを「献身」と間違えてはいけない。疲弊した身体と精神が作り出す自暴自棄、判断力低下状態だ。ちょうどDVの被害者が今の痛みをやりすごせば済むと、まったく回避行動を取らないまま、虐待を受け入れるのに似ている。
それはともかく「がん」という言葉自体はすでに身近なものになっていた。五年前、たまたま取材のためにうけた検査で甲状腺腫瘍が発見されていたが、父が交通事故に遭って亡くなったり、母の認知症が進んだり、といった諸々のことで検査がずっと先延ばしになっていたのだ。

昨年十一月、母が介護老人保健施設に入所し、ふっと手が空き、ああ、そうだ、と紹介状を手に駒込にある専門病院に行った。一回目の穿刺の結果は、灰色。初めて我が身のことについて医師から「がん」という言葉が発せられる。
「厳重経過観察。一ヵ月後に再検査」と言われ、宙ぶらりん状態にいた二月の初め、今度はブラジャーの右側乳首が当たる部分にぽつりと灰色のしみを発見した。
虫刺されの出血くらいのごくごく小さなものだが、頭に黄色いランプが灯った。
どこかで聞いた。乳がんの症状として乳頭からの出血がある、と。早速、ネットで「乳頭出血、がん」を検索する。確かに何件もヒットする。
自分で右側乳房を触ってみる。しこりらしきものはない。少し張っていて痛い。ということは乳腺炎か? 分泌液の色も血というより、薄い泥水か垢みたいな感じだ。
取りあえず、とかかりつけの医院に電話をして乳がん検診の予約をお願いするが、応対に出た看護師さんが遮るように言った。
「あっ、それ、もう症状出ちゃってますから、検診ではなくて直接乳腺科に行ってください」
「はぁ、症状……ですか」
「検診だと自費ですが、症状が出ていれば保険がききますからね」
すこぶるプラグマティックなお言葉に感謝しつつ、インターネットで市内の乳腺科を探し電話をする。診療予約を取ろうとすると二週間先まで一杯だと告げられたが、症状を話すと一転、一週間後の朝いちの予約を入れてくれた。
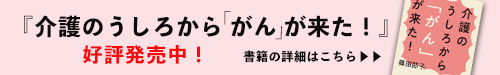
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)










