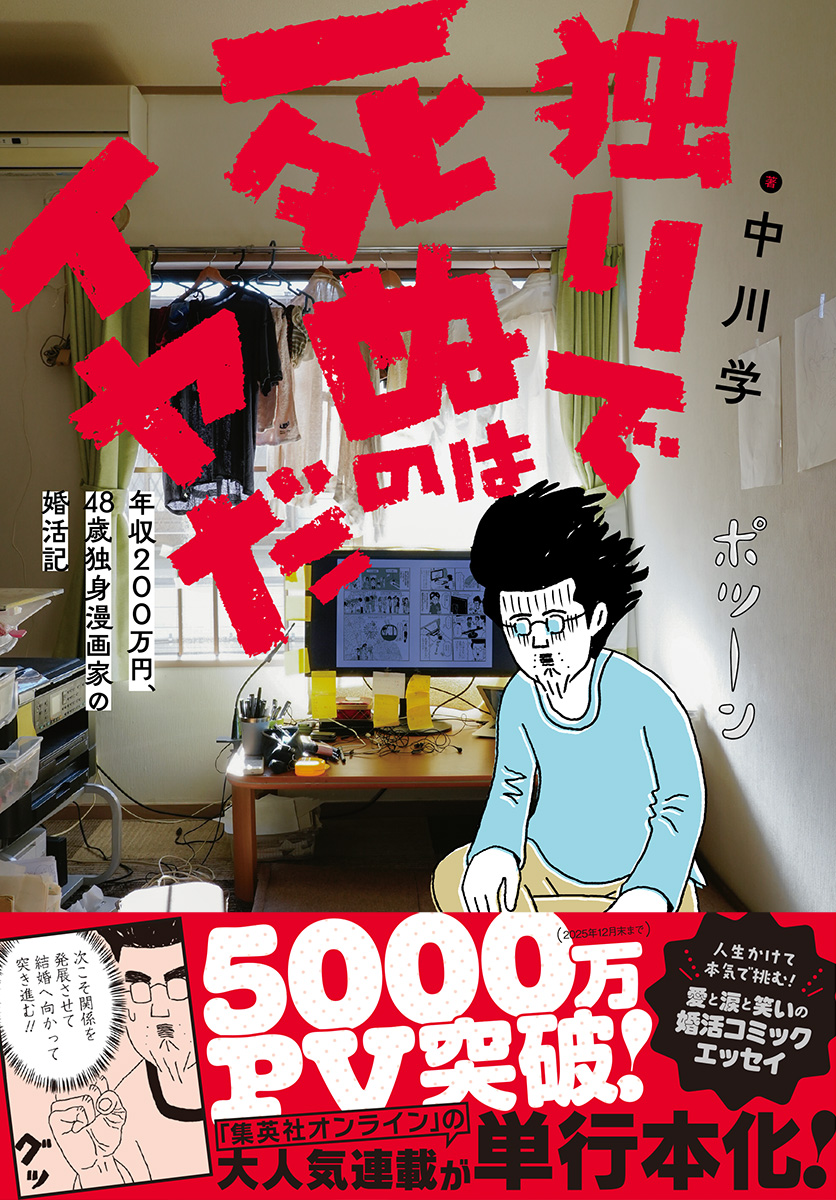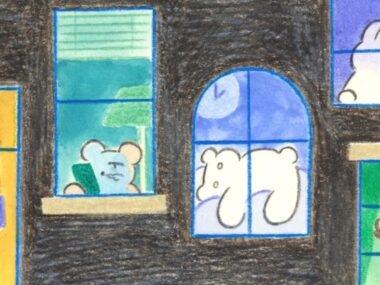2025.7.12
90年代Jホラー隆盛を後押しした「恐怖体験談の投稿」という文化【対談・吉田悠軌×廣田龍平】
本書では、昨年刊行されロングセラーとなっている『ネット怪談の民俗学』著者の廣田龍平さんをお迎えし、学校の怪談ムーブメントのさきがけとなった、学年誌やホラー雑誌、ラジオなどへの投稿文化についてお話しいただきました。
本書より一部をご紹介します。
後編では、ホラー雑誌やラジオ、テレビなどに「体験談の投稿」という形で寄せられた怪談が、「学校の怪談」ブーム、ひいては90年代のJホラーブームに与えた影響について議論します。
(撮影/齋藤晴香)

「学校の怪談」メディア化の加速
廣田 雑誌よりも記録に残りづらい、ラジオやテレビへの視聴者の投稿もありますよね。そこから広まった学校の怪談も多かったのでは。
吉田 小学生より年齢層は上がりますが、60年代から90年代にかけての「深夜ラジオ」という文化は、絶対にものすごい影響力があったはずですね。ただそれがアーカイブとしてほとんど残っておらず、我々が参照できない。それこそもう口承採集のように、当時、ラジオ番組を聴いていた人たちに取材して、その言い伝えを拾っていくしかない。
廣田 なんとなくわかっているものとしては、稲川淳二さんが『オールナイトニッポン』で話した「赤い半纏」。1977~78年頃にこの怪談が一気に女子大生の間で広まったということが、中村希明『怪談の心理学』という本に書かれていました。トイレに入った時、「赤い半纏着せましょか」といった声が聞こえてくる。その対応に失敗すると血まみれになって、赤い半纏を着たようになるという怪談。この話自体はかなり昔からあったんですけど、ラジオを通して全国に広まったとは言えますね。
吉田 稲川淳二さんの「赤い半纏」は、年配の女性から来た投稿なんですよね。番組が放送された70年代後半よりずっと昔、投稿者が女学生時代に聞いたという話。その女性は実話として投稿していますが、当時から全国的に流行っていた都市伝説、学校の怪談の一バージョンですよね。「赤いちゃんちゃんこ」のほうがタイトルとしてメジャーなんですが、稲川さんは「ちゃんちゃんこ」じゃなくて「半纏」なんだと主張している。番組でお手紙を読んだことへの責任感からだと思うんですけど。
廣田 「赤い半纏」については、早くても戦後すぐくらいに生まれた話でしょうね。女性の警察官が検証しに行って殺されてしまうんですけど、いわゆる「婦警」が登場するのは戦後のことなので。いずれにせよ古い話ですが、それが70年代終わりに広まったという。当時のラジオは大きな影響力を持っていたはずですよね。人面犬に関しても、もともとはラジオのネタだったという真偽不明の情報もあります。花子さんの名前も出ていたんですかね。
テケテケや、鉄道事故で下半身が切断された怪談などは、ラジオで語られていた可能性は高いと思います。ただこのあたりは本当に、リアルタイムで聴いていたわけではないのでわからないし、確認のしようがない。
吉田 芸能人に取材した怖い話というのは、年代などが特定しやすいんですけどね。特に雑誌『明星』に載っているような、芸能人が語っているけど、その人の実体験ではないような話。『明星』79年9月号には、藤谷美和子が鉄道事故による下半身切断の怪談を披露しているので、少なくとも70年代末より前には広まっていたんだな、とわかる。同じ号ではザ・ハンダースのアパッチけんが、カシマさんのかなり古い事例を語ってくれている。高校2年の夏合宿で聞いたというので、プロフィールから逆算すると73年の夏だったとわかります。
廣田 70年代から90年代くらいまでのメディアでは、芸能人に怪談を聞くことは多かったですね。『ハロウィン』から派生したホラー雑誌『ほんとにあった怖い話』(現『HONKOWA』)では、芸能人の心霊体験を、本当によく見つけてくるなっていうほど、毎号ずっと載せています。
それと同時期に、漫画家による心霊体験も出てくるわけですよね。山岸凉子の『ゆうれい談』(73年)が、有名なものとしては最初ですかね。また『ほんとにあった怖い話』がまさにそうですけど、投稿された体験談が漫画化されていくようになる。

吉田 『ハロウィン』で読者投稿が初めてマンガ化されたのが、花子さん系の話でした。86年5月号の「トイレに響く笑い声」、東京都江東区、永田由美さんからの投稿。女子トイレの右から2番目の個室にお化けが出るんだということで、友達と二人で行く。やはり複数人で実験するんですね。そしたら「ふふふ」って笑い声が聞こえてきて、扉の鍵が開かなくなって体当たりで逃げるという。花子さんの名前こそ出てこないけれど、花子さん系の話。もう一つが事故物件系の話なんですよね。この2話が創刊初期の『ハロウィン』で初めて漫画化されて、この後、投稿怪談の漫画化がどんどん増えていく。
廣田 この漫画のすぐ横に「〝学校の七不思議〟をおしえて下さい‼」とあります。この頃はまだ「学校の怪談」ではなかった。少なくとも『ハロウィン』の場合は。国会図書館のデジタルコレクションで「学校の七不思議」を検索したら、ある時期から『ハロウィン』にしか出てこなくなるという感じになります。あとコックリさんキューピットさんなど、「次号は、〝学校の七不思議〟大特集‼」ともある。
吉田 もうこの時点から学校に注目していることが窺えます。
廣田 これはけっこう来そうだな、という感触はあったんでしょうね。やはり編集者たち自身の子ども時代に既にあったからなのかな。
その他の雑誌でも、『My Birthday』もそうだし、『サスペリア』93年の増刊号で、『恐怖体験実話コミック』というものが出てくる(7号まで刊行)。再現漫画が多いやつですね。表紙に「まんが家&読者の」とあって、つまり漫画家と読者の体験談なわけです。そもそも『ほんとにあった怖い話』が「マンガ家&芸能人&読者の」という風になっていました。そういう感じで集めていたんだな、というのがわかります。
「学校の怪談」ブームがあった90年代とは、ホラー雑誌ブームの時代でもあったんです。多くのホラー雑誌で、読者投稿が漫画化される。それがさらに映像化される。『ほんとにあった怖い話』ビデオ版が制作されたのが91年。いわゆるJホラーのさきがけとも言われる、斬新な恐怖表現が使われた作品とされますが、それもまず投稿が最初にあった。
吉田 それこそJホラーの幽霊の描き方の基礎となった、と俗説的には言われている『ほんとにあった怖い話』ビデオ版第2弾の、「夏の体育館」。雑誌『ハロウィン』で掲載された話がその後のコミック『ほんとにあった怖い話』では第4巻に収録されています。埼玉県の茂手木裕美さんという人の投稿となっていまして、ババサレの話である「婆去れ!」も投稿している常連さんです。
投稿の再現漫画である「夏の体育館」は、特に大きなことは起こらない、かなり実話怪談らしい話です。それを鶴田法男監督が映像化し、その赤い女の幽霊描写が、黒沢清に大きな影響を与えた。そこからまた黒沢清が『学校の怪談 物の怪スペシャル』の「花子さん」で赤い女を登場させる。そのあたりのJホラー作品が、私がよく言及している現代怪談の赤い女のイメージにもおそらく影響している。それを大元まで遡ると、『ハロウィン』への埼玉県・茂手木裕美さんの投稿に行き着くんですよね。一通の手紙が、漫画化・映像化による再話によって、あらぬ方向へと大きな影響を与えていった。それが最終的には、現代の学校の怪談へ出てくる赤い女にまで繋がっている。
廣田 映像化ということでは、『ほんとにあった怖い話』は、今でも毎年、フジテレビが特別番組としてやってはいますよね。あれも基本的には子ども向けの番組という感じではあります。
吉田 今のテレビ番組としての『ほんとにあった怖い話』は、投稿というより実話怪談のほうにも寄っていて。私の知人でいえば煙鳥さんの実話怪談を映像化しています。読者投稿からの映像化という、初期のオリジナルビデオ版や、別番組ですが『あなたの知らない世界』などとは、ちょっとスタンスが異なっている感じがします。実話怪談が広まって以降、怪談における投稿というものが駆逐されているのかもしれません。今、読者投稿の漫画化となると、ご近所トラブルや嫁姑問題のような、レディースコミック的なもの以外、あまりないですよね。怪談となると、当時の隆盛ぶりに比べたらかなり減っている。
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)