2019.11.15
特別鼎談「ジェンダーバイアスと表現についての考察」~後編〝表象の中のジェンダーバイアス〟
小宮 先ほど言ったセクシュアル・マイノリティの話でいえば、ちょっと前にドラマ『おっさんずラブ』が話題になったり、それこそ漫画原作で『弟の夫』や『きのう何食べた?』がドラマになったりしていますよね。ゲイの話ばかりじゃないかっていう批判はあるんですけど、ちょっとずつ取り上げられるようにはなってきていて。ジェンダーの問題だと逆に「それで大ヒット」のような作品はあまりないかもしれませんが……。
宮川 先生は女性の表象についても言及されていますが、CMでも何度も何度も炎上しているのに、女性差別的な表現がどんどん出てくるというのはどうしてなんでしょう。出てくるたびにみんながっくり、という感じになるんですが。
小宮 企業文化が大きいんじゃないかと思います。一昨年、マスコミ倫理懇談会というイベントに呼ばれていって、CMの中のジェンダーバイアスについて話したんですが、当たり前ですけど広告会社もクライアントの企業も、何も炎上したいと思って作っているわけではないんですよね。よく炎上広告とか炎上商法とかいわれますけど、別に狙って炎上させているわけではない。企業イメージも悪くなったりするわけですから。
にもかかわらず、性差別的に見える表現が繰り返し出てきてしまうわけですから、「何が問題なのか」を、チェックする側の人たちが十分詰めて考えられていないんだと思うんです。テレビ局の管理職の女性がおっしゃっていたんですけど、今、管理職をやっている女性たちって均等法第一世代なんですよね。でも、その世代の総合職で就職した女性って、今や8割は退職してるんです。逆に言うと退職せずに働いているのはがんばって生き残ってきた方々で。そうした中で男性文化に自分たちが染まりすぎていなかったか、ということを今反省していらっしゃったりする。後に続く世代の人たちのために何ができるかとか、ちゃんと考えてることは考えているんですよね。ただ具体的にどうするかというところで、これまでの考え方から抜け切れていないところがあるのかなと思います。(※3)
宮川 私もその世代ですが、いわゆる社会で活躍している女性の「自分ががんばったから勝ち上がって生き残っている、差別されていない」といった発言を目にすることがあり、気になっています。意外と無意識にジェンダーバイアスがあったりして、次の世代にバイアスを残してしまったのではないかというのは自分も含め反省すべきかと思っています。(※4)

これからの表現のあり方
宮川 そろそろまとめとして、これからの表現のあり方を考えてみたいと思います。
小宮 小説であれ漫画であれ、作品の中にどんなバイアスがあるかは、やっぱり社会的な背景をある程度知ることで初めて見えてくるという側面があると思うんです。職場や家庭で多くの女性が経験する抑圧がどのようなものであるかについて、仮に自分には経験がないとしても、ある程度勉強していたら考えられることはある。考えられたら特定の表現とそうした抑圧との繋がりも見えてくるようになる。そういう意味では作品の作り手である作家さんや、編集さんにとって、そういう勉強は作品を社会に届ける側としては必要ではないかと思います。
楠本 表現者が、表現者として作品を世に出す時に、ジェンダーバイアスをはじめとする様々な偏見を自ら踏襲することで、さらにそれを強化するかもしれないことを「選択するのか」ということを意識していく必要があるんじゃないかと思います。
そのためにはもちろん作家自身が、自身の感覚を省みたり、積極的に学んでいくことが大切ですね。(※5)
けれど、それでもまだ自分では気づけない無意識のバイアスを持っている可能性はあるわけで、そんな時には編集者なり、周りがバックアップとして指摘してくれるという、そういう関係が理想的だと思います。

小宮 作品は現実をただ写したものではないですから、意識しているかどうかにかかわらず描き方の取捨選択をしている、自分が注目している部分を描いてるんだっていうことを考えておくことは大事なことだと思います。もちろん、一義的にこれは良くてこれはダメみたいな機械的な基準というものが作れるわけではないと思うんですよ。作品は解釈に開かれているものですし、そういうものとして作ることもあるでしょうから。
ただ、一義的な基準を作るのは難しいにせよ、自分たちがこういうものをこういう観点で作った、無意識でやってるんじゃないんだということが何らかの形で説明できるような作品作りというのがあるはずだと思うんですよね。読者もそれを読んで様々な感想を言ったり、場合によっては鋭く批判したりして、そうした反応がフィードバックされて作品作りに何らかの形で託されて、より多様な作品が出てくるようになる。そういう市民どうしのやりとりは、まさに表現の自由が守りたいものであるはずなんです。
そういう形で実際の社会に起こっている様々な問題を踏まえた上での作品作りになっていくことを期待したいなと思います。
宮川 とても建設的な意見交換になったと思います。ありがとうございました。
●前編にもどる
※1 出版社や編集部、または作家によっても差異はありますが、基本的には漫画連載の場合は「ネーム」という絵コンテの段階で担当編集者のチェックが入り、打ち合わせと、必要があれば修正、その後作画に入ります。編集部内では校了時にゲラ(校正紙)を回覧し、担当編集が見落としたことなどを洗い出し、問題があった場合は作家と相談の上修正します。連載スタート時、もしくは読みきりの場合は、担当編集のオーケーの出たネームが会議にかけられ、掲載か否かが決まります。(楠本)
※2 イギリスで2019年6月、広告の中のジェンダーステレオタイプが禁止になったという記事
日本語版
※3 男性中心的な企業文化と広告炎上
治部れんげさんというジャーナリストが『炎上しない企業情報発信』(日本経済新聞出版社、2018年)という本で「広告炎上」について考察されているのですが、要因のひとつとして女性社員、女性管理職の不足と、その中での「女性の男性化」に注意を促しています。内閣府が毎年出している男女共同参画白書には、各種メディアにおける女性の割合がまとめられているのですが、民間放送各社における女性管理職の割合は2018年時点で14.7%、新聞・通信社では6.6%ということなのでまだまだ低いですね。女性が「特別な存在」としてではなく意思決定に関与できるようになるためには3割が必要だと言われています。
一般的な企業に目を向けても、厚生労働省の賃金構造基本統計調査では、課長級の女性の割合は2018年時点で11.2%、部長級では6.6%しかいません。国立社会保障・人口問題研究所の調査では、第一子出産前に働いていた女性の約半分は出産で仕事を辞めています。正規の職に就いていた場合でも3割は辞めてしまうので、女性にとって出産・育児はキャリアと引き換えという状況はまだ消えていません。家事育児負担を一人で抱え、夫の収入に依存して生活することは人生の選択肢を狭めますし、離別や死別による貧困リスクもあります。「男が外で働いて女が家で家事育児(+補助的労働)」という「男性稼ぎ主モデル」のもとで女性たちが感じている息苦しさや生きづらさを、男性中心的な文化の中で広告の作り手が十分に想像できていないのかもしれません。(小宮)
※4 自分ががんばったから勝ち上がって生き残っている、差別されていない
『お砂糖とスパイスと爆発的な何か』北村紗衣著(書肆侃侃房、2019年)に「内なるマギー」という、マーガレット・サッチャー的な「女性も男社会に同化して成功せねばならない」という強迫観念についての記述があります。サッチャーは女性の成功の一つのモデルかもしれませんが、帝国主義、差別、弱者の搾取などの象徴でもあります。「あなたが頑張って成功するのに、他の女性を助ける必要なんてありますか?」「なぜ、自分で努力をしない人を気遣うんですか?」といった考えを内面化してしまいがちな女性に著者は「そんなわけありません。マギーの言うことなんか聞いてはいけません」と断言しており、まさに今重要な指摘だと感じました。(宮川)
※5 今回、ジェンダーについてもっと考えたいと思われた方には私の大学時代の師であり、また小宮さんの大学院時代の師でもある江原由美子先生の『ジェンダー秩序』(勁草書房、2001年)をお勧めします。緻密な学術書でありながら後半感動的ですらある、繰り返し読みたい名著。入門書としては、『ジェンダーの社会学 入門』江原由美子/山田昌弘著(岩波書店、2008年)や『はじめてのジェンダー論』加藤秀一著(有斐閣、2017年)がわかりやすくお勧めです。(楠本/小宮)
構成・文/宮川真紀
撮影/齊藤晴香
※本記事は2019年5月に実施された鼎談をまとめ、加筆したものです。
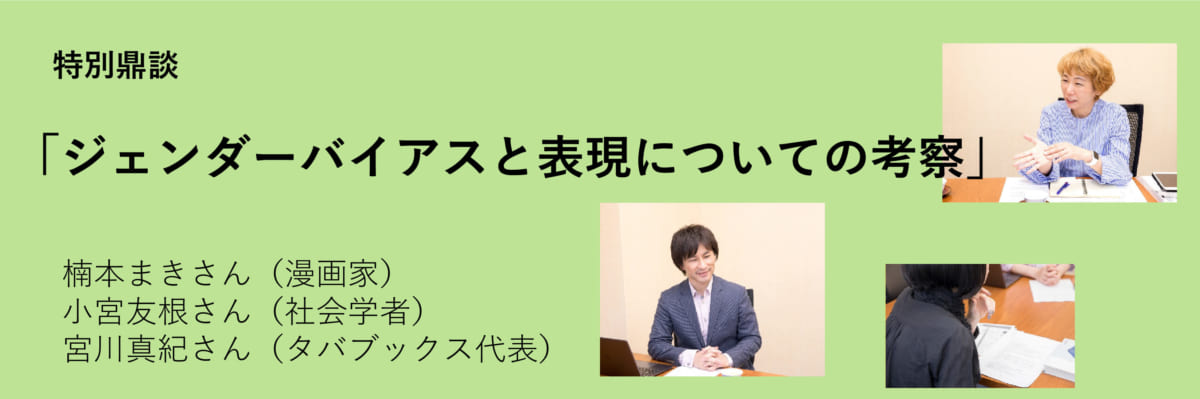
![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)












