2021.7.11
虐待サバイバーの菅野久美子さんが、ストリップ劇場で母と共有した「魔法」
「毒親」や「家の圧力」に深く切り込むコミックエッセイです。
「よみタイ」連載時(2020年5月〜2021年4月)から、SNSなどで大きな反響を呼んだ本作。
単行本化にあたり、親との関係に苦しんできた経験をもつ文化人の方々も、様々な感想を寄せてくださいました。
そのメッセージを連続書評企画としてお届けします。
第1回は、ノンフィクション作家として生きづらさや社会問題に関する記事を多数執筆している、菅野久美子さんです。
自身も虐待サバイバーである菅野さんは『実家が放してくれません』をどのように読んだのでしょうか。
(構成/「よみタイ」編集部)
封印してきた母に対する愛憎
『実家が放してくれません』は、これまで封印していた私の母に対する愛憎を、ザクザクとえぐり出してしまった。それほどまでに心に深く刺さる作品であった。
本作には、毒母のもとに育ち、親になるのが怖いという主人公のアサが、自らの家庭を持つようになり、母と決別するまでの奮闘が描かれている。アサの母は、リアルな姿としては現れず、いつも黒い人影となって、アサの心に忍び寄る。そして子育てと仕事でヘトヘトのアサの生活にするりと入り込み、ヒルのように吸いつくし、コントロールしようとする。母は子供にとって強大で、そこに立ち向かうには圧倒的な痛みと凄まじい傷を伴う。
それは、自分との対峙でもあるからだ。
母親によって手酷く心を傷つけられ、まるで戦災孤児のようにボロボロの少女時代のアサ。大人になっても母の称賛を欲しがるアサ。母親を否定することが自分の土台を否定することだと知るアサ。自分と違って何をしても許される息子に嫉妬を覚えるアサ。母が世界の全てを憎んでいたように、自らも取り巻くものを憎んでいることに気づくアサ……。
アサがそんな自分に直面し、母との闘いに挑む姿には、思わず息を呑む。しかしページが進むにつれて、その「痛み」の先にある発見やアサを通じた追体験こそが、実は大きな救いとなることに気づかされる。

秀逸だと感じたのは、アサが自分の息子を突き飛ばす描写だ。アサはイヤイヤ期の息子と向き合う中で、「どうしてそんなに聞き分けがないの?」と思わず手で息子を振り払ってしまう。その瞬間、後悔とともに「母に注がれた毒は息子に手渡せば楽になるんだ」という感情を身をもって体験する。アサはこの出来事によって、母もまた誰かに毒を注がれたのだろうかと、思い巡らせる。だからこそ、その連鎖を終わらせたいと考える。
――私はきちんと終わらせなきゃいけない。母の執着と、私の依存を。私の中で母を殺さなければいけない――。
私はそんなアサのまっすぐな言葉に心を揺さぶられる。実は私自身、アサと同じく虐待サバイバーだからだ。
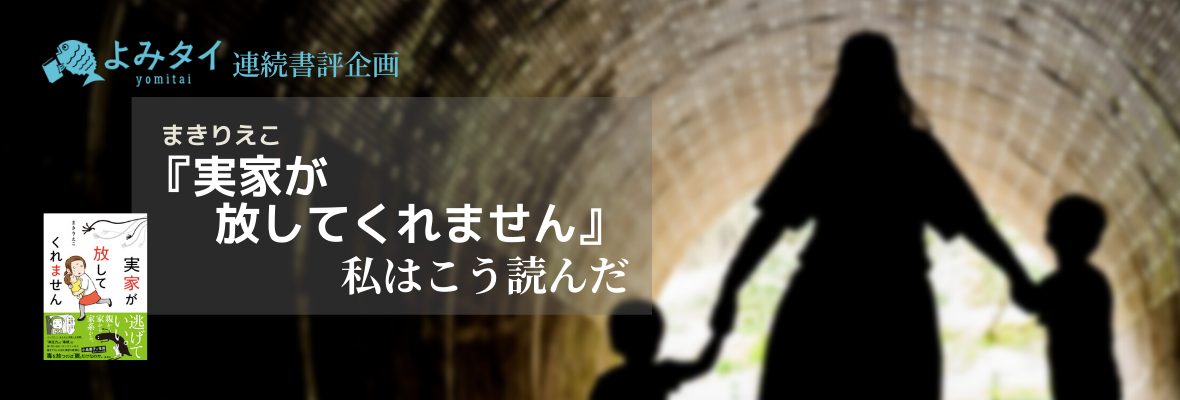

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)










